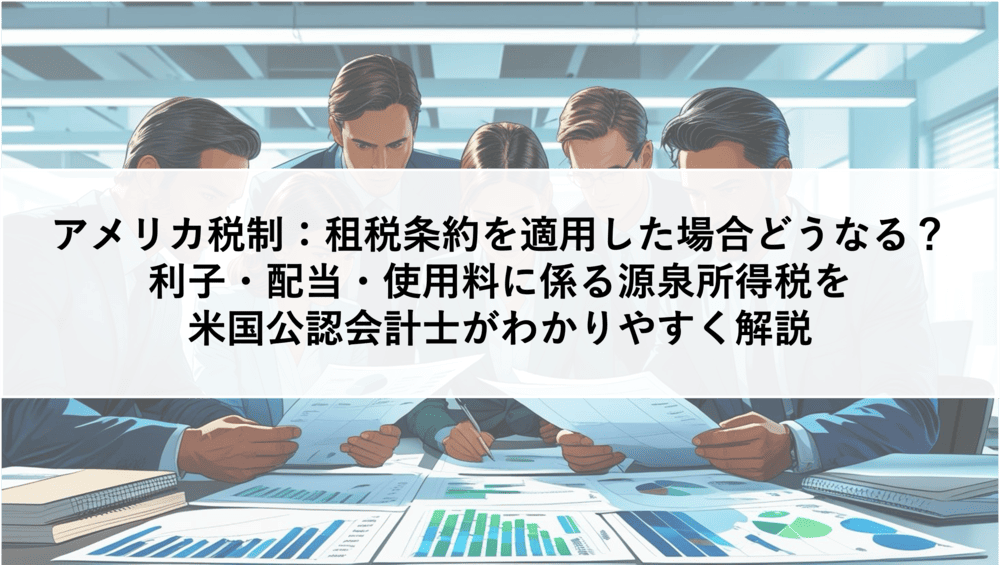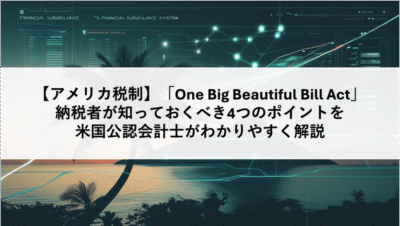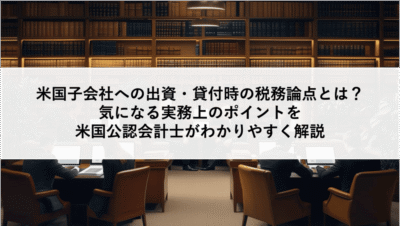日本の企業が米国の企業と取引を行い、利子・配当・ロイヤルティ(使用料)などを受け取る場合、「何もしなければ30%の税金が引かれる」という事実をご存じでしょうか?これは、米国の国内法によって定められた「源泉徴収」という制度によるもので、支払者である米国企業が受取金額から一定の税金を差し引き、米国歳入庁(IRS)に納付する仕組みです。つまり、日本側の法人には7割しか入金されないというのが、米国取引の“デフォルトルール”なのです。
しかし、これは避けることができます。そのカギを握るのが、「租税条約」です。本記事では、米国BIG4で国際税務の実務経験を積んだ会計士が、この30%源泉税の仕組みと回避のための条約活用法、条約適用に際して準備すべき資料を、実務の視点からわかりやすく解説します。
はじめに:米国からの支払いは「30%の源泉徴収」が原則
米国法人から利子、配当、あるいは使用料(ロイヤルティ)の支払いを受ける日本の法人が、まず理解すべき最も重要な原則があります。それは、米国の国内法に基づき、これらの米国源泉の所得に対しては原則として「30%の源泉所得税」が課されるという事実です 。この税金は、支払いを行う米国の法人(源泉徴収義務者)が、日本の法人へ送金する前に徴収し、米国の歳入庁(IRS)へ直接納付する義務を負っています。
つまり、何の手続きも行わなければ、受け取るべき金額の7割しか日本法人には残らないことになります。この30%という高い税率は、多くの日米間取引において収益性を大きく損なう要因となり得ます。
しかし、この厳しい原則には重要な例外が存在します。それが「日米租税条約」です。この条約は、二重課税を排除し、両国間の投資や経済活動を促進することを目的としており、原則として米国の国内法に優先して適用される効力を持ちます。この条約の特典を適切に活用することで、30%の源泉徴収税率を大幅に引き下げ、場合によっては源泉徴収を免除させることが可能になります。
ただし、その適用は自動的に行われるものではありません。日本の法人が自ら、条約の特典を受ける資格があることを証明し、所定の手続きを踏む必要があります。その証明がなければ、米国の支払者は法律に基づき30%の税金を源泉徴収せざるを得ません。したがって、条約のメリットを受けられるかどうかは日本側の企業が制度を正しく理解し、きちんと対応できるかにかかっています。
米国源泉所得税の仕組み:FDAP所得と源泉徴収義務
日米租税条約の解説に入る前に、その土台となる米国の国内法上の源泉徴収制度について正確に理解することが不可欠です。なぜなら、租税条約はあくまで国内法の原則に対する「特例」として機能するからです。ここでは、どのような所得が課税対象となり、誰が徴収義務を負うのかという基本構造を明らかにします。
FDAP所得(Fixed, Determinable, Annual, or Periodical Income)の定義
米国の源泉徴収制度が対象とするのは、特定の種類の所得であり、これを「FDAP所得」と呼びます。これは直訳すると「固定的、確定的、年次または定期的な所得」を意味し、主に受動的な投資から生じる所得が該当します。ご参考に、IRSはFDAP所得の例として以下のものを挙げています。
- 利子 (Interest)
- 配当 (Dividends)
- 賃貸料 (Rents)
- 使用料 (Royalties)
- 給与、報酬、手数料 (Salaries, wages, compensations, commissions)
- 年金 (Pensions and annuities)
そして、本記事で取り扱うFDAP所得は、経費控除が一切認められない「グロスベース」で課税されるのが特徴となっています。つまり、受け取る金額の総額に対して、源泉徴収税率が適用されることになります。
源泉徴収の原則:税率30%と支払者の義務
米国を源泉とするFDAP所得を米国外の法人へ支払う場合、米国の国内法が定める源泉徴収税率は一律30%です。この税金を徴収し、IRSに納付する法的な責任を負うのが米国の支払者である「源泉徴収義務者(一般に、Withholding Agentと言います)」です。
源泉徴収義務者の責任は非常に重く、たとえ支払先の外国法人が租税条約上の特典を受ける資格を持っていたとしても、適切な証明書類が提出されない限り、30%の税率で源泉徴収する義務があります。もし源泉徴収を怠った場合、その支払者自身が未納分の税金および罰則を負担するリスクを負うことになります。
この仕組みが、日本の法人にとっては極めて重要です。余談ですが、米国の取引先がなぜ「フォームW-8BEN-E」といった書類の提出を厳格に求めてくるのか、疑問に思ったことはないでしょうか。その背景にはこのような厳格な法的義務と彼らにとっても小さくないコンプライアンスリスクが存在します。支払者が自らを守るため、受領者が条約上の特典を受ける資格があることを正式に証明する書類を要求するのは、当然のプロセスといえます。さらに、支払いの性質が不明確な場合、例えば、それが米国源泉のFDAP所得なのかどうか判断できない場合、源泉徴収義務者はそれが米国源泉の課税対象所得であると推定し、30%の源泉徴収を行わなければならないという規則もあります。
したがって、受領者側が自社の受け取る所得の性質を明確にし、条約適用のための手続きを能動的に進めない限り、30%という高い税率が自動的に適用されてしまうのです。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
日米租税条約による特例:源泉地国課税の軽減・免除
米国内国歳入法(IRC)が定める30%の原則に対し、日米租税条約は強力な軽減措置を提供します。この章では、条約がどのように国内法に優先して適用されるのか、そして、日米間の取引で特に重要な「配当」「利子」「使用料」について、条約が定める具体的な軽減・免除税率を条文に沿って解説します。
日米租税条約の概要と国内法への優先適用
租税条約は、二国間の合意に基づき締結される国際的な約束事です。日本国憲法第98条第2項には、日本国が締結した条約を誠実に遵守することが規定されており、これは一般に、国内法と条約の規定が抵触する場合には、条約の規定が優先して適用されることを意味します。米国においても同様の考え方がとられており、租税条約の適用により、国内法で定められた30%の税率よりも有利な条件(低い税率や免税)が規定されている場合、その条約の規定が適用されることになっています。
現行の日米租税条約は、2003年に署名され、その後、数度の改正を経て現在に至ります。特に重要なのが、2019年に発効した改正議定書で、これにより源泉所得税に関する規定が納税者にとって更に有利な内容に更新されました。
配当支払いに対する軽減税率(日米租税条約 第10条)
米国子会社から日本の親会社へ支払われる配当は、両社の資本関係に応じて、源泉徴収税率が段階的に設定されています。これは、両国間の直接投資を促進するという条約の政策的な意図を反映したものです。以下に、それぞれどのような条件で軽減税率ないし免税が適用されるのか、詳しく解説していきます。
まず、もっとも有利な「免税(0%)」が適用されるのは、日本の親会社が米国子会社の議決権付株式の50%超を、配当の支払義務が確定する日を末日とする6ヶ月間継続して所有している場合です。この場合、米国での源泉徴収は完全に免除されることになります。2019年の改正議定書によって、それまで必要とされていた12ヶ月以上の保有期間が6ヶ月以上に短縮され、より利用しやすい制度となりました。
次に、免税の要件は満たさないものの、日本の法人が米国子会社の議決権付株式を10%以上保有している場合には、源泉徴収税率が5%に軽減されます。
一方、上記のいずれの条件も満たさない、いわゆるポートフォリオ投資(例:10%未満の出資による一般的な上場株式投資)に対する配当には、10%の源泉税が課されます。
このように、株式の保有割合と保有期間によって適用される税率が異なるため、自社の持株状況を正確に把握し、適切な税率の適用を受けることが重要です。
利子支払いに対する免税(日米租税条約 第11条)
米国法人から日本の法人へ支払われる利子については、日米租税条約により、原則として米国での源泉徴収が免除されるという非常に有利な取り扱いが認められています。具体的には、米国で発生し、日本の居住者(法人を含む)が受益者となる利子に対しては、通常課される30%の源泉税が免除されることになります。これは、2019年に発効した改正議定書によって免税の対象範囲が拡大されたものであり、日米間の資金移動や融資をより円滑に行うための重要な制度的措置と位置づけられています。
ただし、この原則には重要な例外があります。支払者の利益や資産価値の変動などに応じて金額が決定される「利益連動型利子(contingent interest)」については免税の対象とはならず、10%の限度税率が適用される場合があります。これは、実質的には配当に近い経済的性質を持つ支払いが、利子として偽装されることによる租税回避を防ぐための規定となっています。
使用料(ロイヤルティ)支払いに対する免税(日米租税条約 第12条)
技術やブランドなどの無形資産の使用に対して支払われる使用料(ロイヤルティ)についても、日米租税条約は投資や技術交流の促進を目的として、米国での源泉課税を完全に免除する規定を設けています。
具体的には、米国で発生し、日本の居住者が受益者となる使用料に対しては30%の源泉税が免除され、0%の税率が適用されます。ここでいう「使用料」とは、文学的・芸術的・科学的著作物(映画フィルムや放送用テープを含む)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式または秘密工程の使用、あるいはその使用権に対して支払われるすべての種類の対価を含みます。この免税措置は、テクノロジー企業やコンテンツ産業をはじめとする、知的財産を基盤とした多くの日本企業にとって、米国市場でのビジネス展開を後押しする重要なメリットとなっています。
条約特典を受けるための重要要件:「適格居住者」とLOB条項
前章で解説した有利な軽減税率や免税措置は、残念ながら誰でも無条件に享受できるというわけではありません。日米租税条約には、条約の特典を不当に利用する行為を防ぐための極めて重要かつ厳格なルールが存在します。それが「特典制限条項(Limitation on Benefits、通称、LOB条項)」です。この章では、LOB条項の目的と、その核心である「適格居住者」となるため基準について解説します。
なぜLOB条項(特典制限条項)は存在するのか?
LOB条項が設けられている最大の理由は、「条約漁り(トリーティショッピング)」を防止するためです。条約漁りとは、日米いずれの国の居住者でもない第三国の居住者が日米租税条約の特典(例えば、源泉税の免除)を得るためだけに、日本や米国に名目上の会社(ペーパーカンパニー)を設立し、その会社を通じて投資を行うといった租税回避行為を指します。
もしLOB条項がなければ、例えばタックスヘイブンに拠点を置く投資家が、日本にペーパーカンパニーを設立し、その会社を経由して米国に投資することで、本来であれば課されるべき30%の源泉税を不当に免れることが可能になってしまいます。
このような条約の濫用を防ぎ、日米租税条約の特典が、両国で実質的な経済活動を行っている適切な居住者にのみ与えられるようにするための「門番」の役割を果たすのが、日米租税条約 第22条に規定されているLOB条項なのです。したがって、条約の特典を申請する日本法人は、まずこのLOB条項の要件をクリアし、自らが「適格居住者(Qualified Resident)」であることを証明しなければなりません。
適格居住者(Qualified Resident)となるための主要テスト
日米租税条約第22条は、法人が「適格居住者」と認められるための複数のテストを定めています。日本の法人はこれらのうちいずれか一つを満たすことで、原則として条約の特典を受ける資格を得ます。以下に、法人にとって特に重要な判定基準を整理します。
-
適格者基準
個人、政府、一定の上場会社や公益法人、年金基金、または以下の条件を共に満たす場合。
・居住地国の適格者により支配されている法人 かつ
・第三国への過度な所得移転がない法人 -
能動的事業活動基準
居住地国で実質的に事業を行っており、その事業と関連・付随する所得を得ていること。尚、相手国で得る所得がその国での事業活動に基づく場合には、居住地国で行っている事業も実質的なものである必要があります。 -
当局の認定
上記①②を満たさない場合には、日米両国の当局による認定を受ければ、特典の適用が可能です。
なお、以下のようなケースに該当する法人は、条約特典を受けられない(LOB条項を満たさない)可能性があるため注意が必要です:
-
ペーパーカンパニー(実体のない法人)
名義上は存在していても、オフィスや従業員、実際の事業活動がない法人。 -
外国ファンド傘下の日本SPC(特別目的会社)
外国の投資ファンドが投資目的で設立した、日本国内に事業実態のない会社。 -
所得の大半を第三国に支払う構造の日本法人
日本で得た利益を、ロイヤルティやサービス料などの名目で他国へ流している構造。 -
非公開会社で、適格者以外の外国株主が多数を占める法人
株式を公開しておらず、主要株主が条約上の「適格者」に該当しない外国法人である会社。 -
設立間もないスタートアップで事業実態がまだない法人
まだ営業が開始されていない、売上や雇用の実績が乏しい段階の企業。 -
海外の個人が実質支配する日本法人(形式上は日本法人でも)
法人の設立国は日本でも、資金や経営判断がすべて外国に依存しているケース。 -
受動的投資活動しか行っていない法人(例:純投資会社)
実際のサービスや製品の提供は行わず、利子・配当などの受取のみを目的とした法人。 -
日本法人を通じて米国との取引だけを行う導管会社(例:中間持株会社)
実質的に米国との取引のためだけに設立され、機能やリスクを持たない法人。
とはいえ、上記のような特殊なケースを除けば、通常の日本法人であれば多くの場合、日米租税条約の適用を受けられる=テストの基準(LOB条項)を満たすと考えて差し支えありません。実務上は、「こうした基準が存在する」ということをあらかじめ理解しておき、該当する可能性がある取引や構造の場合には慎重に確認する、という姿勢が大切です。
実務編:租税条約の適用に向けて準備すべき書類リスト
これまでの章で、米国源泉所得税の原則と日米租税条約による特例、そしてその特例を受けるためのLOB条項という理論的な枠組みを解説しました。この章では、それらの知識を実務に落とし込むための「具体的な手続き」と「何を準備すれば良いのか」について、日本の法人が直面する典型的なケースを想定して詳述します。
日本法人が米国子会社から利息を受け取る場合の実務対応
ここでは、日本法人が米国子会社に資金を貸し付け、その利息を受け取るケースを例にとり、実際にどのような手続きが必要で、どの書類を準備すべきかを具体的に説明します。以下のステップと書類を適切に準備・管理することで、日米租税条約による源泉税の免除(0%)を確実に享受することができます。
必要となる手続き・書類一覧
-
Form W-8BEN-E(日本法人が作成・米国子会社サイドで保管)
日本の親会社が「外国法人であること」および「日米租税条約による免税の適格者であること」を証明するための届出書です。米国子会社は、このフォームを利息の支払日までに受領・保管しておく必要があります。IRSへの提出義務はありませんが、税務調査時に提示を求められるため、正確かつ紛失のないよう保管が必要です。 -
Form 1042-S(米国子会社が作成・IRSに提出)
源泉徴収の有無にかかわらず、外国法人に対する支払いを行った事実は報告義務の対象となります。したがって、租税条約により源泉税が0%であっても、米国子会社はこのフォームを用いて支払い内容をIRSに報告する必要があります。 -
Form 1042(米国子会社が作成・IRSに提出)
Form 1042-Sで報告した支払い情報を集計し、源泉税に関する年間の総括を報告するための書類です。源泉徴収額がゼロであっても提出義務があり、IRSはこのForm 1042と1042-Sを照合して整合性を確認します。 -
Form SS-4(該当する場合のみ、日本法人がIRSへ申請)
日本法人が米国の納税者番号(EIN)を保有していない場合に、EINを取得するための申請書です。W-8BEN-Eの記入欄にEINが必要となるため、結果的に条約適用の大前提としてこの取得が必須となるケースが多くあります。発行までに数週間程度かかることがあるため、早めの対応が重要です。
このように、日米租税条約の特典を実務に落とし込むためには、正しいフォームの準備と事前準備が重要となります。初めて条約適用を行う場合には、不安や不明点も多いかと思いますが、今回ご紹介したポイントを押さえておけば、大きな抜け漏れは防げるはずです。
なお、租税条約は国ごとに異なる条文・要件が存在しますので、他国との取引に応用する場合は、その国との条約内容を個別に確認するようにしてください。また、事案によっては解釈が分かれることもあるため、必要に応じて専門家にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
本稿では、米国から利子・配当・使用料を受け取る日本法人が直面する源泉所得税の問題について、米国の国内法の原則から日米租税条約による特例、そしてその適用を受けるための具体的な実務手続きまでを網羅的に解説してきました。
本記事で解説した内容は、多くの標準的な取引に対応可能ですが、国際税務は常に個別具体的な事情によって判断が分かれる分野です。特に、以下のような状況に該当する場合、自己判断で手続きを進める前に、専門家への相談をお勧めします。判断に迷う場合には、当サイトが運営する匿名・無料の相談窓口「みんなの国際税務Q&A」をご活用ください。個別の税務アドバイスを提供するものではありませんが、一般的な見地からの専門家の回答を得ることで、問題解決に向けた信頼性の高い第一歩を踏み出すことが可能です。国際税務の課題解決の一助として、お気軽にご利用いただければ幸いです。