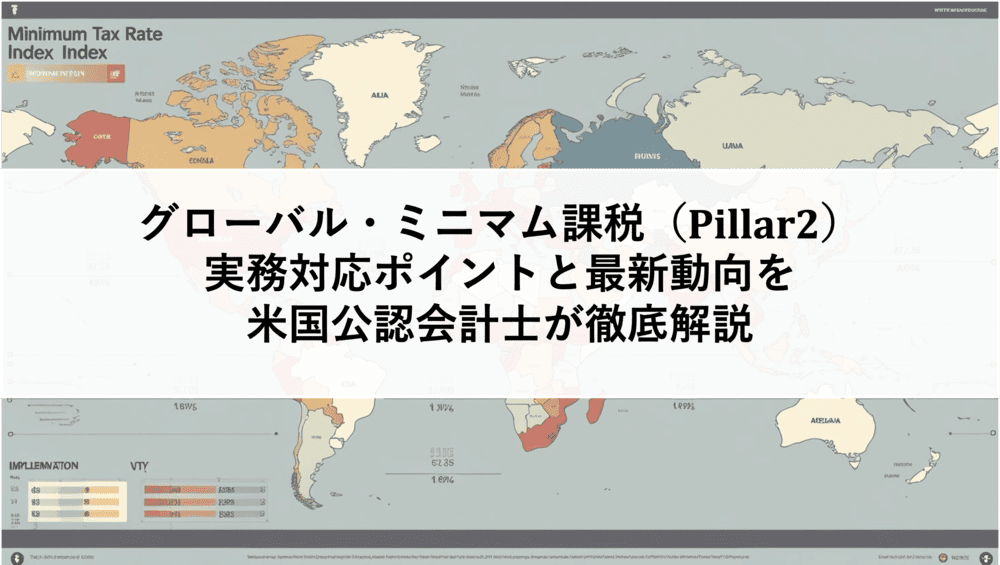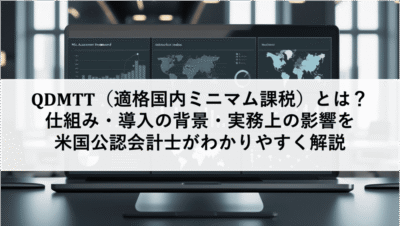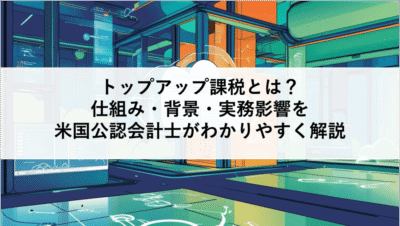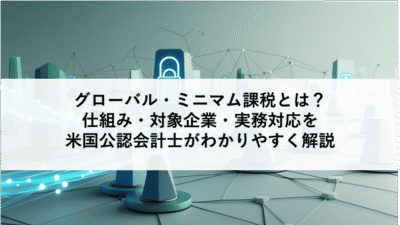2024年4月1日以後開始する事業年度から、日本においても「グローバルミニマム課税」がいよいよ適用開始となりました。年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,200億円程度)以上の多国籍企業グループを対象とするこの新しい国際課税ルールは、これまで多くの企業にとってまだまだ先の話だったかもしれません。しかし、今やその対応は喫緊の経営課題となっています。「具体的に何から手をつければいいのか」「自社への影響がどの程度あるのか見当もつかない」「申告準備のために、どのような情報が必要になるのか」こうした悩みを抱える企業の経理・税務ご担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、国際税務を専門とする実務家の視点から、グローバル・ミニマム課税の概要から企業が直面する具体的な実務上の論点、そして今から準備すべきことまで、分かりやすく解説していきます。
そもそもグローバル・ミニマム課税とは何か
グローバルミニマム課税は、経済のデジタル化に伴う国際的な租税回避行為に対処するため、OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において約140の国・地域が合意した国際課税ルールの大きな変革(BEPS2.0)の「第2の柱(Pillar Two)」に位置づけられています。その目的は、軽課税国に利益を移転することによる法人税の引き下げ競争(いわゆる「底辺への競争」)に終止符を打ち、多国籍企業グループに対してその活動を行うすべての国・地域で最低15%の税負担を求めることにあります。
具体的には、子会社等が所在する国の実効税率が15%に満たない場合に、その差額分(トップアップ課税)を最終親会社等の所在国で合算して課税する「所得合算ルール」が中核となります。この制度の導入により、これまでタックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用が免除されていた事業実体のある海外子会社であっても、その国の実効税率が15%未満であれば日本で追加の税負担が発生する可能性が出てきました。
日本における法制化の状況と今後のスケジュール
日本では、令和5年度(2023年度)税制改正において「所得合算ルール(IIR)」が「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」として法制化され、2024年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されています。さらには、令和7年度(2025年度)税制改正大綱においてIIRを補完するルールである「軽課税所得ルール(UTPR: Undertaxed Profits Rule)」および「国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)」の導入が盛り込まれました。これにより、日本のグローバル・ミニマム課税制度は、OECDのモデルルールに準拠した形で完全に整備されることになります。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
【本題】実務担当者が直面する3つの重要論点と対応策
この新しい税制に対応するため、実務担当者は具体的にどのような課題に直面し、どう備えるべきでしょうか。ここでは、特に重要となる3つの論点について解説します。
論点1:GloBE所得・調整後対象租税額の複雑な計算
グローバル・ミニマム課税(GloBEルール)対応で最も大きな実務負担となるのが、追加課税額(トップアップ課税額)の算定です。これは連結財務諸表の数値を出発点に、多数の加減算調整を実施した上で「GloBE所得(損失)」および「調整後対象租税額」を国・地域別に算出する必要があり、非常に複雑です。
たとえばGloBE所得の計算では、会計上の税引前利益を始点として、配当控除、資本損益の除外、罰金や寄附金の非加算など、モデルルールで定められた数十項目の調整が行われます。また、調整後対象租税額の計算でも、繰延税金資産・負債の扱いや、不確実な税務ポジションに関する会計上の引当金の調整など、高度な専門的判断が求められます。
対応策:早期のデータ収集と計算ロジックの理解
計算ロジックを正確に理解するためには、OECDが公表しているモデルルールやコメンタリー、各種ガイダンスを読み解く必要があります。これらは専門性が高く難解ですが、計算の根幹をなすため、時間をかけてでも理解を深めるか専門家の支援を仰ぐことが不可欠です。
論点2:グループ内での情報共有体制の構築
グローバルミニマム課税の計算と申告はグループ全体で一体となって行う必要があります。特に最終親会社が日本にある場合、世界中の子会社から必要な財務・税務データを収集しなくてはなりません。しかし、海外子会社によっては、これまで親会社へのレポーティングパッケージに含まれていなかった詳細なデータ(例:繰延税金の詳細な内訳など)の提出が必要となる場合があります。また、各国の法制度や会計基準の違い、言語の壁などが情報収集の障壁となることも想定され、必要十分なデータ収集がスムーズに行うことは容易ではない企業様が多い印象です。
対応策:グループ共通のレポーティングパッケージの策定と周知
「何のために、どのような情報が、いつまでに必要なのか」を明確に、かつ丁寧に伝えることで、子会社側の協力も得やすくなります。場合によっては、親会社の担当者が現地に赴いて説明会を実施するなど、積極的なコミュニケーションが功を奏することもあるでしょう。
論点3:申告・納税のプロセスとセーフハーバー活用の検討
グローバル・ミニマム課税の申告は、「GloBE情報申告書(GloBE Information Return)」を用いて行います。この申告書は、対象会計年度終了の翌日から15か月以内(初年度は18か月以内)に原則として最終親会社がその所在国の税務当局へ提出することとされています。なお、この申告書の作成には膨大な情報量が必要となり、申告期限から逆算しながら計画的に準備を進める必要があります。
対応策:セーフハーバーの適用検討と計画的な準備
上記の申告義務に関して、セーフハーバーには複数の選択肢がありますが、2026年12月31日以前に開始し20286月30日以前に終了する対象会計年度については、国別報告事項(CbCR)の数値を用いて簡易な判定を行い、申告書作成の工数を大幅に削減することも可能です。自社グループがこうしたセーフハーバールールを適用できるのか、専門家とともに早期に検討することをお勧めします。ただし、適用できたとしても、GloBE情報申告書の提出義務が完全に免除されるわけではない点には注意が必要です。
企業が今すぐ取り組むべきこと
ここまで解説してきた3つの論点を踏まえ、対象となる可能性のある企業の担当者の皆様は以下のステップで準備を進めていくことが賢明です。
- 影響度の評価・試算: まずは、自社グループがグローバル・ミニマム課税の対象となるか、対象となる場合にどの国・地域で、どの程度の追加課税が発生する可能性があるのか、簡易的な試算を行います。これにより、優先的に対応すべき課題が明確になります。網羅的に分析を実施するため、必要に応じて専門家のスポットでの利用を検討されてみても良いかもしれません。
- データ収集・管理体制の整備:影響度の試算結果を踏まえ、精緻な計算に必要なデータ項目を洗い出し、グループ各社から収集するためのプロセスおよび仕組みを構築します。Excelベースでの管理から始め、特にグローバルに展開する大企業の場合には、将来的なITソリューションの導入も視野に入れても良いかもしれません。
- 専門家の活用:グローバルミニマム課税は、税務だけでなく会計、法務、ITなど多岐にわたる知見が求められる新しい領域です。自社内だけで対応することが困難な場合は、ためらわずに外部の税理士やコンサルタントといった専門家の知見を活用することを検討してください。
まとめ
グローバルミニマム課税への対応は、単なる税務コンプライアンス上の課題にとどまりません。グループ全体の税務ガバナンスや経営戦略、さらには事業展開そのものにも影響を与えうる重要な経営課題です。適用初年度の申告期限が迫る中、もはや「様子見」は許されません。本記事で解説した実務上の論点を参考に、まずは自社グループの影響度を把握することから、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
国際税務は非常に複雑で、個別の事情によって対応が大きく異なります。もし、この記事を読んでもなお具体的な進め方に不安がある、自社のケースではどう考えればよいか分からないといったお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
当サイト「国際税務総合研究所」では、皆様の国際税務に関する疑問を解決するための一助として、無料・匿名で質問できる「みんなの国際税務Q&A」を設けております。一般的な見地からにはなりますが、専門家として皆様の疑問にお答えし、その内容をサイト上で共有することで、同じ悩みを持つ多くの方々の問題解決にも繋げていきたいと考えております。個別の税理士に相談する前の、第一歩としてご活用いただければ幸いです。