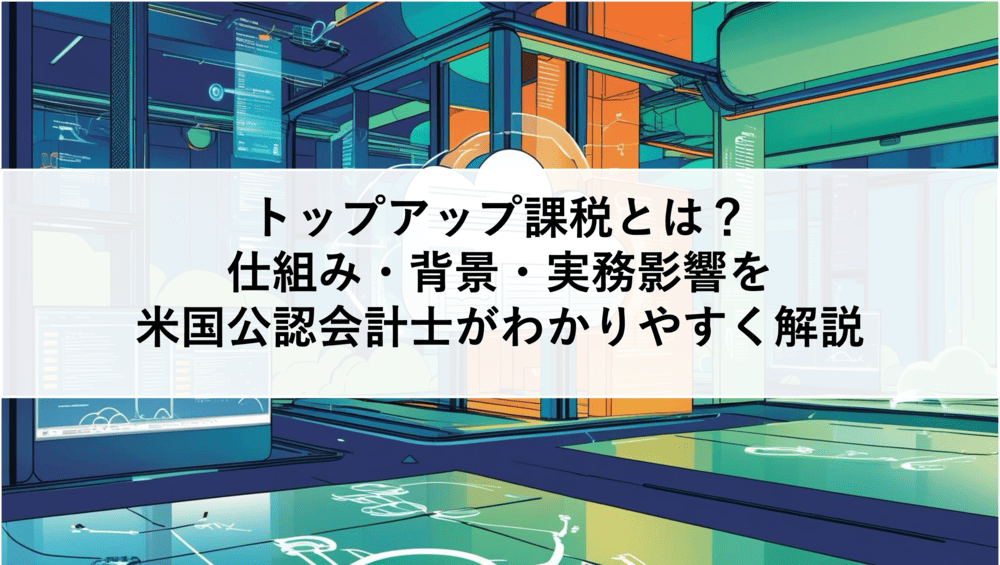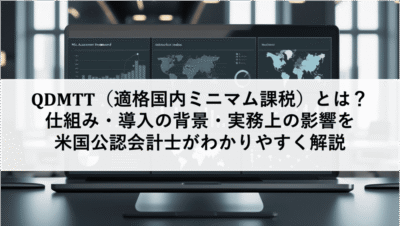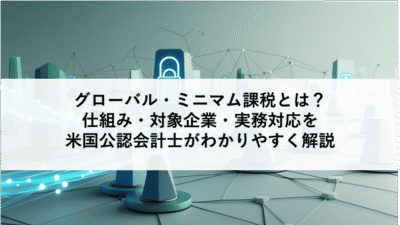トップアップ課税の仕組みから背景、実務への影響まで、実務担当者が押さえるべきポイントを米国BIG4出身の会計士が丁寧に解説します。実務経験に基づいた視点で、トップアップ課税の注意点をわかりやすくお伝えします。
トップアップ課税とは?
トップアップ課税(Top-up Tax)とは、ある国や地域での法人税負担が一定の最低水準を下回っている場合に、その差額分を他国が追加的に課税する仕組みを指します。
この制度は、OECDが主導するグローバル・ミニマム課税(GloBEルール)の中心的な考え方のひとつであり、2023年以降、世界各国で導入が進んでいます。
簡単に言えば、「税金をほとんど払っていない国があるなら、別の国でその差額を補って課税する」という考え方です。これにより、多国籍企業による極端な“節税”を抑止し、課税の公平性を確保する狙いがあります。
具体的な仕組み:どこで、どのように課税されるのか
トップアップ課税は、以下のようなステップで機能します。
-
多国籍企業の各国での「調整後実効税率」を算定
-
それが15%を下回っている国の所得を特定
-
その差額分(例:調整後実効税率が10%であれば、差額分は5%)を、親会社所在国などが追加課税
例えば、シンガポールでの調整後実効税率が10%であった場合、グループ全体の本国(たとえば日本)がGloBEルールを導入していれば、その5%の差額に対して「トップアップ課税」が日本の税務申告において発動します。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
トップアップ課税とQDMTTの関係
多くの国が、外国からのトップアップ課税を回避するために、自国内で差額を先に課税する制度である、QDMTT(適格国内ミニマム課税)を整備しています。
この制度を導入することで、自国で15%の実効税率が確保されることになり、他国による差額課税を受けることなく、課税権を維持できます。
つまり、トップアップ課税されるくらいなら、自国で先に課税しておこうという考え方です。
実務担当者にとっての留意点
トップアップ課税は制度としては新しい概念ですが、実務への影響はすでに顕在化しつつあります。以下の観点での対応が求められます。
-
調整後実効税率の計算ロジックの理解とシミュレーション対応
GloBEルールに従った独自の調整が必要となり、従来の税率概念とは異なる算定が求められます。 -
グループ内の税務データの整合性と可視化
各国での所得・税額・控除内容を正確に把握し、連結ベースでの整合性ある報告体制を構築する必要があります。 -
会計・税務システムのアップデート
トップアップ課税やQDMTT(適格国内ミニマム課税)に対応した計算機能・報告機能の整備が求められ、会計・税務プロセス全体への影響も無視できません。
おわりに
トップアップ課税は、単なる追加課税というよりも、「国際的な課税主権と課税の公平性」を再定義する新たな仕組みです。各国で制度設計が進む中、グループ全体としての税負担の可視化と統制が、今後ますます重要になります。制度が複雑であるがゆえに、まずは基本的な構造を正しく理解し、自社のグループ構成や税率水準を踏まえたシミュレーションを行うことが、実務対応の出発点となります。