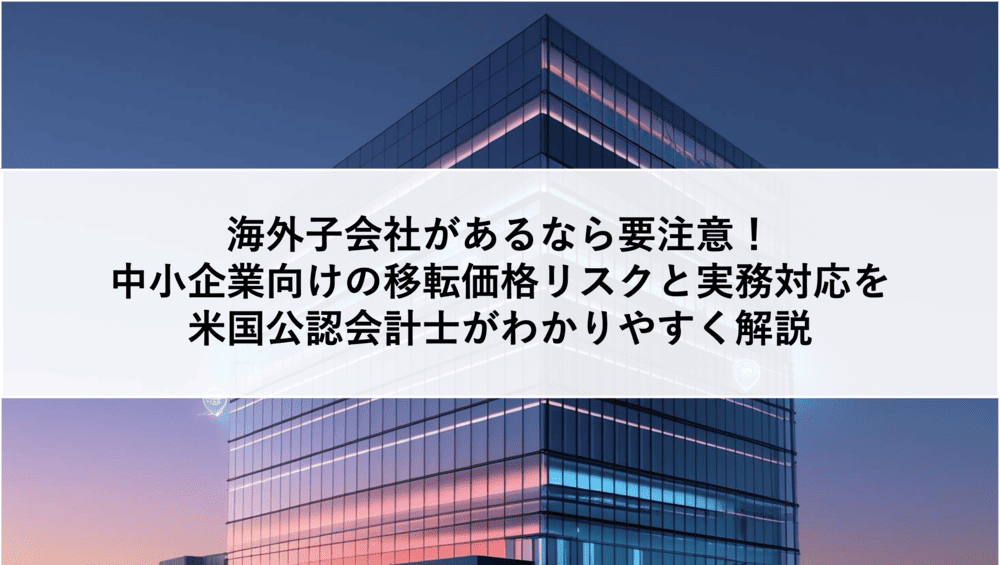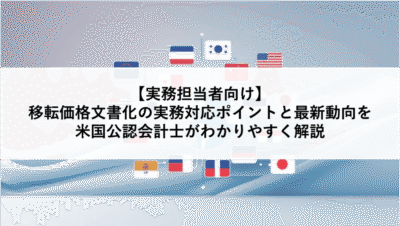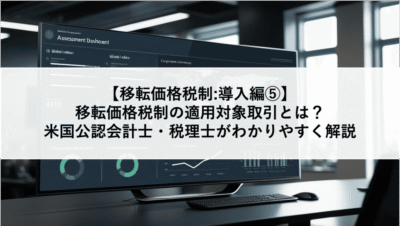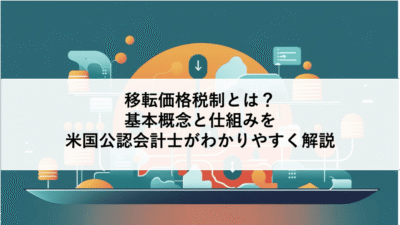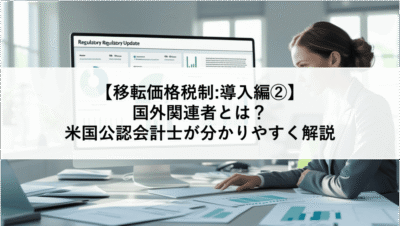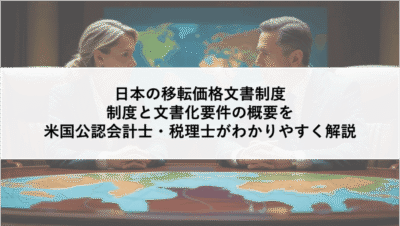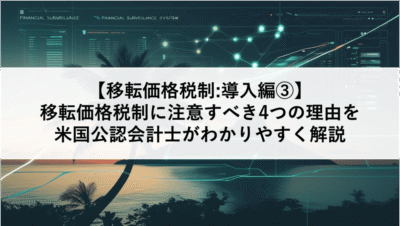「うちは中小企業だから、移転価格なんて大企業だけの話だろう。」海外に子会社や関連会社を持つ経営者の方々からこのようなお話を伺うことが少なくありません。しかし、それは極めて危険な誤解といえます。海外の関連会社と何らかの取引がある場合、企業の資本金や売上規模にかかわらず、原則として「移転価格税制」の適用対象となります。
この税制への理解が不足していると、ある日突然、税務調査で数千万円、場合によっては億単位の追徴課税を指摘される可能性があります。こうした予期せぬキャッシュアウトは企業の存続そのものを揺るがしかねない重大な経営リスクです。この記事では、国際税務を専門とする米国公認会計士の立場から、多くの中小企業経営者が見過ごしがちな移転価格税制の基本、具体的なリスク、そして今すぐ着手すべき対策について、専門的な内容をできる限り平易な言葉で、わかりやすく解説していきます。
そもそも移転価格税制とは何か?基本の仕組みを理解する
移転価格税制と聞くと、複雑で難解なイメージを持たれるかもしれません。しかし、その根底にある考え方は非常にシンプルです。まずは、この制度がなぜ存在するのか、その基本的な仕組みから理解を深めていきましょう。
なぜ「移転価格」が問題になるのか?所得の海外移転を防ぐ仕組み
移転価格(Transfer Price)とは、親会社と海外子会社のような、同一企業グループ内で行われる国際取引の価格を指します。これには製品や部品の売買だけでなく、技術指導の対価(ロイヤルティ)や経営サポートへの対価、資金の貸付利息など、グループ内で行われるあらゆる取引が含まれます。
では、なぜこの「グループ内の価格」が税務上、問題視されるのでしょうか。それは、グループ企業間では取引価格をある程度自由に設定できるため、それを利用して利益を意図的に操作し、税率の低い国へ所得を移転することが可能になるからです。例として、日本の親会社(法人税率30%)が原価1,000円の製品を製造し、税率の低いA国(法人税率10%)にある子会社に販売するケースを考えてみましょう。
- ケースA:子会社に1,000円で販売
- 日本の親会社の利益:0円(納税額0円)
- A国の子会社が2,000円で外部販売した場合の利益:1,000円(納税額100円)
- グループ全体の納税額:100円
- ケースB:子会社に1,800円で販売
- 日本の親会社の利益:800円(納税額240円)
- A国の子会社がケースAに同じく2,000円で外部販売した場合の利益:200円(納税額20円)
- グループ全体の納税額:260円
このように、親会社から子会社への販売価格(移転価格)を低く設定する(ケースA)だけで、グループ全体の税負担を意図的に軽くできてしまいます。こうした行為は、日本から見れば本来得られるはずだった税収が不当に失われることを意味します。移転価格税制は、このような取引価格の操作による所得の海外移転を防止し、各国がその国で生み出された経済的価値に見合った適正な課税を行うことを目的としています。
制度の根幹「独立企業間価格(Arm’s Length Price)」という考え方
移転価格税制の最も重要な概念が「独立企業間価格(Arm’s Length Price、略してALP)」です 。これは利害関係のない第三者同士(独立した企業間)で取引が行われるとした場合に、設定されるであろう価格を指します。
税務当局は、企業が実際に用いた取引価格がこの独立企業間価格から逸脱していると判断した場合、その取引が「独立企業間価格で行われたものとみなして」所得を再計算し、差額に対して課税を行います。先の例で言えば、仮に独立企業間価格が1,800円だと算定された場合、たとえ会社が1,000円で取引していたとしても、税務上は1,800円で販売したものとして800円の利益が日本で発生したと認定され、それに対する法人税が課されることになるのです。
この独立企業間価格という考え方は、日本独自のルールではありません。経済協力開発機構(OECD)が策定した「移転価格ガイドライン」に基づく国際的な標準ルールであり、主要な国々がこの原則に沿って国内法を整備しています。これにより、多国籍企業に対する課税の公平性と国際的な整合性が図られています。
移転価格税制の対象となる「国外関連者」の定義
移転価格税制が適用されるのは、「国外関連者」との取引です。では、どのような関係にある海外法人が「国外関連者」に該当するのでしょうか。これには、形式的な基準と実質的な基準の二つがあります。
まず、形式基準(形式的な支配関係)です。これは主に株式の保有割合によって判定されます。
- 親子関係:一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%以上を直接または間接に保有している関係。
- 兄弟関係:同一の者(法人または個人)が、二つの法人の発行済株式等の50%以上をそれぞれ直接または間接に保有している関係。
多くの企業は海外子会社を100%出資で設立するため、この親子関係に該当し、自動的に国外関連者となります。
次に、より注意が必要なのが実質基準(実質的な支配関係)です 。これは、株式保有率が50%未満であっても、一方の法人が他方の法人の事業方針を実質的に決定できる場合に適用されます 。具体的には、以下のような事実関係が考慮されます。
- 役員関係:役員の兼任などにより、事業方針を実質的に決定できる関係。
- 取引依存関係:取引の大部分を依存している関係。
- 資金依存関係:運転資金の大部分を融資や保証に依存している関係。
中小企業の場合、形式的な資本関係だけでなく人的なつながりや取引上の力関係によって実質的な支配関係が成立しているケースも少なくありません。したがって、「株式保有率が50%未満だから大丈夫」とは一概に言えないのです。
「中小企業には関係ない」が危険な誤解である3つの理由
制度の基本を理解した上で、なぜ「中小企業だから関係ない」という考えが危険なのか、その具体的な理由を3つの側面から掘り下げていきます。
理由1:税務当局の調査対象は中小企業へ拡大している
かつて移転価格調査といえば、追徴課税額が数十億、数百億円にのぼる大企業の大型案件が中心でした。しかし、近年その様相は大きく変化しています。国税庁の調査実績を見ると、調査件数自体は高水準を維持しつつも、1件あたりの申告漏れ所得金額は減少傾向にあります 。これは、調査対象が大企業だけでなく、中堅・中小企業へと「すそ野が広がっている」ことを明確に示しています。
この背景には、税務当局の体制強化があります。国税庁は国際課税を重点課題と位置づけ、専門調査官を増員してきました 。そして、その専門人材を国税局だけでなく、主要な税務署にも配置するようになっているようです。これにより、従来は国税局が管轄する大企業が主戦場だった移転価格調査を、税務署が管轄する中小企業に対しても実施できる体制が整ってきたのだと考えられます。
一部には「資本金1億円以下の中小法人は税務署の管轄だから、移転価格調査のリスクは低い」という見方もあります。しかし、これは過去の話になりつつあります。法律そのものには、企業の資本金や規模による適用除外規定は存在しません。あくまで執行上の優先順位の問題でしたが、その優先順位が変わりつつあるのが現状です。さらに、この変化を後押ししているのが、BEPSプロジェクト(税源浸食と利益移転プロジェクト)に代表される国際的な税務執行協力の強化です。このプロジェクトの成果として、各国税務当局は企業グループの情報を自動的に交換する仕組みを手に入れました。これにより、税務当局は以前とは比較にならないほど容易に、かつ正確に、企業の国際的な取引と利益配分の全体像を把握できるようになっています。
理由2:グローバル化で海外取引を行う中小企業が急増している
インターネットの普及やサプライチェーンのグローバル化により、今や中小企業にとっても海外展開は特別なことではなくなりました。より安価な労働力を求めて海外に製造拠点を設けたり、新たな市場を求めて販売子会社を設立したりするケースは年々増加しています。
こうした海外子会社との製品売買、部品供給、技術指導、資金援助といった活動は、すべて移転価格税制の対象となる「国外関連取引」に該当します 。つまり、企業のグローバル化が進めば進むほど、意図せずして移転価格税制のリスクに直面する企業が増えるのは必然なのです。
理由3:意図しない「利益移転」でも課税対象になり得る
中小企業の経営者からよく聞かれるのが、「税金逃れをしようなどとは全く考えていない。ただ、設立したばかりの海外子会社が軌道に乗るまで支援したかっただけだ」という声です。そのお気持ちは十分に理解できます。しかし残念ながら、移転価格税制の適用において、租税回避の「意図」の有無は問われません。この税制は、あくまで客観的な事実に基づいて適用されます。つまり、国外関連者との取引価格が独立企業間価格と異なり、その「結果」として日本の所得が減少していれば、課税の対象となり得るのです 。例えば、子会社を支援する目的で製品を原価同然で販売したり、無利息で運転資金を貸し付けたりする行為は、たとえ善意から出発したものであっても、税務上は「利益の移転」とみなされる可能性があります 。この「意図は問われない」という原則は、移転価格税制を理解する上で最も重要なポイントの一つです。
では、具体的にどのような取引が税務調査で問題となりやすいのでしょうか。ここでは、多くの中小企業で見られる典型的な4つのケースを取り上げ、そのリスクを解説します。
ケース1:棚卸資産取引(製品や部品の売買価格)
これは最も古典的かつ一般的な論点です。日本の親会社が製造した製品や部品を、海外の販売子会社や製造子会社に販売する取引がこれにあたります。
特に問題となりやすいのが、海外子会社の立ち上げ期に現地の市場開拓を支援する目的で、製品を通常よりも安い価格で供給するケースです。親会社としては当然の支援策と考えるかもしれませんが、税務当局から見れば、その「値引き分」は本来日本で計上されるべき利益が海外子会社に移転したものと判断されます。その結果、独立企業間価格との差額が日本の親会社の所得に加算され、追徴課税の対象となるリスクがあります。
ケース2:役務提供(経営指導・技術支援・業務代行の対価)
日本の親会社が海外子会社に対して行う様々なサポート業務も、移転価格税制の対象となります。例えば、経理や総務といった管理業務の代行、親会社の役員による経営指導、技術者による製造ノウハウの提供などが挙げられます。
多くの企業ではこうしたサポートを「親として当然の務め」と考え、無償で行ったり、契約書を取り交わしていなかったりするケースが散見されます。しかし、独立した第三者間であればこのような価値あるサービスが無償で提供されることはあり得ません。したがって、税務当局は、これらの役務提供には対価が発生すべきであると考えます。
ここで特に注意すべきは、この問題が「寄附金」として認定されるリスクです。無償の役務提供は経済的利益の無償供与とみなされ、海外子会社への「寄附金」として扱われることがあります 。税法上、国外の関連会社に対する寄附金は、そのほとんどが損金(経費)として認められません。さらに深刻なのは、寄附金認定された場合、後述する「国際二重課税」を解消するための「相互協議」という救済手続きの対象外となるのが一般的であるという点です。つまり、日本で課税された上に、相手国での税金は減額されず二重の税負担が確定してしまうという、最も避けたいシナリオに陥る可能性があるのです。軽い気持ちで行った子会社支援が、取り返しのつかない事態を招くこともあるのです。
ケース3:金融取引(親子間の貸付金利)
海外子会社の設立時や事業拡大時に、日本の親会社が運転資金や設備投資資金を貸し付ける(親子ローン)こともよくあります。この場合も、親会社は子会社から独立企業間価格に基づいた適正な利率の利息を受け取る必要があります。
無利息や市場金利よりも著しく低い金利での貸付は、税務調査で必ず指摘されるポイントです。税務当局は、仮に子会社が銀行などの第三者から同条件で借入を行った場合に適用されるであろう金利を算定し、親会社が受け取るべきであった利息との差額を「みなし収益」として所得に加算します。
ケース4:無形資産取引(ロイヤルティの授受)
親会社が長年かけて築き上げてきたブランド、特許、製造ノウハウといった「無形資産」も移転価格税制における重要な要素です。海外子会社が、親会社のブランド名を使って製品を販売したり、親会社が開発した特許技術を利用して製造を行ったりする場合、その使用対価として適正なロイヤルティを親会社に支払う必要があります。
特に、海外子会社の利益率が日本の親会社に比べて著しく高い場合、税務当局は「子会社の高収益は、親会社の無形資産を無償または安価で利用していることに起因するのではないか」と疑いの目を向けます 。ロイヤルティの受け取り漏れは、典型的な利益移転のパターンとして厳しくチェックされます。
移転価格調査の実態とペナルティの重さ
万が一、移転価格調査の対象となった場合、企業はどのような事態に直面するのでしょうか。そのプロセスと、指摘を受けた場合の金銭的・経営的なインパクトの大きさを正しく理解しておくことが、リスク管理の第一歩です。
通常の税務調査と何が違うのか?移転価格調査の流れと特徴
移転価格調査は、通常の法人税調査とはいくつかの点で大きく異なります。
- 調査の期間が長い:通常の税務調査が数日で終わるのに対し、移転価格調査は1年以上に及ぶことも珍しくありません。
- 調査の対象範囲が広い:財務・経理部門だけでなく、事業内容や価格決定プロセスを把握するため、営業、製造、開発といった現場の担当者への詳細なヒアリングが行われることがあります。
- 遡及期間が長い:課税の対象となる期間(除斥期間)が、原則として7年(2020年3月31日以前に法定申告期限が到来する事業年度は6年)と、通常の税務調査よりも長期間に及びます。7年分の取引が対象となれば、たとえ単価のズレは小さくとも、累積の課税額は巨額になり得ます。
税務調査は、当局からの調査開始通知を受けることから始まり、その後は膨大な資料の提出を求められます。さらに、担当官との間で書面による意見交換を何度も重ねながら論点を整理していく必要があり、企業にとっては時間的にも人的にも大きな負担となります。
こうした負担は、APAを事前に取得しておくことで大幅に軽減することが可能です。実際に、APAを申請せずに取引を進めた企業が、後の調査対応に追われ、その膨大な実務負担から「事前にAPAを取得しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。それほど、移転価格にかかる当局からの調査への対応は会社にとって相当な負担となり得ます。
追徴課税はいくら?加算税・延滞税を含めた金銭的インパクト
移転価格に問題ありと判断された場合、企業が支払うのは、本来納めるべきだった法人税(本税)だけではありません。それに加えて、ペナルティとしての「加算税」と、利息に相当する「延滞税」が課されます。
加算税には、申告額が過少であった場合に課される「過少申告加算税」(追加本税の10%〜15%)や、意図的な仮装・隠蔽があったと認定された場合に課される「重加算税」(同35%〜40%)などがあります。移転価格課税は更正額が大きくなる傾向があるため、これらのペナルティも相当な金額になります。
過去には、ファナック社が約22億円 、良品計画社が約70億円 といった大企業の事例が報道されていますが、中小企業にとっても他人事ではありません。たとえ追徴額が数千万円であっても、それは企業のキャッシュフローに深刻な打撃を与え、経営計画を根底から覆すインパクトを持ちます。
最大のリスク「国際二重課税」とその解決の難しさ
移転価格課税における最大のリスクは、「国際的な二重課税」です 。これは、一つの利益に対して二つの国がそれぞれ課税するという最悪の状態を指します。
例えば、日本の税務当局が親会社の所得を1億円増額する更正処分を行ったとします。これにより、親会社は日本で追加の納税を強いられます。しかしこのとき、海外子会社の所在国の税務当局が、自動的に子会社の所得を1億円減額して、納めすぎた税金を還付してくれるわけではありません。その結果、グループ全体で見ると、この1億円の利益に対して日本と相手国の両方で税金を支払うことになってしまうのです。
この二重課税状態を解消するための公式な手続きが、「相互協議(Mutual Agreement Procedure, MAP)」です 。これは、両国の税務当局同士が交渉を行い、課税権の配分を調整する制度です。しかし、この相互協議はそのプロセスが長期にわたることやコストが高額になることから、中小企業にとって決して簡単な救済策ではありません。したがって、相互協議は最後の手段と考えるべきであり、最善の策はそもそも税務調査で指摘を受けないように、事前にしっかりと備えておくことといえます。
中小企業が今から始めるべき移転価格対策の4ステップ
では、中小企業は具体的に何から手をつければよいのでしょうか。ここでは、専門家でなくとも今日から始められる移転価格対策の4つのステップをご紹介します。
ステップ1:自社のリスクを把握する(簡易リスクチェック)
まずは、自社が移転価格税制上どの程度のリスクを抱えているのかを客観的に把握することから始めましょう。以下のチェックリストを使って、簡易的な自己診断を行ってみてください。
- 海外子会社の利益率が、日本の親会社の利益率よりも恒常的に高いですか?
- 海外子会社が、設立以来ずっと赤字続きではありませんか?
- 海外子会社が、タックスヘイブンと呼ばれるような低税率国・地域(法人税率が15%未満等)に所在していますか?
- 日本の親会社から海外子会社へ、無償または著しく低い対価での役務提供(経営指導、技術支援など)を行っていませんか?
- 日本の親会社から海外子会社へ、無利息または著しく低い金利での資金貸付を行っていませんか?
- 海外子会社との取引に関して、価格設定の根拠を明確に説明できる文書(契約書、価格交渉の議事録など)が整備されていますか?
- 一つの海外子会社との年間の取引総額(売上・仕入の合計)が数億円規模になっていませんか?
これらの質問に一つでも「はい」がつく場合は移転価格上の潜在的なリスクを抱えている可能性があります。国税庁も同様の趣旨のチェックシートを公表しており、これらを参考に自社の状況を確認することができます。
ステップ2:取引価格の根拠を説明できる資料を準備する(移転価格文書化)
リスクを把握したら、次に行うべきは「国外関連者との取引価格が、独立企業間価格に基づいて決定されていること」を客観的に説明するための資料を準備することです。これを「移転価格文書化」と呼びます。BEPSプロジェクト以降、国際的には「マスターファイル」「国別報告書(CbCR)」「ローカルファイル」という3種類の文書の整備が求められています。このうち、中小企業にとって最も直接的に関係するのが「ローカルファイル」です。
日本の税法では、前事業年度における一の国外関連者との取引合計額が50億円以上、または無形資産取引の合計額が3億円以上の場合に、ローカルファイルの作成・保存が義務付けられています(同時文書化義務)。
またこの金額基準を見て、「うちは該当しないから大丈夫」と安心するのは早計です。これは、移転価格対応における最大の「罠」とも言えます。なぜなら、この基準はあくまで「確定申告期限までの文書作成義務」を定めたものに過ぎないからです。
たとえこの義務を負わない企業であっても、「国外関連取引を独立企業間価格で行う義務」そのものが免除されるわけではありません。税務調査の際には、文書化義務の有無にかかわらず、当局は「独立企業間価格の算定根拠を示す資料」の提出を求めることができます。もし、指定された期限内(通常45日〜60日)に合理的な資料を提出できなければ、税務当局は同業他社の利益率など、自らが収集した情報に基づいて所得を計算する「推定課税」を行うことが可能になります 。この場合、通常は納税者にとって不利な条件で課税される可能性が極めて高くなります。
したがって、文書化義務がない中小企業であっても、万一の調査に備えて、自社の取引価格の妥当性を立証できる最低限の分析と資料を準備しておくことが、極めて重要な防衛策となるのです。
ステップ3:独立企業間価格の算定方法の基本を学ぶ
では、取引価格の妥当性はどのように示せばよいのでしょうか。ここでは、独立企業間価格を算定するための代表的な方法の概要を知っておきましょう。専門的な計算を自ら行う必要はありませんが、どのような考え方で価格が検証されるのかを理解しておくことは有益です。
日本の税法およびOECDガイドラインでは、いくつかの算定方法が認められており、取引の内容に応じて最も適切な方法を選択することになります 。日本の移転価格税制において代表的なものは「基本三法」と呼ばれます。
- 独立価格比準法(CUP法):国外関連取引と全く同じような商品を、全く同じような条件で第三者と取引した実績があれば、その価格を独立企業間価格とする方法です。最も直接的で信頼性の高い方法ですが、完全に比較可能な取引を見つけることは実務上は極めて困難なため、実務で適用されるケースは稀です。
- 再販売価格基準法(RP法):海外の販売子会社などが、親会社から仕入れた商品を第三者に販売する取引に用いられます。その第三者への販売価格から販売子会社が獲得すべき通常の利幅(売上総利益)を差し引いて「親会社からの仕入価格(=独立企業間価格)」を逆算する方法です。
- 原価基準法(CP法):海外の製造子会社などが親会社のために製品を製造したりサービスを提供したりする取引に用いられます。製品の製造にかかったコスト(売上原価)に製造子会社が獲得すべき通常の利幅を上乗せして「親会社への販売価格(=独立企業間価格)」を算定する方法です。
この他にも、営業利益率を比較する「取引単位営業利益法(TNMM)」など、いくつかの方法が存在します。重要なのは、自社の取引がこれらのいずれかの方法に照らして、経済的に合理的であることを説明できるようにしておくことです。ただし、これらの算定方法は業種やビジネスモデルによって、適用されやすい手法にある程度の「定石」があります。そうした実務上の慣行や国税当局の見方については専門的な知識が必要になるため、実際の適用にあたっては移転価格の専門家に相談することを強くおすすめします。
ステップ4:専門家への相談を検討するタイミング
ここまで解説してきた通り、移転価格税制への対応は非常に専門的です。ステップ1のリスクチェックで懸念事項が見つかった場合や、国外関連者との取引が恒常的に行われ、その金額も無視できない規模になってきた場合は、独力での対応には限界があります。その際は、速やかに国際税務や移転価格を専門とする税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。
相談する最適なタイミングは、「税務調査の通知が来てから」ではありません。「まだ何も問題が起きていない、今のうち」です。事前の相談であれば、リスクの低い取引構造への見直しや説得力のある価格設定ロジックの構築など、打てる手は数多くあります。調査が始まってからでは、対応は防御一辺倒となり、選択肢は著しく狭まります。
また、取引規模が大きく、将来にわたる税務リスクを確実に回避したい場合には、「事前確認制度(APA)」という選択肢もあります。これは、独立企業間価格の算定方法などについて事前に税務当局と合意を得ておく制度です。APAを取得すれば、その合意内容に従っている限りは移転価格調査で指摘を受けることはありません。ただし、申請から合意までには長い時間と多額の費用を要するため、適用は慎重に検討する必要があります。
まとめ:移転価格税制への備えは、未来の経営を守る「転ばぬ先の杖」
本稿で解説してきたように、「中小企業だから移転価格は関係ない」という考えはもはや通用しない時代です。グローバルに事業を展開する以上、企業の規模に関わらず、すべての企業がこの国際課税のルールと向き合う必要があります。移転価格税制への対応は、決して単なるコストや手間ではありません。それは、予期せぬ税務リスクから会社を守り、持続的な海外展開を可能にするための重要な経営基盤の構築です。この記事が、貴社のグローバル経営における「転ばぬ先の杖」となれば幸いです。
この記事を読んで自社の状況に不安を感じた方、あるいは具体的な取引について専門家の一般的な見解を知りたいと思われた方は、第一歩として、当サイトが運営する無料・匿名の相談窓口「みんなの国際税務Q&A」を活用してみるのも一つの手段です。問題を先送りせず、今日から行動を起こすことが未来の経営を守ることにつながります。