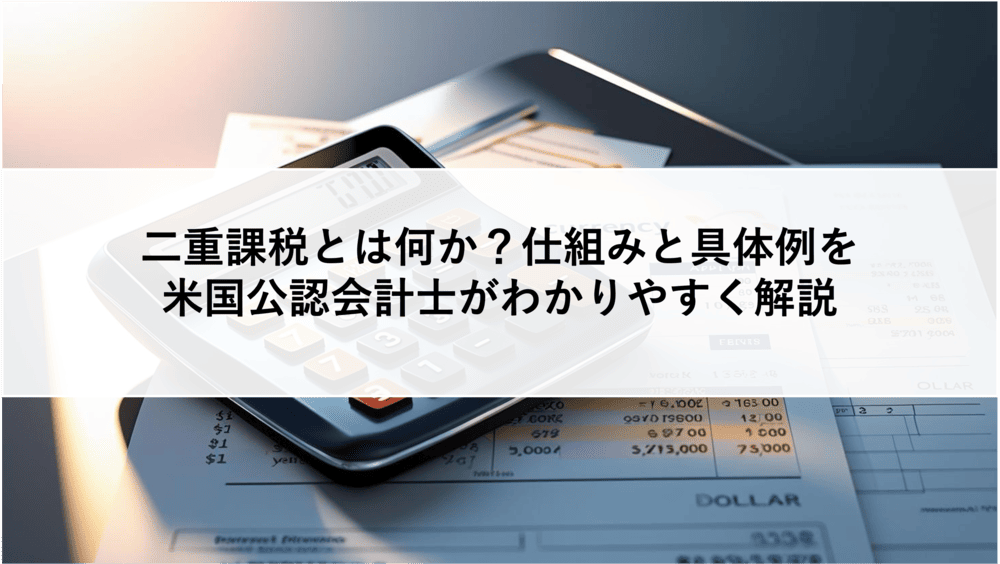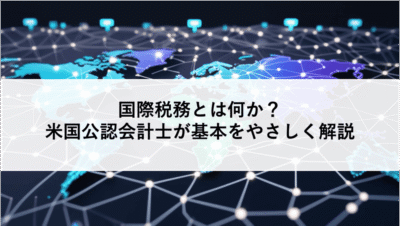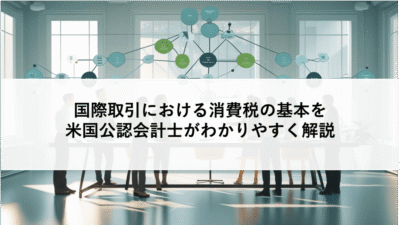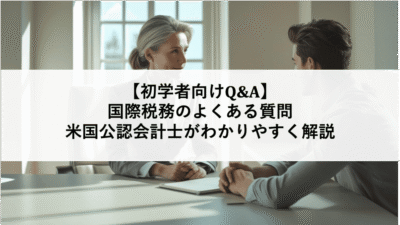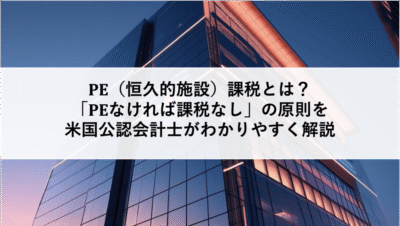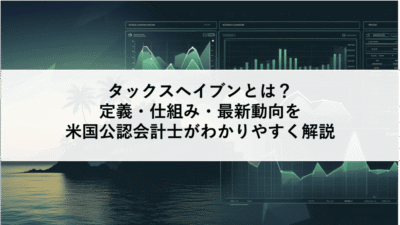二重課税とは同じ所得に対して複数の国で税金がかかる状態です。本記事では二重課税の意味や発生する理由、具体例、回避方法を初学者向けに米国公認会計士がわかりやすく解説します。
二重課税とは
二重課税を端的に言えば、同じ所得に対して異なる国がそれぞれ税金をかけることを言います。例えば、日本に住む人が海外で収入を得た場合、その収入に対してまず海外の税法に基づく課税が行われ、次に日本の税法に基づいて日本でも課税されることがあります。つまり、同じ所得に2回課税されるため「二重課税」と呼ばれます。なお「二重課税」という言葉は国内でも使われますが(例:法人税と株主の所得税)、本記事では主に国境を越えた場面での課税の重複(国際的な二重課税)を中心に解説します。
二重課税はなぜ起きるのか?
二重課税が発生する背景には、各国が独自の税法を持ち、課税権を主張する仕組みがあります。例えば日本では、居住者には全世界の所得に課税する(全世界所得課税)制度を採用しています。これは日本国内に住所がある個人や登記上の本店が日本にある法人は、国内外で稼いだすべての所得が日本の課税対象となることを意味します。一方、所得が発生した国(源泉地国)でもその国の法律で課税が行われる場合、同じ所得に対して両国で課税権が重なるため、結果的に二重課税が生じるのです。
たとえば、ある日本人が海外で働いて給与を得た場合、その給与には働いた国での所得税だけでなく、日本でも海外所得として日本の所得税が課される可能性があります。また、租税条約などの国家間での二重課税を防ぐ取り決めが締結されていない相手国同士では、お互いの税制を調整できず、結果として二重課税が起きやすくなります。このように、居住地国と所得の発生地国の両方に課税権が認められるケースにおいて二重課税が生じます。
二重課税の具体例
二重課税はさまざまなケースで発生しますが、典型的な例を見てみましょう。
-
居住国と源泉国による課税: たとえば、日本居住者が米国の企業で働いて給与を得た場合、米国で所得税が源泉徴収された後、その所得を日本の確定申告で申告する際にも日本の所得税が課される可能性があります。日本と米国はそれぞれ居住者に全世界所得課税を課しているため、同じ給与所得が両国で課税対象となり、二重課税が生じるのです。逆に米国に居住しながら日本の企業で働いて給与(日本国内源泉所得)を得た場合にも、日米双方で課税されるケースがあります。
-
投資収益における課税: 例えば、日本に住む個人が外国企業の株式を保有し、その配当を受け取ったケースを考えます。この配当については、発行国である外国で源泉徴収税が課されると同時に、日本においても海外所得として課税されることがあります。つまり、同じ配当金に対し、外国と日本の両方で税金がかかるため二重課税になります。株式の配当だけでなく、海外の銀行への預金に対して発生した利子収入などについても同様のことが起きえます。
これらの例のように、居住地国と所得発生地国の税法が重なる場面で二重課税が起きます。企業の場合でも、外国子会社で得た利益に対し現地での法人税が課され、その配当を親会社が受け取って日本で法人税がかかるといったケースで二重課税が生じます。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
二重課税を回避する方法
二重課税による過大な負担や不公平を避けるため、各国は外国で支払った税金を相互に調整する仕組みを設けています。主な方法は以下の通りです。
-
外国税額控除: ある所得に対して外国で税金を支払った場合、日本の確定申告でその外国税額を所得税から控除できる制度があります。たとえば、日本在住者が米国株の配当を受け、その配当に対して米国で源泉徴収税を納付した場合、日本の確定申告でその米国税額を所得税から差し引くことができます。このように、居住地国で課される税額から外国で払った税額を差し引くことで、実質的な税負担を軽減し二重課税を防止します。
-
租税条約の適用: 多くの国は二重課税を防ぐために租税条約(例:「〇〇国との間の所得に関する租税条約」)を締結しています。租税条約では、特定の所得について源泉地国での課税が免除または軽減される規定が盛り込まれています。例えば、条約で定められた免税所得(配当や利子など)については、源泉徴収税率がゼロに設定されたり、二国間で課税権の調整が行われたりします。租税条約を適用するには申告書への添付など追加手続きが必要ですが、これによって同じ所得に対する二重課税を排除または軽減することが可能です。
国際的な二重課税の排除においては、上に挙げた外国税額控除制度および租税条約の適切な活用が極めて重要です。これらの制度は各国の税制や納税者の居住地によって適用要件および手続きが大きく異なるため、個別の事案については税務の専門家による適切なアドバイスを求めることをおすすめします。
当記事でご紹介した内容は二重課税の基本的な考え方と例になります。ご自身の状況で疑問がある方は、当サイトの無料相談窓口「みんなの国際税務Q&A」で専門家に匿名相談することも可能です。初学者向けにもわかりやすく解説していますので、ぜひご利用ください。
まとめ
二重課税とは、同じ所得に対して複数の国から税金を課されてしまうことです。例えば、海外で得た収入が現地と日本の両方で課税されるといったケースで、これは各国がそれぞれの税法に基づいて課税するために起こりますが、このような問題を解決するため、外国税額控除や租税条約といった仕組みが用意されています。少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な考え方を理解しておけば無駄な税金を払わずに済むため、海外投資や国際的な取引を行う際は事前に調べておくことをお勧めします。分からないことがあれば、海外の会計士や国際税務に強い税理士などの専門家に相談してみましょう。国際税務は一見複雑ですが、正しい知識があれば適切に対処できますので、まずは基本から理解していきましょう。