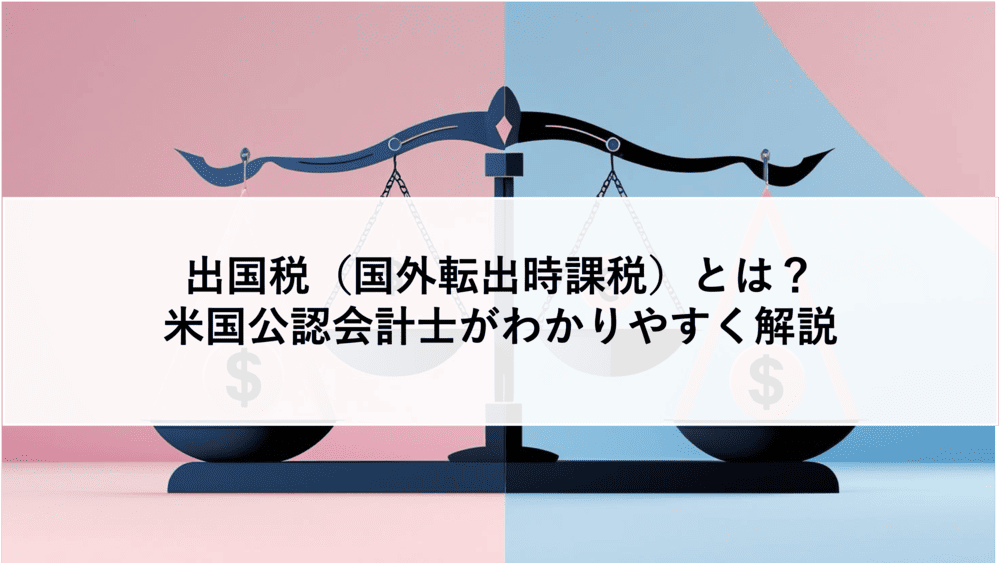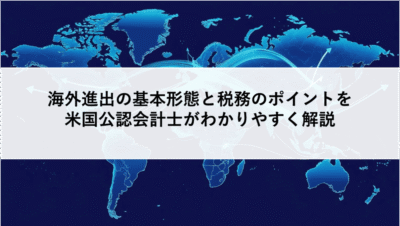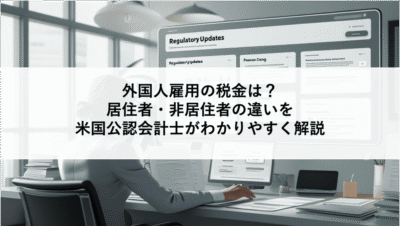海外移住を検討する際、日本に1億円以上の資産を保有する方が直面し得るのが「出国税(国外転出時課税)」です。本記事では、その基本的な仕組みや適用要件に加え、納税猶予制度など実務上重要となるポイントを国際税務の専門家がわかりやすく解説します。
はじめに:海外移住と「出国税」の基本
海外への移住は生活環境の大きな変化を伴うだけでなく、税務上の居住者区分にも根本的な影響を及ぼします。日本の税務においては「居住者」と「非居住者」の区分が課税関係を決定する上で非常に重要です。所得税法上の居住者判定は、単に海外に引っ越したという事実だけでなく、生活実態に基づいて総合的に判断されるます。そのため、意図せず日本の居住者とみなされ、予期せぬ税負担や申告義務が生じるケースが少なくありません。国際的な人の移動が増加する現代において、このような税務上の認識の差異がのちに大きな問題に発展するケースも多くなっています。
「出国税」とは何か?その基本的な意味と制度の目的
「出国税」は通称であり、正式名称は「国外転出時課税制度」といいます。この制度は、日本から国外へ転出する時点で1億円以上の対象資産を所有している場合、その資産を実際に売却していなくても、売却したと仮定した場合の含み益に対して所得税が課されるものです 。つまり、未実現の利益に対しても課税が行われる「みなし譲渡課税」の仕組みが採用されています 。
なぜ「出国税」が導入されたのか?国際的な背景と日本の位置づけ
国外転出時課税制度は、平成27年(2015年)7月1日に施行されました。その導入の背景には、国際的な租税回避を防止しようとする動きがあります。具体的には、日本に居住している間に多額の含み益を抱えた株式等を保有したまま、キャピタルゲインが非課税となる国(例えば、香港やスイスなど)へ移住し、そこで資産を売却することで「日本でも移住先の国でも課税を逃れる」という租税回避行為を防ぐ目的があります。この制度は、アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ、英国など、既に多くの主要国で導入されている国際的な潮流の一部です。これは、各国が自国の徴税権を維持するための措置として位置づけられており、国際的な税務ガバナンスの強化という側面を持っています。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
出国税の適用対象者と対象資産
国外転出時課税制度の対象となるのは、特定の条件を満たす日本の居住者です。自身の状況が該当するかどうかを正確に把握することが、適切な税務計画の第一歩となります。
どのような人が対象となるのか?
国外転出時課税の対象者は、以下の2つの条件をいずれも満たす日本の居住者です。
- 国外転出時に、「対象資産」の合計金額が1億円以上であること。
この「1億円以上」という基準は、主に高額な資産を保有する富裕層をターゲットとしていることを示唆しており、富裕層による租税回避の防止を通じて、税の公平性を維持するという制度の目的を反映しています。 - 「国外転出」をする日から遡って過去10年以内において、国内に5年を超えて住所または居所を有すること。
この「5年超の国内居住期間」の要件は、単なる短期滞在者ではなく、日本で一定期間経済活動を行い、その間に資産を形成したとみなされる個人を対象としていることを意味します。これにより、制度が不必要に広範囲に適用されることを防ぎ、真に課税権を維持すべき対象に絞っているというコンセプトがうかがえますね。補足として、外国籍の個人も対象となりますが、特定の在留資格(例:投資・経営、技術・人文知識・国際業務など)での滞在期間は、この5年超の国内居住期間の計算から除外される場合があります。
課税対象となる「対象資産」の種類
出国税の対象となる資産は、今のところは以下の金融資産に限定されています。
- 有価証券:株式(上場・非上場問わず)、国債、地方債、社債、投資信託の受益証券、株券不発行会社に係る非上場株式など。NISA口座内の有価証券も含まれます。
- 匿名組合契約の出資持分
- 未決済の信用取引、デリバティブ取引等
ここで特に注意すべき点は、中小企業のオーナーが保有する非上場株式も対象となるため、事業承継の一環として海外の親族に自社株を贈与する際にはこの制度が適用されてしまう点です。
出国税の対象外となる資産
一方で、以下の資産は国外転出時課税制度の対象外とされています。
- 現金
- 預金
- 貸付金
- 一部のストックオプション
- 仮想通貨(暗号資産)
補足として、現時点で仮想通貨は出国税の対象外とされていますが、国外転出後に売却した場合には居住国での課税ルールが直接適用される点に注意が必要です。各国で課税タイミングや取扱い(譲渡所得・雑所得扱いなど)が異なるため、移住前に二重課税リスクや課税繰延効果の有無を検討することが国際税務上は重要となります。
「国外転出」の定義と判断基準
「国外転出」とは、単に海外へ引っ越すことではなく、「国内に住所及び居所を有しないこととなること」と定義され、日本の税法上の「非居住者」となることを指します。ここでいう「住所」とは生活の本拠を指し、「居所」とは「一時的ではない相当期間において継続して居住する場所」を指します。これらの判断は一般に、納税者の生活実態に基づいて総合的に行われます。海外への転勤、留学、移住など、通常1年以上海外に滞在するケースが国外転出に該当し、数ヶ月程度の短期出張などは含まれません。この「国外転出」の定義が単なる物理的な移動ではなく、税法上の「居住者」ステータスの変更を伴う点に、この制度の法的厳密性が見られます。納税者は自身の生活実態が税務上どのように評価されるかを正確に理解する必要があり、この定義の理解が申告期限や納税猶予の適用条件に影響を与えるため、手続きの成否を分ける重要なポイントとなります。
出国税の計算方法と税率
国外転出時課税は、実際に資産を売却していなくても課税されるという特殊な性質を持つため、その計算方法と適用税率には注意が必要です。
「みなし譲渡」による課税の仕組み
国外転出時課税は、納税者が実際に資産を売却していなくても国外転出の時にその対象資産を時価で譲渡(売却)したものと「みなして」課税される制度です 。この「みなし譲渡」という法的フィクションにより、含み益がある資産に対して課税がなされます。一見すると何も問題がないように思えますが、ここで注意が必要なのは「実際に売却益が発生しているわけではない中で、つまり納税者に現金収入が実際にはない状態で税金を支払う必要が生じる」という点です。
課税所得の計算方法:納税管理人の有無による評価時期の違い
課税所得は、対象資産の「みなし譲渡価額」(国外転出時の時価)から「取得費等」を差し引いて計算されます。この資産の評価時期は、納税管理人の届出の有無によって異なります。
- 納税管理人を置く場合: 国外転出をする年の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告・納税が必要です。この場合の資産の評価時期は、国外転出日時点の時価となります。
- 納税管理人を置かない場合: 出国日までに確定申告書を提出し、納税が必要です。この場合の資産の評価時期は、国外転出予定日から起算して3ヶ月前の日の時価となります。
納税管理人の有無が評価時期と申告期限に大きな影響を与える点は、海外移住計画の早期段階での税務計画の重要性を示唆します。また、納税管理人を置かない場合の「3ヶ月前」という評価基準は市場変動リスクを納税者が負う可能性があり、計画的に資産管理を行う必要があります。
適用される税率:所得税と復興特別所得税
国外転出時課税に適用される税率は、原則として15.315%です。これは、所得税15%に復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)を加算したものです。
なお、(現時点では)住民税については原則として出国税の課税対象とならないとされています。しかし、住民票の転出届を提出しないと海外移住後も日本に住民登録が残ったままとなり、住民税が特別徴収され続けるリスクがありますので、住民票の転出届を忘れないようにしましょう。
申告・納税手続きの具体的な流れ
国外転出時課税制度の対象となった場合、適切な申告・納税手続きを期限内に行うことが不可欠です。特に、納税管理人の選任は手続きの進行に大きな影響を与えます。
確定申告の必要性と申告期限(納税管理人の有無別)
国外転出時課税の対象となった場合、確定申告が必須となります。申告期限は、納税管理人の届出の有無によって以下のように異なります。
- 納税管理人を置く場合: 国外転出をした年の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに確定申告書を提出します。
- 納税管理人を置かない場合: 国外転出日までに確定申告書を提出し、納税も完了させる必要があります。
なお、納税管理人を置かない場合の「出国日までの申告・納税」という期限はスケジュールとして非常にタイトとなりますので、余裕を持ったスケジュールで申告されることをおすすめします。
納税管理人の選任:その役割と手続きの重要性
納税管理人とは、納税者に代わって税務署との事務連絡(税務書類の受け取りなど)や納税を行ってくれる人や法人のことです。海外移住時、ないし海外に転出を行う場合に自身の納税管理人を指定することは、原則として義務とされています。また、後述する納税猶予制度を利用する上でも必須の手続きとなりますので、海外へ転出を行う際の重要な手続きの一つです。なお、納税管理人の届出書は国外転出時までに税務署に提出する必要があります。
納税方法:e-Tax、スマホアプリ納付、振替納税など
国税の納付手段には、納税者の利便性を考慮し、多様な方法が提供されています。
- 振替納税:事前に届け出た預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に自動で引き落としにより納付する方法。
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):e-Taxを利用して、事前に届け出た預貯金口座から即時または指定した期日に引き落としにより納付する方法。
- インターネットバンキング等:インターネットバンキング、モバイルバンキング、またはATMから納付する方法。
- クレジットカード納付:専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法(決済手数料がかかります)。
- スマホアプリ納付:専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、各種スマホ決済アプリを使用して納付する方法(納付税額が30万円以下の場合に利用可能)。
- 現金納付:金融機関および所轄の税務署の窓口や、コンビニエンスストアで納付する方法。
特に、e-Taxや国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」の活用は、確定申告書の作成から提出、納付までを効率的に行う上で非常に便利となっています。
以下に、納税管理人の有無による申告・納税手続きの違いをまとめます。
| 項目 | 納税管理人を置く場合 | 納税管理人を置かない場合 |
| 資産評価時期 | 国外転出日時点の時価 | 国外転出予定日から起算して3ヶ月前の日の時価 |
| 確定申告期限 | 国外転出をした年の確定申告期限(翌年3月15日)まで | 国外転出日までに |
| 納税期限 | 確定申告期限(翌年3月15日)まで | 国外転出日までに |
納税猶予制度:一時的な海外滞在者のための救済措置
国外転出時課税は、実際に資産を売却していない含み益に課税されるため、納税資金(現金)の確保が困難な場合があります。このような納税者の負担を軽減するために、「納税猶予制度」が設けられています 。以下、制度の概要と適用を受けるための手続きについて、具体的にみていきましょう。
納税猶予制度の概要と目的
納税猶予制度は、制度の厳しさ(みなし譲渡課税)と納税者の現実的な負担能力との間のギャップを埋めるための「セーフティネット」として機能しています。特に、海外駐在員など一時的な海外滞在後に5年以内に帰国する可能性が高い層にとっては課税自体が取り消される可能性があるため、極めて重要な制度です。
納税猶予を受けるための条件:納税管理人の届出と担保提供
納税猶予を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 国外転出時までに「納税管理人の届出書」を税務署に提出し、納税管理人を定めること。
- 確定申告書に納税猶予の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付すること。
- 納税猶予分の所得税額及び利子税額に相当する担保を提供すること。
基本的な納税猶予期間は5年間です 。しかし、一定の条件を満たし、「延長届出書」を提出することで、さらに5年間(合計10年間)の延長が可能とされています。
納税猶予期間中の継続手続きと利子税
納税猶予期間中は、毎年「継続適用届出書」を税務署に提出する必要があります。この提出を怠ると、猶予が打ち切られ、納税義務が直ちに発生する可能性があるため注意が必要です。また、納税猶予期間中は猶予された所得税額に対して利子税(= 利子)が発生しますので、注意が必要です。
納税猶予期間中に対象資産の譲渡等を行なった際、国外転出先の国で外国所得税が課された場合には「外国税額控除」の適用を受けることで、日本と海外での二重課税を防ぐことができます。外国税額控除は、国際税務における基本的な原則である「二重課税の排除」を目的とした重要な仕組みです。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
まとめ
「出国税(国外転出時課税)」は、その適用要件や対象資産、申告・納税手続き、納税猶予など丁寧な理解が必要とされる課税制度です。特に、実際に資産を売却していなくても課税される「みなし譲渡」の特性や、納税管理人の有無による手続きの違いなど、専門知識なしでは正確な理解と適切な対応が難しい点が多々あります。
海外移住や国際的な資産移転を検討している方で金融資産が1億円以上あるような場合では、出国税関連で思わぬ納税や事務手続きが必要になる可能性がありますので、はやめに国際税務に精通した税理士に相談し、自身の状況に応じた最適な税務プランニングを行なっていくことをお勧めします。
国際税務総合研究所では、このような国際税務に関する皆様の疑問にお答えするため、無料・匿名で相談できる窓口「みんなの国際税務Q&A」を設けております。個別の税理士に相談する前の第一歩として、またセカンドオピニオンとしても、ぜひご活用ください。