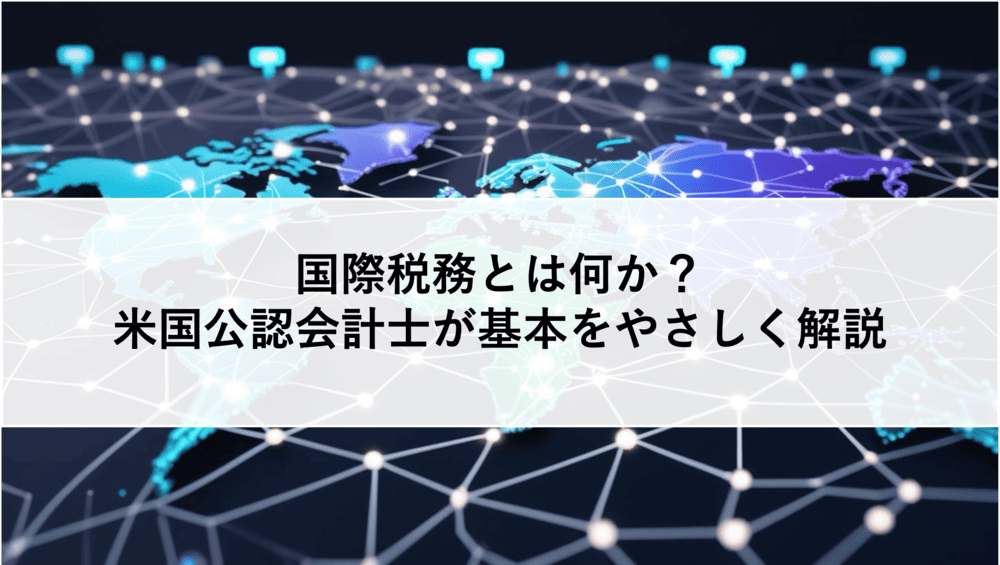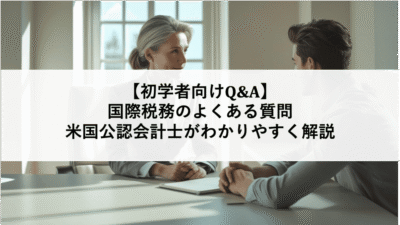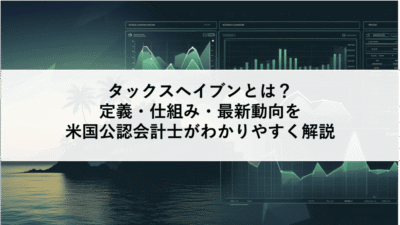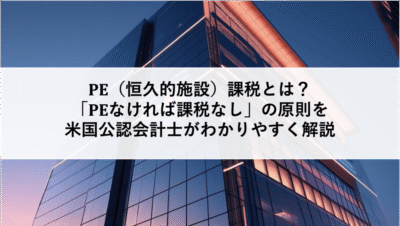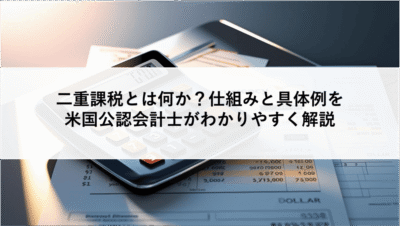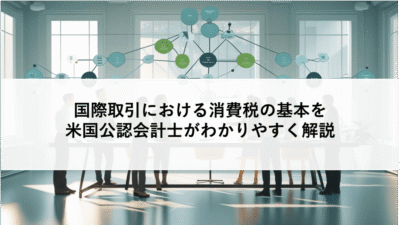国際税務とは、国境を越えた取引に関する税金のルールや問題全般を指します。本記事では、国際税務の定義からその仕組みや主要な論点まで、米国公認会計士がわかりやすく解説します。複数国間の取引で起こりうる「二重課税」の問題や二重課税を防ぐ国際ルールである「租税条約」の役割、海外子会社管理に頻出論点である「移転価格税制」や「タックスヘイブン対策税制」など、国際税務における基本的かつ重要な概念について、順番に見ていきましょう。
国際税務の定義と重要性
国際税務という言葉は法律上の厳密な定義があるわけではありませんが、簡単にいえば「2か国以上が関わる取引で発生する税務上の問題」全般を指します。例えば、日本に本社があり海外に支店がある企業や、海外向けにサービスを提供して収入を得るケースでは、日本と海外の双方で税金が発生する可能性があります。このように、国際税務では日本の税制だけでなく取引先国など外国の税制についても考慮する必要があります。
今日、企業の海外進出や個人のグローバルな活動が進む中で、国際税務の重要性はますます高まっています。異なる国の税法が絡むことで、同じ所得に複数の国が課税するリスク(これを国際税務の文脈では「二重課税」リスクと呼びます。)があり、適切に対処しないと過重な税負担や税務上のトラブルにつながります。そこで各国は、租税条約の締結や国内法の整備によって国際課税ルールを調整し、企業や個人が安心して国際ビジネスを行える環境づくりを進めています。
国際税務が扱う主な論点
国際税務の対象となる論点は多岐にわたりますが、実務的な観点でメインとなるトピックを挙げると次のようになります:
- 居住者・非居住者の判定(課税範囲の違いと課税方法)
-
二重課税の回避策(外国税額控除制度など)
-
租税条約による調整(課税権の配分や税率の上限設定、恒久的施設(PE)の規定など)
- 移転価格税制(多国籍企業間取引の適正な価格設定ルール)
-
CFC税制(タックスヘイブン対策税制)(海外子会社の所得合算課税による租税回避防止策)
以下、これらのポイントを順にやさしく解説していきます。
居住者と非居住者で異なる課税範囲
まず国際税務の基本として理解しておきたいのが、居住者と非居住者の区別です。税法上の居住者か非居住者かによって、課税される所得の範囲(課税範囲)が大きく異なります。
-
居住者の場合:所属国の税法では通常、その居住者が世界中で得たすべての所得(全世界所得)が課税対象になります。これを「全世界所得課税」といい、所得を受け取る人や企業が自国に「居住」していることを理由に、その所得の発生場所を問わず課税する方式です。例えば日本では、日本に住所がある個人や本店がある法人は居住者とみなされ、海外で得た所得も日本の課税対象(ただし後述の外国税額控除などで二重課税の調整が可能)となります。
-
非居住者の場合:その国に居住実体がない人や企業については、通常、当該国内で得た所得(国内源泉所得)のみに課税します。これを「源泉地国課税」といい、所得が国内で生じたという地理的なつながりを根拠に課税する方式です。例えばアメリカに居住する日本国籍を持つ日本人を例にとると、1年以上アメリカに居住して日本非居住者と認定された人については、日本国内で発生した所得に限って課税され、それ以外のアメリカおよび海外で発生した所得は日本では課税されません。
このように、ある所得が発生した際に「居住地国」(所得受領者の居住国)か「源泉地国」(所得の発生源の国)かによって課税範囲が変わるため、国際取引ではどの国の居住者とみなされるかが重要なポイントになります。一つの所得に対し複数国が課税権を主張すると国際的な二重課税が発生し得ます。次章では、この二重課税の仕組みとその解消方法について見てみましょう。
二重課税と外国税額控除による救済
二重課税とは何か
二重課税とは、同一の所得に対して複数の国が課税を行う状況を指します。例えば、日本にもアメリカにも収入源がある企業や個人の場合、同じ所得について日本でも米国でも課税対象となることがあります。実際、現代のグローバル経済では多くの企業や個人が複数国で収益を得る機会が増えており、その結果として異なる国で同じ所得に課税される二重課税の問題が生じやすくなっています。
二重課税が起きる典型例は、居住地国と源泉地国の双方がその所得を自国の課税対象に含める場合です。たとえば日本の居住者が米国で所得を得た場合、米国では源泉地国としてその所得に課税し、同時に日本も居住者の全世界所得としてその所得に課税することになります。同様に米国の居住者が日本で所得を得た場合も、日米双方で課税される可能性があります。
このように二重課税が生じると、納税者にとって二重の税負担となり、国際ビジネスの障害や不公平感につながります。そこで、各国は二重課税を避けるための救済措置を設けています。
二重課税を避ける仕組み:外国税額控除と国外所得免除
外国税額控除(Foreign Tax Credit)制度は、居住地国で課税する際に他国で既に課された税額を控除(差し引き)できるようにする仕組みです。先ほどの例で、日本の居住者が米国で所得を得て米国に税金を支払った場合、日本はその所得に対する自国の所得税を計算する際に、米国で支払った税額の全部または一部を自国の税額から差し引き(=日本で支払い税金を減額)します。これにより、同じ所得について最終的な税負担が米国・日本の合計で二重にならないよう調整されます。
一方、国外所得免除(Exemption)方式は、特定の海外所得について居住地国で非課税(免税)とすることで二重課税を排除する方法です。例えば企業の海外子会社から受け取る配当について、一定要件の下で居住地国が課税しない制度などが該当します。国によっては全世界所得課税を基本としつつ、特定の海外所得は非課税とする仕組みを採用している場合があります。
日本を含む多くの国では、基本的に外国税額控除方式をとりつつ、一部に国外所得免除を組み合わせた制度設計がなされています。いずれにせよ、外国税額控除や国外所得免除によって「同じ所得に対して最終的に二重の税金を払わなくて済む」ように調整することが各国の共通の目標となっています。実際、日本と米国をはじめ主要国同士では互いに外国税額控除制度を設けて、居住者に対する二重課税の回避を図っています。
後述する租税条約も、こうした二重課税の解消に大きな役割を果たします。次の章では、国際税務に欠かせない租税条約について基本を解説します。
租税条約の役割
租税条約(Tax Treaty)とは、二国間または多国間で結ぶ税務に関する国家間の協定で、主に二重課税の防止や納税者による租税回避の防止を目的としています。租税条約を締結することで、条約当事国同士で課税権を調整し、国際的な二重課税の除去と租税回避への対処を図ります。日本も多数の国と租税条約を結んでおり、これにより海外との安定した投資・経済交流を促進しています。
租税条約の主な内容
租税条約には典型的に次のような取り決めが含まれます:
-
課税権の配分:どの所得についてどちらの国が課税できるかを定めます。例えば「事業所得」については、ある企業が相手国に恒久的施設(PE: Permanent Establishment)を持たない限りは相手国では課税しない(=事業利益は原則として居住地国のみ課税)と規定されます。これにより、企業が従業員の短期派遣や小規模な活動を他国で行っても、相手国に恒久的施設さえなければその利益は本国のみで課税されるため、予期せぬ課税を避けることができるように設計されています。
-
投資所得等の源泉地国課税の制限:利子・配当・ロイヤルティ等の受動的所得について、源泉地国での課税に上限税率(減税または免税)を設けています。例えば日本とある国の租税条約で「配当の源泉地国課税は10%を超えない」と定められていれば、日本企業がその国で受け取る配当に対する現地源泉徴収税は最大10%に制限され、それを超える課税は条約違反となります。場合によっては「一定要件下で利子やロイヤルティは源泉地国で非課税」とする条約もあります。これら条約規定により、源泉徴収税率が軽減される(またはゼロになる)ため、投資収益に対する二重課税が軽減・解消されます。
-
居住地国での二重課税の排除方法:租税条約では、居住地国側で二重課税を除去するための方法(先述の外国税額控除方式または国外所得免除方式)について明記することが多いです。条約締結国同士でこの取り決めをすることで、相互に自国の居住者に対し二重課税救済を確実に提供することを約束します。
-
相互協議手続き:条約の解釈適用をめぐって納税者が二重課税など不当な課税を受けている場合、関係国の税務当局同士が相互協議(Mutual Agreement Procedure)を行い解決を図る枠組みも盛り込まれています。これにより、個別事案で条約通りに課税が行われていない場合でも、当局間の協議によって二重課税の救済や問題解決が期待できます。一方で、二国間の相互協議手続きが短期間で完了するケースは一般的に少なく、納税者に有利な結果が得られた場合でも、手続き開始から数年が経過してしまうことは珍しくありません。そのため、相互協議の利用を前提とした取引計画や経営判断を行う際は、長期間を要することを十分に考慮する必要があります。
-
情報交換と租税回避防止:近年の租税条約には、税務情報の交換や協力条項も含まれます。例えば金融口座情報の自動的交換、相手国からの情報要請への対応、徴収共助(お互いの国の税金を代わりに徴収する協力)など、国際的な租税回避や脱税に共同で対処するための規定が設けられています。これらは企業の所得移転や個人資産の国外隠匿を防ぐ国際協調の一環です。
租税条約と国内法の関係
租税条約は国家間の取り決めであるため、締結国の国内法より優先して適用されるのが原則です。日本国憲法98条2項に「締結した国際法規は誠実に遵守する」とあるように、日本でも条約の規定が国内法と異なる場合、条約が優先します。したがって、租税条約の規定によって国内法上の税率や課税関係が修正されるケースがあります。例えば、日本の所得税法では非居住者の受け取る利子に20%の源泉徴収課税を課していますが、条約で相手国居住者の利子課税上限が10%と定められていれば、日本はその条約相手国の居住者に対し10%を超えて課税できないことになります。
このように租税条約の存在により、実際の課税関係は国内法単独の場合と変わってくる点に注意が必要です。条約適用を受けるためには所定の手続(相手国居住者であることの証明提出など)が必要ですが、適用されれば国内法より有利な税率や課税範囲の限定が享受できます。また日本では「租税条約実施特例法」という法律を定め、条約の定めを国内法に橋渡しする細かなルールも整備されています。いずれにせよ、租税条約は国際税務の基本インフラであり、海外取引を行う際には自国と相手国の租税条約の内容を確認することが最重要です。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
移転価格税制:グループ内取引の適正価格
グローバルに事業展開する多国籍企業にとって重要なのが移転価格税制です。これは、企業が海外の関連会社(親会社・子会社やグループ企業)との取引価格を不当に操作して利益を移転させないようにするための税制です。
通常、独立した第三者同士の取引であれば市場原理に従った適正な価格が成立します。しかし、親子会社のようなグループ内取引では当事者が同一グループで経営目的を共有しているため、取引価格を人為的に上下させ、親子会社間の利益配分を操作することも理論上可能です。例えば、法人税率の低い国にある子会社に製品を安価で売り、高税率国にある親会社で高値で買い戻す、といった取引をすれば、グループ全体として利益を低税率国に付け替えることができてしまいます。
こうした恣意的な所得移転を防ぎつつ各国で適正に課税するため、移転価格税制では「独立企業間価格(Arm’s Length Price)」で取引が行われたものとみなして所得計算を行うルールを設けています。具体的には、税務当局がグループ内取引を審査し、もし取引価格が独立第三者間の通常の価格とかけ離れている場合には、その取引は独立企業同士であれば成立したであろう適正価格で行われたものと仮定して各社の所得を再計算し、課税します。これにより、恣意的な価格操作による利益移転(所得の海外流出)を防止するわけです。
日本の移転価格税制は、OECD(経済協力開発機構)の「移転価格ガイドライン」に沿った手法を採用しており、独立企業間価格を算定する具体的方法(比較可能な取引との価格比較法、再販売価格基準法、原価基準法など)が細かく定められています。また文書化要件として、多国籍企業にはグループ全体の事業概要や国別報告書、ローカルファイル(国別の詳細な移転価格文書)の作成・提出が義務付けられ、税務当局による監視が強化されています。これらはOECD主導のBEPSプロジェクト(後述)によって各国で導入が進んだもので、国際税務における透明性向上と適正課税確保のための措置です。
初学者の方は詳細な算定方法まで理解する必要はありませんが、ポイントは「グループ企業間の取引は第三者同士の市場価格で行われたものと見なして税金を計算する」ということです。これによって、多国籍企業が税負担の低い国へ利益を移しすぎることを防ぎ、各国に公平な税収配分を確保する狙いがあります。
タックスヘイブン対策税制(CFC税制)
タックスヘイブン対策税制(日本の正式名称: 外国子会社合算税制)も国際税務の重要な制度です。これは、日本の法人等が税率の低い国・地域(いわゆるタックスヘイブン)に設立した子会社に利益を貯めこむことで日本での課税を回避する行為に対応するための仕組みです。
具体的には、日本の親会社が持つ外国子会社が以下の条件に当てはまる場合、その子会社の所得を日本の親会社の所得と合算して日本で課税します(より具体的な判定基準は「CFC税制(タックスヘイブン対策税制)とは?仕組みや要件を米国公認会計士がわかりやすく解説」をご確認ください):
-
子会社の所在地国の税負担率が著しく低い(一定の低税率以下)
-
子会社がペーパーカンパニー等、実質的な経済活動を伴っていない(事業実体がない)
-
上記を含め、法律で定める要件(経済活動基準など)を満たさない場合
簡単に言えば、「実体のない海外子会社の受動的な所得」については、たとえ現地ではほとんど課税されなくても、日本の親会社の所得とみなして日本で課税するという制度です。例えば「税率が極端に低い国にペーパーカンパニーを置き、日本のビジネスの利益をその会社に計上して日本での課税を逃れる」というスキームに対して、日本の税務当局は「それは実体のない所得移転だ」とみなし、その子会社の利益にも日本で課税するわけです。
ただし、このタックスヘイブン対策税制には適用除外もあります。低税率国の子会社でも、一定の実体基準(現地でちゃんと事業を行い管理運営されている等)を全て満たす場合や、子会社の所得が主に事業所得で受動的所得ではない場合には、合算課税の対象から除かれる仕組みになっています。これにより、本当に現地で経済活動を営んでいる海外子会社まで一律に課税強化するのではなく、租税回避目的のペーパーカンパニーをターゲットにした課税となるよう配慮されています。
タックスヘイブン対策税制は、日本だけでなく多くの国で導入されているCFC(Controlled Foreign Company)税制と呼ばれるものです。グローバル企業が租税回避のために利用しがちな低課税国への所得移転を各国が共同で防止する枠組みであり、国際税務の公平性を担保する重要な柱となっています。
BEPSと国際的な租税回避防止の潮流
最後に、近年の国際税務の大きな潮流としてBEPS(Base Erosion and Profit Shifting: 税源浸食と利益移転)プロジェクトについて触れておきます。BEPSとは、多国籍企業が各国の税制の抜け穴や不整合を意図的に利用して、「本来課税されるべき国から意図的に利益を移転し、税負担を不当に減らす」ことを指す概念です。OECDはG20と協力してこの問題に取り組み、2015年に15の行動計画(BEPS Action Plan)から成る最終報告書を取りまとめました。
BEPS行動計画には、先述した移転価格文書化の強化(国別報告書の導入など)や、租税条約の乱用防止条項の導入、有害な税制競争の排除、タックスプランニングの透明性向上など、多岐にわたる項目が含まれています。これらの勧告を受けて各国は国内法や条約を改正し、国際的租税回避への対策を強化しました。日本も2016年度税制改正で移転価格税制の文書化要件を導入するなど、BEPSプロジェクトの成果を反映しています。
さらに近年では、BEPSプロジェクトの延長としてデジタル経済への課税やグローバル最低法人税率の導入が議論・合意されました。OECD/G20インクルーシブ・フレームワークでは2021年10月、約130か国以上が連携してグローバル法人税の最低税率を15%にすることに合意しています。これは巨大多国籍企業がどの国に利益を移しても最低15%の税負担は免れないようにすることで、各国間の課税競争を抑制し、税源浸食を防ごうという新たな取り組みです。2024年以降、このグローバル・ミニマム課税(BEPS 2.0の「柱2」)が各国で実装段階に入っており、国際税務のルールはさらに大きく変化しようとしています。
このように国際税務の世界では、各国が協調して公正な課税と課税漏れ防止のための枠組みを作り上げつつあります。多国籍企業によるアグレッシブな節税策は年々難しくなり、逆に真面目に納税している企業や個人が不利を被らない環境整備が進んでいると言えるでしょう。
まとめ:国際税務の基本を理解する意義
国際税務の基本事項として、「居住者と非居住者の課税範囲の違い」「二重課税のメカニズムとその回避方法」「租税条約による課税調整」「企業の移転価格規制」「タックスヘイブン対策」などを概観しました。これらは国際取引や海外進出に関わる上で避けて通れない重要ポイントです。
初学者の方にとっては少し盛りだくさんに感じられたかもしれませんが、今回整理した重要トピックを踏まえ、国際取引に関わる際には自社(自分)がどの国でどんな税負担を負う可能性があるのかを事前に把握し、条約の適用や各種制度を活用して適正な納税・タックスプランニングを行うことが大切です。国際税務は専門性が高く複雑な分野ですが、基本を理解しておくことで不必要な税コストを避け、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
国際税務の基本を押さえつつ、適切な知識と専門家のサポートを得て、グローバルなビジネス展開を円滑に進めましょう。お読みいただきありがとうございました。