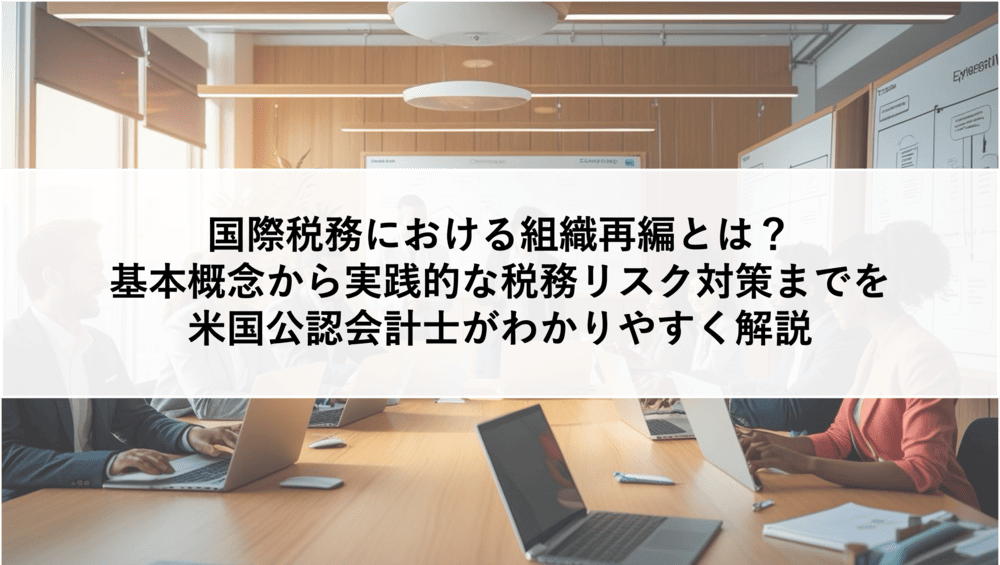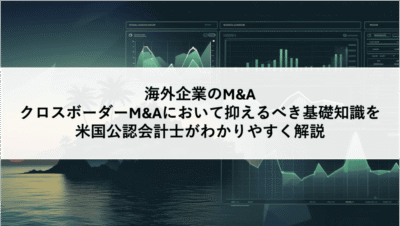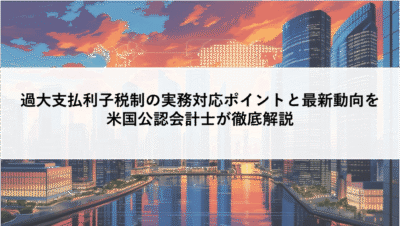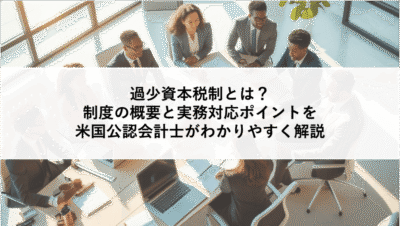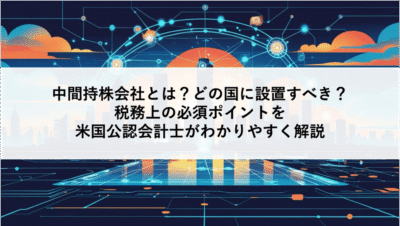国際税務における組織再編は、単なる会社の合併や分割を意味しません。本記事ではグローバルビジネスの根幹を揺るがしうる機能・リスクの国際的移転という視点から、組織再編の基本概念、そして最も重要な論点となる移転価格税制やタックスヘイブン対策税制との関係を、初学者の方にもわかりやすく解説していきます。
はじめに:組織再編における国際税務の重要性
グローバル経済が深化する現代において、企業の組織再編は単なる国内の法的手続きに留まるものではありません。サプライチェーンの最適化、クロスボーダーM&Aによる市場拡大、そして事業承継といった、企業の根幹を成す経営戦略を実現するための極めて重要な手段となっています。しかし、その戦略的な意思決定が国境を越えるとき、そこには必ず国際税務の問題が絡んできます。
海外子会社の設立、事業部門の海外移管、グループ内での役割分担の見直しといった一連の活動は、すべて国際税務の観点から「組織再編」と捉えられます。そして、それは各国の税務当局から極めて厳しい監視の対象にもなります。なぜなら、組織再編はグループ全体の利益がどの国で、どれだけ生み出されるかを根本から変える可能性があるからです。
本記事では、これから国際税務を学ばれる方や海外展開を始めたばかりで「何から手をつければよいか分からない」という企業の経営者・担当者様を対象に、基礎からわかりやすく解説します。まず「組織再編」の基本的な考え方を整理し、なぜそれが国際税務の最重要論点となるのかを解説します。その上で、組織再編と切っても切り離せない最重要ルールである「移転価格税制」をはじめ、「タックスヘイブン対策税制」などの主要な国際課税ルールとの関係性を具体的な事例を交えながら体系的にご説明します。
組織再編の基本概念
そもそも組織再編とは何か?
多くの方が「組織再編」と聞くと、会社の合併や分割といった言葉を思い浮かべるかもしれません。それは間違いではありませんが、国際税務の世界ではより本質的な視点が求められます。
会社法が定める組織再編行為
まず、基本となる国内法上の整理から始めましょう。日本の会社法では、組織再編行為として合併、会社分割、株式交換、株式移転などが定められています。これらは、複数の会社を一つに統合したり(合併)、会社の一事業を切り出して別会社化したり(会社分割)するもので、企業の法的な器(うつわ)そのものを変更する手続きです。これらは、国際税務を考える上での出発点となります。
国際税務における「組織再編」の真の意味:機能・資産・リスクの国境を越えた移転
国際税務の世界では、前述した法的な形式よりもその再編によって「事業の実態」がどのように国境を越えて動いたのか、という経済的実態が何よりも重視されます。この実態を捉えるためのキーワードが、「機能(Function)」「資産(Asset)」「リスク(Risk)」の3要素です。企業の利益は、これら3つの要素が組み合わさることで生み出されます。例えば、製品を開発する「機能」、その開発に必要な特許という「資産」、そして製品が売れないかもしれないという「リスク」を本社が担うことで、本社に利益が帰属します。
国際税務における組織再編とは、この利益の源泉である機能・資産・リスクが、ある国から別の国へ移転することを指します。例えば、これまで日本の親会社が担っていた研究開発機能をシンガポールの子会社に移管する、あるいは、アジア市場における在庫リスクを香港の統括会社が集中して負うように変更する、といった経営判断は、法的な合併や分割を伴わなくても、国際税務上は極めて重大な「組織再編」と見なされるのです。この視点の転換こそが、国際税務における組織再編を理解するための第一歩となります。
なぜ組織再編が国際税務の最重要論点となるのか
機能・資産・リスクの国際的な移転が、なぜこれほどまでに税務当局の厳しい監視対象となるのでしょうか。その根底には、各国の「課税権」をめぐる対立があります。
グローバルな利益配分と各国の課税権の衝突
利益の源泉を動かす「機能移転」という考え方
法人税は、原則として利益が稼得された国で課税されます。そして、その利益は利益を生み出す源泉となる経済活動、すなわち「機能」や「リスク」が存在する場所で発生したと考えるのが国際税務の大原則です。研究開発機能を持つ法人は研究開発から生まれる利益を、マーケティング機能を担う法人はブランド価値向上による利益を、そして販売リスクを負う法人は販売活動から得られる利益を、それぞれ受け取るべきだと考えられます。
国際的な組織再編は、この利益の源泉そのものを国境を越えて動かす行為に他なりません。日本の親会社が担っていた製造機能をタイの子会社に移管すれば、これまで日本で計上されていた製造利益は、今後はタイで計上されることになります。これは、日本から見れば自国の税収(税源)が失われ、タイから見れば新たな税収が生まれることを意味します。
このように、企業の組織再編は各国の税収に直接的な影響を及ぼすため、国と国との間の「課税権の奪い合い」という側面を持ちます。失われる側の税務当局は、その機能移転が経済的合理性に基づいたものか、不当な利益移転ではないかを徹底的に検証しようとします。これが、国際組織再編が常に税務上の重要論点となる根本的な理由です。
税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトとの関連性
2000年代以降、一部の多国籍企業が組織再編やグループ内取引の価格操作を巧みに利用し、知的財産権などを軽課税国の子会社に集中させ、利益を人為的に移転させる租税回避スキームが世界的に問題となりました。
このような「税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting、BEPS)」と呼ばれる問題に対処するため、OECD(経済協力開発機構)とG20が主導し、国際課税ルールを抜本的に見直す「BEPSプロジェクト」が始動しました。このプロジェクトの成果として、移転価格税制の厳格化やタックスヘイブン対策税制の強化など、現在運用されている国際課税ルールの多くが整備されました。現代の国際税務を理解する上で、このBEPSプロジェクトの存在は不可欠な背景知識と言えるでしょう。
組織再編と一体で理解すべき「移転価格税制」
国際的な組織再編を語る上で、避けては通れない最重要の税制が「移転価格税制」です。これは、組織再編という特別なイベントだけでなく、日常的な全ての親子会社間取引に適用される国際税務の根幹をなすルールです。
移転価格税制の基本:独立企業間価格という絶対的な物差し
移転価格税制とは、企業が海外の親会社や子会社、兄弟会社といった「国外関連者」との間で行う取引の価格(移転価格)が、もしその取引が全く資本関係のない第三者との間で行われたとしたら成立したであろう価格(独立企業間価格:Arm’s Length Price)と異なっている場合に、その取引を独立企業間価格で行われたものとみなして課税所得を再計算する制度です。
重要なのは、この税制が「企業に租税回避の意図があったかどうか」を問わない点です。たとえビジネス上の理由から子会社を支援する目的で安価に製品を販売したとしても、その価格が独立企業間価格から乖離していれば、機械的に適用され、差額分の所得が日本で課税されることになります。
対象となる取引の範囲
移転価格税制の対象は、国外関連者との間で行われるほぼ全ての取引に及びます。主なものは以下の4つに分類されます。
- 有形資産の取引:製品や部品、原材料などの売買取引。
- 無形資産の取引:特許権や商標権(ブランド)、ノウハウなどの使用許諾(ライセンス)に伴うロイヤルティの支払い。
- 役務提供:経営指導、経理・法務などのバックオフィス業務支援、技術サポートといったサービスの提供。
- 金融取引:親子会社間の資金の貸付(親子ローン)や、子会社の銀行借入に対する親会社の債務保証など。
組織再編で特に問題となる移転価格税制上の論点
組織再編が行われると、グループ内の機能・資産・リスクの配分が大きく変わるため、それに伴い、上記で挙げたような関連者間取引の価格設定の妥当性が改めて問われることになります。
無形資産の移転とDEMPE分析
組織再編の中でも、特許権やブランドといった価値の高い「無形資産」が海外子会社に移転されるケースは、税務調査における最重要ターゲットの一つです 。
BEPSプロジェクト以降、無形資産から生じる利益の帰属を判断する上で、国際的に「DEMPE分析」という考え方が標準となりました。これは、単に無形資産の法的な所有者(Legal Owner)であるというだけで利益を得る権利はなく、その無形資産の価値創造に貢献した以下の機能を実際に誰が果たしたかによって利益配分を決めるべきだ、という考え方です。
- Development(開発)
- Enhancement(改良)
- Maintenance(維持)
- Protection(保護)
- Exploitation(活用)
例えばある会社の日本本社が、長年かけて築き上げたブランドの法的所有権だけを税率の低いスイスの子会社に移転したとします。しかし、その後もブランド価値を高めるためのグローバルなマーケティング戦略の立案や広告宣伝活動(Enhancement / Exploitation機能)を日本本社がコントロールし費用も負担しているのであれば、ブランドから生じる利益の大部分は、依然として日本本社に帰属すべきだと判断されます。形式的な所有権の移転だけでは、税務上の利益移転は認められないのです。
役務提供と寄附金認定リスク
日本親会社が海外子会社に対して行う経営指導や業務支援といった「グループ内役務提供」も、移転価格税制の対象です。これらのサービスが無償、または独立企業間価格よりも著しく低い対価で行われた場合、税務当局はその取引を二つの異なる側面から問題視します。
一つは移転価格税制の観点ですが、もう一つ、より深刻なのが「国外関連者に対する寄附金」と認定されるリスクです。親会社が子会社に無償で提供したサービスの価値に相当する経済的利益が、親会社から子会社への寄附とみなされるのです。日本の法人税法では、国外関連者に対する寄附金はその全額が損金の額に算入されない(つまり、経費として認められない)という非常に厳しい規定があります。そしてさらに重大なのは、寄附金として認定された場合、移転価格課税と異なり、二重課税を解消するための国家間の話し合いである「相互協議」の対象とならないのが一般的である点です。これは、日本で課税された上に、海外子会社の国でも対応する税金の還付が受けられず、グループ全体として完全な二重課税状態に陥ることを意味します。
このリスクを回避するため、実務上は提供する役務の対価を適切に回収することが不可欠です。特に、経理やITサポートといった付加価値の低い定型的な支援業務については、その提供にかかった総原価(直接費+間接費)に5%の利益を上乗せした金額(マークアップ)を対価として請求することが、独立企業間価格として認められる簡便法(低付加価値役務提供)が用意されています(OECDガイドラインによる提唱)。
金融取引(親子ローン・債務保証)
グローバルに事業を展開する企業グループでは、資金効率の観点から親会社が海外子会社に直接資金を貸し付けたり(親子ローン)、子会社が現地で銀行から借り入れる際に親会社が債務保証を行ったりすることがよくあります。これらの金融取引も移転価格税制の対象であり、設定された金利や保証料が独立企業間価格であることが求められます。
特に、2022年6月に国税庁が公表した「移転価格事務運営要領」の一部改正により、この分野の取り扱いは大きく変わりました。改正前は、貸し手である親会社の資金調達コストなどを参考に金利を設定することも一定の状況下で許容されていましたが、改正後は、そのような簡便的な方法は原則として認められなくなりました。現在の国際標準では、借り手である海外子会社が「親会社の支援なしに、子会社単独で市場から資金調達した場合に適用されるであろう金利(=子会社の信用力に基づく金利)」を算定することが求められています。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
組織再編に関連する国際的租税回避防止ルール
移転価格税制のほかにも、国際的な組織再編を検討する上で理解しておくべき重要な租税回避防止ルールが存在します。これらは相互に関連し合っており、多角的な視点でのリスク分析が不可欠です。
タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の概要
タックスヘイブン対策税制(CFC: Controlled Foreign Company 税制、または外国子会社合算税制とも呼ばれます)は、法人税率が著しく低い国や地域(タックスヘイブン)に子会社を設立し、そこに利益を留保することで日本の税負担を不当に免れる行為を防止するための制度です。
この税制の核心は、一定の要件を満たす軽課税国の外国子会社(特定外国関係会社など)の所得を「日本の親会社の所得に合算」して日本で課税するという点にあります。組織再編によって海外に設立された統括会社や知的財産管理会社が、この税制の対象となるか否かは重要な検討事項です。
適用判定のポイント:経済活動基準
CFC税制の適用を免れるためには、その外国子会社が単なるペーパーカンパニーではなく、現地で実体のある事業活動を行っていることを証明する必要があります。その判定基準として「経済活動基準」が設けられています 。具体的には、以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。
- 事業基準:主たる事業が株式の保有や知的財産権の提供など、受動的な所得を生むものではないこと。
- 実体基準:本店所在地国に事業に必要な事務所、店舗、工場などの固定施設を有していること。
- 管理支配基準:本店所在地国において、その事業の管理、支配、運営を自ら行っていること。
- 非関連者基準または所在地国基準:業種に応じて、主として非関連者と取引を行っているか、または主としてその国で事業を行っていること。
組織再編で設立された海外子会社が、例えばレンタルオフィスを借りているだけで重要な意思決定はすべて日本の親会社の指示で行われているような場合、「実体基準」や「管理支配基準」を満たさないと判断され、CFC税制の適用対象となるリスクがあります。
過少資本税制と過大支払利子税制
これは、グループ内の資金調達の方法を利用した租税回避を防止するためのルールです。企業が海外の親会社から資金を調達する際、株主として資金を入れる「出資(エクイティ)」と、お金を借りる「貸付(デット)」の二つの方法があります。
日本の税法上、出資に対するリターンである「配当」は原則として損金(経費)になりませんが、貸付に対する「支払利子」は損金になります。この違いを利用し、出資を極端に少なく(過少資本)、貸付を過大にすることで、日本子会社の利益を支払利子の形で海外親会社に移転し、日本の税負担を軽減しようとする行為が考えられます。
過少資本税制はこのような租税回避を防ぐため、国外の支配株主等からの負債額が資本持分の一定倍率(原則として3倍)を超える場合、その超過部分に対応する支払利子の損金算入を認めないという制度です。
国際課税の新たな潮流:グローバルミニマム課税
BEPS 2.0プロジェクトの成果として、国際課税の枠組みを大きく変える「グローバル・ミニマム課税(第2の柱)」が導入されつつあります。これは、年間総収入金額が7.5億ユーロ以上の巨大多国籍企業グループを対象に、事業展開する国や地域にかかわらず、最低15%の法人税負担を求めるという画期的なルールです 。具体的には、ある国での子会社の実効税率が15%に満たない場合、その差額分(トップアップ税額)を、最終親会社が所在する国で合算して課税する「所得合算ルール(IIR)」がその中核をなします 。
この新ルールの導入は、単に軽課税国での税メリットを失わせるだけでなく、各国の「税源争奪」を一層激化させる可能性があります。例えば、これまで軽課税国にあった子会社の利益に対し、日本がIIRによってトップアップ課税を行うよりも、そもそもその利益は移転価格税制上は日本に帰属すべき所得であるとして、より高い日本の法人税率で課税しようとするインセンティブが税務当局に働く可能性があります。これにより、今後、移転価格調査がさらに厳格化されることが予想され、企業はより高度な税務リスク管理を求められることになります。
国際的な組織再編における税務リスクと実践的対策
これまで見てきたように、国際的な組織再編には様々な税務リスクが伴います。これらのリスクを適切に管理し、予期せぬ追徴課税を避けるためには平時からの入念な準備が不可欠です。
移転価格調査と寄附金認定のリスク
税務調査のプロセスと主な指摘事項
移転価格税制に関する税務調査は、通常の法人税調査とは大きく異なる特徴を持ちます。まず、調査期間が1年から3年、場合によってはそれ以上に及ぶことが珍しくありません。また、課税の対象となる期間(除斥期間)も、通常の5年ではなく原則として7年と長く設定されています(日本の場合)。
調査の過程では、会計帳簿や契約書といった書類の提出はもちろんのこと、事業内容や価格決定プロセスを理解するため、経理・財務部門だけでなく、研究開発、製造、営業といった事業部門の担当者に対しても広範かつ詳細なヒアリングが行われます。税務当局は、企業の主張する取引の形式だけでなく、その経済的実質、すなわち誰がどのような機能・リスクを担っていたのかを徹底的に解明しようとします。
追徴課税と深刻な二重課税問題
移転価格調査の結果、国外関連者との取引価格が独立企業間価格と異なると判断された場合、その差額分の所得に対して追徴課税が行われます。移転価格課税は、特定の取引だけでなく継続的な取引全体が対象となることが多いため、追徴税額は数億円から、時には数百億円という巨額に上るケースも少なくありません。そして、このリスクはもはや大企業だけのものではなく、海外展開を行う中堅・中小企業にも及んでいます。
さらに深刻なのが、「国際的な二重課税」の問題です。例えば、日本の税務当局が親会社の所得を10億円増額する更正処分を行ったとします。この10億円の所得は、取引相手である海外子会社の国では既に課税されている所得です。つまり、同じ所得に対して日本と海外子会社の国の両方で課税されてしまう状態が生じます。この二重課税を解消するためには、両国の税務当局間で話し合いを行う「相互協議」という手続きを申し立てる必要があります。しかし、相互協議は解決までに数年単位の長い時間を要する上、必ずしも両国が合意に至るとは限らず、二重課税が完全に解消されないリスクも残ります 。
リスクを回避するための事前準備
このような深刻なリスクを回避するためには、組織再編の計画段階から、あるいは日常的な取引の段階から適切な対策を講じておくことが極めて重要です。
移転価格文書化の重要性(ローカルファイル等)
BEPSプロジェクト以降、国際的なルールとして、多国籍企業グループには移転価格に関する情報を文書化することが求められています。具体的には、以下の3種類の文書から構成される3層構造の文書化が標準となっています。
- マスターファイル:グループ全体の事業概要、移転価格ポリシー、無形資産の状況などを記載した、グループの青写真となる文書。
- 国別報告書(CbCR):国・地域ごとに、収入金額や税引前利益、納税額、従業員数などを報告する文書。
- ローカルファイル:個別の国外関連取引について、その価格が独立企業間価格であることを詳細に説明・立証する文書。
この中で個別の税務調査において最も重要となるのが「ローカルファイル」です。これは、税務当局に対して自社の価格設定の正当性を主張するための、いわば「盾」となる書類です。日本の税法では、前事業年度の国外関連取引の合計額が50億円以上などの大規模な取引を行う企業に対して、確定申告期限までのローカルファイル作成(同時文書化義務)を課しています。しかし、この基準に満たない中堅・中小企業であれば何もしなくてよい、ということにはなりません。
なぜなら、文書化義務がない企業であっても、税務調査の際に調査官からローカルファイルに相当する資料の提出を求められることがあるからです。その際、指定された期限内(通常60日以内)に提出できなければ、税務当局は、税務当局自身が収集した類似企業の利益率などを用いて課税額を算定できる「推定課税」という強力な権限を行使できます。調査が始まってから60日間という短期間で、質の高い分析に基づいた文書を作成することは事実上不可能です。したがって、推定課税のリスクを回避するためには、取引規模にかかわらず、平時からローカルファイルを準備しておくことが、事実上の必須要件となっているのです。
事前確認制度(APA)の活用による予測可能性の確保
将来にわたる移転価格課税のリスクを抜本的に解消するための、最も確実な手段が「事前確認制度(APA: Advance Pricing Arrangement)」です。これは、企業がこれから行おうとする国外関連取引の独立企業間価格の算定方法について、事前に税務当局に申し出て、その妥当性の確認を得る制度です。
APAには、日本の税務当局との間だけで確認を得る「ユニラテラルAPA」と、取引相手国の税務当局も巻き込み、両国の当局間で合意を形成する「バイラテラルAPA」があります。バイラテラルAPAを取得すれば、日本と相手国の双方から移転価格課税を受けるリスクがなくなり、二重課税の問題を根本から回避できるという絶大なメリットがあります。
ただし、APAの申請には、詳細な分析に基づく膨大な資料の作成が必要であり、専門家の支援が不可欠です。また、特にバイラテラルAPAの場合、両国当局間の相互協議を要するため、合意に至るまでには通常2~3年程度の期間がかかります。費用と時間はかかりますが、それに見合うだけの「税務上の予測可能性」と「安心」を得られる極めて有効な手段と言えます。
まとめ
本記事では、国際税務における組織再編の概念から、その中核をなす移転価格税制、そして関連する主要な国際課税ルールと実践的なリスク対策までを概観してきました。上に挙げたような複雑で変動の激しい環境下で、個々の企業の事業内容や再編の目的に応じた最適なストラクチャーを構築し、税務リスクを適切に管理するためには高度な専門知識と豊富な経験が不可欠です。安易な自己判断は、将来的に巨額の追徴課税や二重課税といった深刻な事態を招きかねません。
海外展開や組織再編を検討される際には、計画の初期段階から国際税務に精通した専門家に相談し、自社の状況に即した適切なアドバイスを受けることをおすすめします。それが、グローバルな事業展開を成功に導き、企業価値を守るための最も確実な道筋となります。