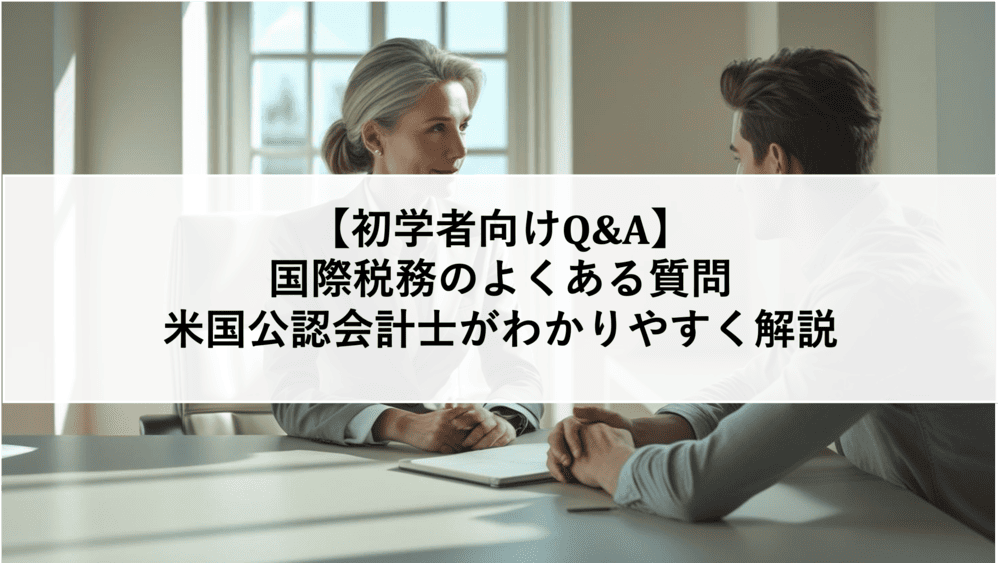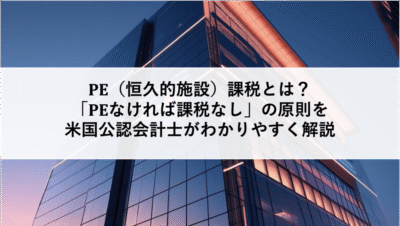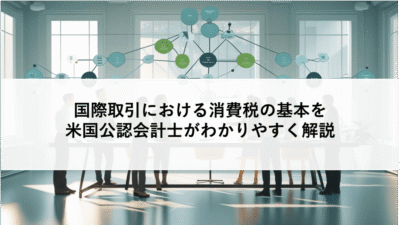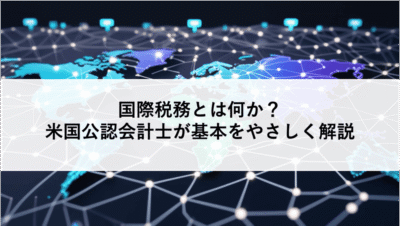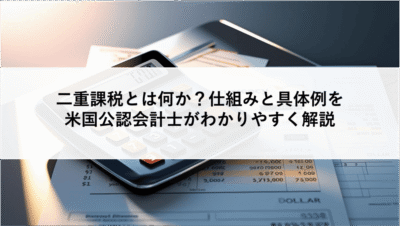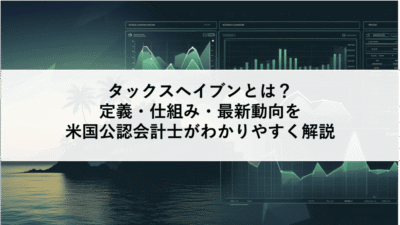海外ビジネスや個人の資産運用が当たり前になった現代において「国際税務」は決して他人事ではありません。しかし、「何から手をつければ良いかわからない」「専門用語が難しくて理解できない」と感じる方が多いのも事実です。この記事では米国公認会計士としての長年の経験に基づき、国際税務の初心者が抱きがちな基本的な疑問にQ&A形式で一つひとつ丁寧にお答えします。海外赴任、海外投資、二重課税といった具体的なテーマを取り上げ、できる限り平易な言葉で解説を進めます。
第1部:国際税務の「キホン」を理解する
Q1. そもそも「国際税務」とは何ですか?
A. 簡潔に言えば、個人や法人の活動が2つ以上の国にまたがる際に発生する税金に関するルールや手続きの総称です。
多くの方が誤解されがちなのですが、「国際税務」という名前の単一の法律が存在するわけではありません。その実態は日本の所得税法や法人税法といった国内法、取引相手国の税法、そしてそれらの国同士が結んだ「租税条約」といった複数のルールが複雑に絡み合って構成される分野。この様々な法律がパッチワークのように組み合わさっている構造こそが、国際税務が難解とされる根本的な理由です。一つのルールを学ぶのではなく、複数の法体系間の相互作用を読み解く必要があります。
国際税務の本質は、国境を越えて生じる所得や取引に対して「どの国が、どの所得に、どのように課税する権利を持つのか」という国家間の課税権の配分を調整することにあります 。例えば、日本の企業が海外に子会社を設立して利益をあげる、個人が海外へ転勤して給与を受け取る、あるいは海外の不動産や株式に投資して収益を得るといったあらゆる国際的な経済活動がその対象となります。
Q2. なぜ国際税務の知識が必要なのですか?―「二重課税」の問題
A. 最大の理由は、一つの所得に対して複数の国から税金が課される「二重課税」という不利益を避けるためです。
二重課税とは、同一の納税者が得た同一の所得に対して複数の国が課税権を主張することで発生する現象を指します。この問題の背景には国家間の課税ルールの根本的な対立があります。一つは納税者が住んでいる国が課税権を持つという「居住地国課税」、もう一つは所得が発生した国が課税権を持つという「源泉地国課税」です。
例えば、日本に住んでいる方が米国の企業でリモートワークをして収入を得たとします。この場合、所得が発生した国(源泉地国)である米国がその所得に課税しようとする一方で、その方が住んでいる国(居住地国)である日本も課税しようとします。特に日本の税法では、国内に住む「居住者」に対して所得が世界のどこで発生したかにかかわらず、そのすべての所得に課税する「全世界所得課税方式」を採用しているため、この二重課税の問題が非常に生じやすくなっています。
もしこの二重課税を放置すれば海外で得た利益の大部分が税金で失われ、国際的なビジネスや投資の大きな障壁となってしまいます。そこで、国際税務という分野ではこの不合理な状態を調整するための様々な仕組みが用意されています。後述する「租税条約」や「外国税額控除」といった制度は、まさにこの二重課税という中心的な問題を解決するために設計されたいわば国際経済の潤滑油のような役割を担っています。
Q3. 国際税務で最も重要な「居住者」と「非居住者」の違いとは?
A. 日本の税法上、どこまでの所得が課税対象になるかを決定づける最も根本的な課税区分です。この判定一つで、納税義務の範囲が全く異なります。
居住者(Resident)とは
日本の所得税法上、「居住者」とは日本国内に「住所」を持つか、または現在まで継続して1年以上「居所」を持つ個人を指します。しばしば混乱される方が多いですが、この判定に国籍は一切関係ありませんので注意が必要です。
- 住所とは「生活の本拠」 「住所」は、単に住民票がある場所ではなく、「その人の生活の中心が客観的に見てどこにあるか」という実態で判断されます 。具体的には、職業、国内で生計を共にする家族の有無、保有資産の所在といった複数の要素を総合的に考慮して判定されます。そのため、海外での滞在日数が1年の半分(183日)を超えているからといって直ちに日本の居住者ではないと判断されるわけではない点に、細心の注意が必要です。この「生活の本拠」という概念は多分に解釈の余地があり、税務当局との見解の相違が生じやすいポイントでもあります。
- 居所とは 「居所」は、生活の本拠とまでは言えないものの相当期間にわたって継続して居住している場所を指します。
居住者と判定された場合、原則として日本国内で得た所得(国内源泉所得)も海外で得た所得(国外源泉所得)も、そのすべてが日本の所得税の課税対象となります。これを「全世界所得課税」と呼びます。
非居住者 (Non-resident)とは
上記の「居住者」の定義に当てはまらない個人が「非居住者」となります。典型的な例は、1年以上の予定で海外へ転勤する方などです。非居住者の場合、日本の所得税が課されるのは日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限定されます。海外での勤務に対する給与など、国外で発生した所得については原則として日本での課税義務はありません。
この「居住者」「非居住者」の区分は、国際税務のあらゆる論点の出発点となります。ご自身の状況がどちらに該当するかを正確に把握することが、国際税務を理解する上での第一歩です。より詳しい定義については、国税庁のウェブサイトをご参照ください。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
第2部:個人に関するよくあるケース
Q4. 1年以上の海外赴任が決まりました。日本の税金はどうなりますか?
A. 1年以上の予定での海外勤務の場合、原則として日本を出国した日の翌日から「非居住者」となり、日本の所得税と住民税の取り扱いが大きく変わります。
所得税の取り扱い
非居住者となった後は、海外での勤務に対して現地で支払われる給与(国外源泉所得)には、原則として日本の所得税は課税されません。ただし、出国するまでの期間(その年の1月1日から出国日まで)に日本国内で得た給与については日本の居住者として課税対象となります。そのため多くの企業では、従業員の出国前にその年最後の給与を支払う際に年末調整を行います。これを一般に「出国時年末調整」と呼びます。
この出国時年末調整は通常の年末調整と異なる点がいくつかあります。例えば、生命保険料控除や社会保険料控除の対象となるのは出国日までに実際に支払った保険料のみです。また、配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうかは、通常の12月31日時点ではなく出国時点の現況で判断される点に注意が必要です。
住民税の取り扱い
住民税の扱いは所得税と異なり、注意が必要です。住民税は、その年の1月1日時点に住所がある市区町村において前年の所得に基づいて課税される仕組みです。したがって、例えば2024年4月に海外へ出国した場合でも2024年1月1日時点では日本に住所があるため、2023年分の所得に対する住民税(2024年度分)は全額納付する義務があります。
Q5. 海外在住中(非居住者)でも日本で確定申告が必要な場合はありますか?
A. はい、非居住者であっても日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合には、日本で確定申告が必要になることがあります。
非居住者の日本の所得税における課税対象はあくまで「日本国内で発生した所得」に限定されます 。しかし、「国内源泉所得」の範囲はご自身が日本にいないからといって無関係だと考えると思わぬ課税対象となることがあり、注意が必要です。国内源泉所得には所得税法で17種類が定められていますが 、非居住者にとって関係することが多い代表的な例は以下の通りです。
- 日本国内にある不動産の賃貸料や売却益: 例えば、海外在住中に日本に所有するマンションを貸して得た家賃収入やそのマンションを売却して得た利益は典型的な国内源泉所得です。
- 日本国内での役務提供の対価: 海外在住中の方が一時的に日本に出張して講演を行い、その対価として報酬を受け取った場合、その報酬は国内源泉所得に該当します。
- 日本の内国法人から受ける配当金: 日本の株式会社の株式を保有していて配当金を受け取った場合、その配当金は国内源泉所得となります。
- 日本の内国法人の役員報酬: これは特に注意が必要な点ですが、日本の法人の役員である場合にはその役務提供を海外で行っていたとしてもその報酬は原則として国内源泉所得とみなされます。
これらの国内源泉所得がある場合には原則として日本で確定申告を行い、納税する必要があります。ただし、所得の種類によっては支払いを受ける際に一定の税率で源泉徴収されるだけで納税が完了する「源泉分離課税」が適用され、確定申告が不要となるケースもあります。
Q6. 海外から確定申告するにはどうすればよいですか?「納税管理人」とは?
A. 日本に居住していない方が確定申告などの税務手続きを行うためには、ご自身に代わって手続きを行う代理人として「納税管理人」を選任し、税務署に届け出る必要があります。
納税管理人とは「非居住者本人に代わって税務署とのやり取りを行う代理人」を指します。具体的には、確定申告書の提出、税金の納付、還付金の受領など税務手続きを一括して代行します。税務署から送付される書類も、すべて納税管理人宛に送られます。納税管理人を定めた場合、原則として出国日までに「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を出国前の納税地を管轄する税務署長に提出する必要があります。
納税管理人は日本国内に住所または居所を有する個人や法人であれば誰でも選任可能です。例えば、家族や友人に依頼することもできますし、税理士などの専門家に依頼することもできます。ただし、納税管理人の法的な役割は「提出」や「納付・受領」といった手続きの代行に限られます。確定申告書の「作成」そのものは、納税者本人または税理士などの専門家が行う必要がありますので、申告内容が複雑な場合には申告書の作成を税理士に依頼し、そのまま納税管理人にもなってもらう方法が最も確実で安心といえます。
第3部:知っておきたい重要制度
Q7. 「租税条約」とは、わかりやすく言うと何ですか?
A. 二国間で個別に結ばれる「税金に関する特別な約束事」です。主な目的は、「国際的な二重課税の防止」と「脱税や租税回避行為の防止」にあります。
租税条約は国際税務において極めて重要な役割を果たします。その最大の特徴は、それぞれの国の国内税法よりも優先して適用される非常に強力なルールであるという点です。例として、租税条約に定められていることの多い内容は以下の通りです。
- 二重課税の排除:どちらの国がどのような所得に課税できるかという課税権の範囲を定めたり、一方の国で課税された税金をもう一方の国で控除する方法を規定したりします。
- 源泉税率の軽減:国境を越えて支払われる配当、利子、使用料(ロイヤルティ)といった投資所得に対して、所得の源泉地国が課税できる税率の上限(限度税率)を定めます。これにより、国内法で定められた税率よりも低い税率が適用され、二重課税が効果的に軽減されます。
- 情報交換:両国の税務当局が、脱税などを防止するために納税者に関する情報を交換するための規定も含まれています。
重要なのは、租税条約による税率の軽減や免除といった恩恵は自動的に適用されるわけではないという点です。原則として、これらの特典を受けるためには所得の支払者を通じて事前に「租税条約に関する届出書」を日本の税務署に提出する手続きが必要です。この手続きを怠ると国内法の高い税率で源泉徴収されてしまい、後から還付を受けるためには煩雑な手続きが必要になる場合があります。
日本は多くの国と租税条約を締結していますが、その内容は相手国ごとに異なります 。したがって、国際取引を行う際には必ず相手国との租税条約の有無とその内容を個別に確認することが不可欠です。
Q8. 「外国税額控除」とは、どのような制度ですか?
A. 外国で納付した所得税額を日本の所得税額から直接差し引くことができる制度です。これは、租税条約と並んで国際的な二重課税を調整するための最も主要な仕組みの一つです。
この制度の目的は、日本の居住者が国外で得た所得(国外源泉所得)について、現地の国で納税し、さらに日本でも全世界所得課税に基づき納税するという二重課税の状態を日本の税金計算の段階で調整することにあります。その仕組みは一見すると複雑ですが、基本的な考え方は「外国に納めた税額」と「日本で計算した控除限度額」を比較し、いずれか少ない方の金額を納付すべき日本の所得税額から直接控除するというシンプルなものです。
ここで重要なのが「控除限度額」という概念です。外国でいくら高い税金を払ったとしても全額が日本で控除できるわけではありません。控除できる金額には上限が設けられており、その限度額は大まかには以下の計算式で算出されます。
この式が意味するのは、控除できる上限額はその人の所得全体に占める「国外所得の割合」に応じて決まるということです 。つまり、この制度はあくまで二重課税を排除するためのものであり、外国の高い税金を日本が肩代わりする制度ではないという点を理解することが重要です。
なお、この外国税額控除の適用を受けるためには必ず確定申告を行う必要があります。給与所得のみで普段は会社で年末調整が完了している方でも、この控除を利用したい場合にはご自身で確定申告をしなければなりません。その際、確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」や外国で税金を納付したことを証明する書類などを添付して提出することを忘れないようにしてください。
第4部:海外の資産について
Q9. 海外に5,000万円を超える資産があります。何か手続きは必要ですか?
A. はい、その年の12月31日時点で資産の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する日本の居住者(非永住者を除く)は「国外財産調書」という書類を(その年の翌年の6月30日までに)住所地等の所轄税務署に提出する義務があります。
この制度は、国際的な資産移転が容易になる中で富裕層などが海外に資産を移すことによる課税逃れを防ぎ、国内の税務当局が国外の資産状況を正確に把握することで、適正な課税を確保する目的で導入されています。
Q10. どのようなものが「国外財産」にあたりますか?
A. 国外にある不動産、預貯金、有価証券などが典型例です。ただし、ある財産が「国内」にあるか「国外」にあるかの判定は物理的な場所のイメージとは異なる場合があり、財産の種類ごとに法律で細かく基準が定められています。国税庁が公表しているFAQには、その詳細な判定基準が示されています 。主な財産の所在地の判定基準は以下の通りです。
- 不動産(土地・建物): その不動産の所在地で判定します。海外にある不動産は国外財産です。
- 預貯金: 預金を受け入れた金融機関の営業所(支店)の所在地で判定します 。したがって、日本の銀行の海外支店にある預金は国外財産ですし、逆に外資系銀行の日本支店にある預金は国内財産となります。
- 有価証券(株式など): 原則としてその株式を発行した法人の本店所在地で判定します。しかし、証券会社の特定の口座で管理されている場合はその口座が開設されている証券会社の営業所の所在地で判定されるため、注意が必要です。
特に注意が必要なのが、近年保有者が増えている暗号資産(仮想通貨)についてのルールです。暗号資産の所在地は、利用している取引所が海外にあるかどうかではなく、「その暗号資産を保有している人の住所地によって判定される」という非常に特殊なルールになっています 。国外財産調書の提出義務者は「日本の居住者」ですから、日本の居住者が保有する暗号資産はたとえ海外の取引所のウォレットで管理していても全て「国内財産」として扱われますので、国外財産調書の記載対象にはなりません。
より詳細な情報については、国税庁のFAQをご参照ください。
まとめ
この記事では、国際税務に関して初学者が抱きがちな10の基本的な質問にQ&A形式でお答えしました。複雑に見える国際税務ですが、その根底には本記事でご紹介したようないくつかの重要な原則があり、そうした原則を丁寧に押さえておけば大きな税務リスクを抱える心配はないといえます。しかし、実際に海外赴任が決まった、海外資産を相続したなど、具体的な判断や手続きに直面した際には決して自己判断で進めることなく、国際税務に精通した専門家へ相談することを強くお勧めします。
なお、当サイトでは匿名・無料で相談できる窓口「みんなの国際税務Q&A」を設けています。国際税務に精通した会計士が一般的な見地から回答し、皆様の一次的な問題解決をサポートいたしますのでお気軽にご質問ください。有料の専門家への個別相談前にぜひ一度ご活用いただいたり、セカンドオピニオンとしてご活用いただいたりなど、皆様の国際税務対応に少しでも役立ていただければと思います。