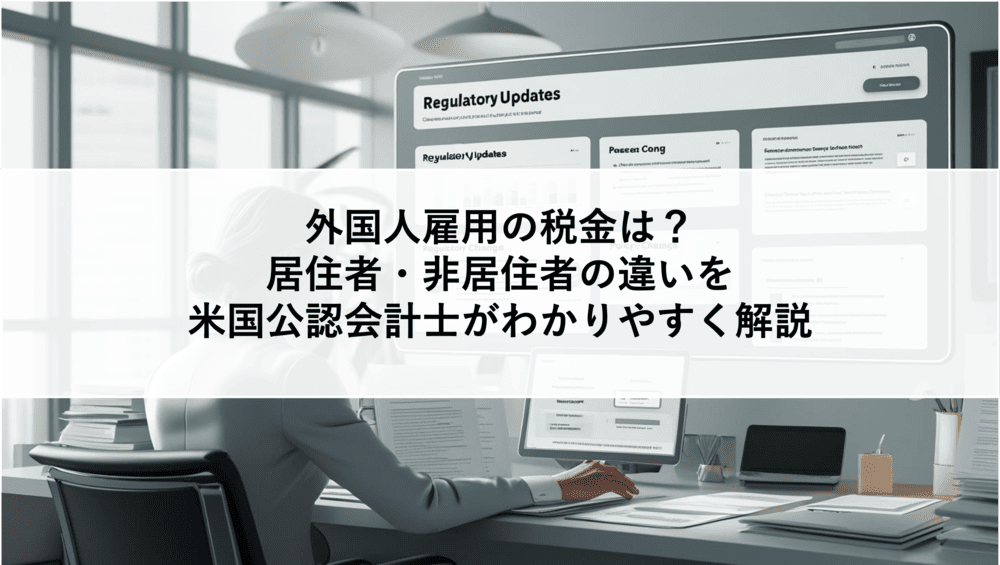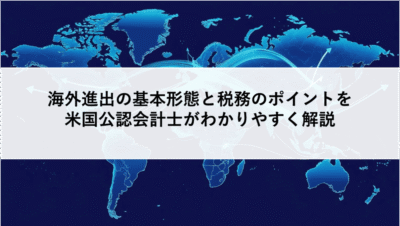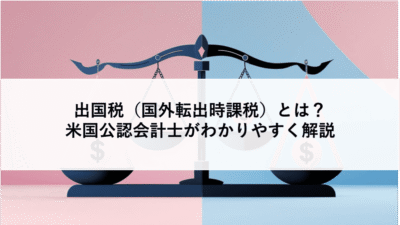外国人を雇用する際の税金や源泉徴収で悩んでいませんか?この記事では、最も重要な「居住者」と「非居住者」の区分から、給与計算時の所得税、住民税、租税条約の適用まで、国際税務の専門家が基本を分かりやすく解説します。前提として、本記事では「日本において」外国人従業員を雇用するケースを考えます(海外で外国人従業員を雇用するケースについては別の記事にて解説します)。
はじめに:外国人雇用の税務、最初の関門は「居住者」か「非居住者」か
グローバル化が進む現代において、外国人を雇用することは企業にとって珍しいことではなくなりました。しかし、日本人従業員とは異なる税務上の取扱いに戸惑う人事・経理担当者の方も少なくないのではないでしょうか。
特に、給与から源泉徴収する所得税の計算は、その外国人従業員が日本の税法上で「居住者」と「非居住者」のどちらに区分されるかによって、課税の範囲や税率が大きく異なります。この最初の区分を誤ると、追徴課税などの思わぬリスクにつながる可能性もあります。
この記事では、企業の担当者が押さえておくべき外国人雇用に関する税務の基本、特に「居住者」と「非居住者」の区分に応じた給与の源泉徴収について、順を追って分かりやすく解説します。
最重要ポイント:「居住者」と「非居住者」の判定
外国人従業員の税務を考える上で、すべての出発点となるのが税務上の「居住者」と「非居住者」の区分です。なぜなら、どちらに該当するかで、課税される所得の範囲が変わるためです。単純に「日本に住んでいるかどうか、もしくは国籍が日本かどうか」という単純な定義ではありませんので、注意が必要です。次項にて、日本の所得税法における定義をおさえておきましょう。
税務上の「居住者」とは
日本の所得税法上、「居住者」とは「日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上、居所を有する個人」をいいます。単純に国籍が外国というだけでは判断されません。
- 住所: 個人の生活の本拠(生活の中心)を指します。客観的な事実、例えば、住居、職業、資産の所在、家族の居住状況などから総合的に判断されます。
- 居所: 生活の本拠とはいえないまでも、ある程度の期間継続して居住する場所を指します。例えば、海外に生活の本拠がある人が日本での長期プロジェクトのために1年以上の契約でホテルやサービスアパートメントに滞在する場合、その場所が居所と認定されることがあります。
したがって、日本で採用し、日本で生活の基盤を置いて働く外国人従業員は、基本的に税務上は「居住者」に該当します。
税務上の「非居住者」とは
日本の所得税法上、「非居住者」とは、上記の「居住者」以外の個人を指します。例えば、海外の親会社から日本の支社へ1年未満の予定で出張してくる従業員や、海外に住みながら日本のプロジェクトにリモートで参加するようなケースが考えられます。
この「居住者」「非居住者」の判定は、入国後の滞在期間や契約内容、生活実態に基づいて行われるため、判断に迷うケースも少なくありません。こちらの判定を誤ると税務上の問題に直結するため、慎重な確認が必要になります。
【区分別】給与にかかる所得税の具体的な取扱い
「居住者」と「非居住者」の区分がついたら、次はそれぞれの給与計算における所得税の取扱いを見ていきましょう。
「居住者」である外国人従業員のケース
外国人従業員が「居住者」と判定された場合、税務上の取扱いは基本的に日本人従業員と同じです。
課税対象となる所得
居住者は、所得が生じた場所が国内か国外かを問わず、そのすべての所得(全世界所得)に対して日本の所得税が課税されます。これを「全世界所得課税」と呼びます。
源泉徴収と年末調整
毎月の給与からは、他の日本人従業員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて所得税を源泉徴収します。そして年末には年末調整を行い、年間の所得税額を確定させ、過不足がある場合には精算します。扶養控除や生命保険料控除などの各種所得控除も、要件を満たせば日本人と同様に適用されます。
ただし、国外に居住する親族を扶養控除の対象とする場合には、その親族関係や送金の事実を証明する書類(親族関係書類および送金関係書類)が必要となる点に注意が必要です。
「非居住者」である外国人従業員のケース
一方、従業員が「非居住者」と判定された場合は、取扱いが大きく異なります。ここが最も注意すべき点となります。
課税対象となる所得
非居住者の場合、課税対象は「国内源泉所得」に限定されます。つまり、日本国内での勤務によって得た給与のみが課税対象です。例えば、海外での勤務期間に対応する給与は、原則として日本の課税対象にはなりません。
源泉徴収と年末調整
非居住者に支払う給与からは、原則として支払額に対し一律20.42%(復興特別所得税を含む)の税率で所得税を源泉徴収します。居住者のように給与の額や扶養親族の数に応じて税額が変わることはありません。また、非居住者は年末調整の対象とはなりません。源泉徴収された20.42%の税金で、原則として日本での所得税の課税関係は完結します。各種所得控除の適用もありません。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
知っておくべき例外:租税条約による免税措置
非居住者への課税については、もう一つ重要な論点があります。それが「租税条約」です。日本は多くの国と租税条約を締結しており、二重課税の排除や脱税の防止などを目的としています。この租税条約に、非居住者の給与所得に関する特別な規定(免税規定)が設けられている場合があります。
例えば、「短期滞在者免税」がその代表例です。これは、一定の要件を満たす非居住者の日本での滞在が「ごく短期間」である場合に、日本での課税を免除するというものです。一般的な要件は以下の通りですが、詳細は個別の租税条約によって異なります。
- 日本での滞在日数が、その課税年度(暦年)を通じて合計183日を超えないこと
- 給与の支払者が、日本の居住者(企業など)でないこと
- 給与が、日本にある支店など、支払者(外国法人)の恒久的施設によって負担されるものでないこと
この免税措置の適用を受けるためには、最初の給与の支払日の前日までに、従業員本人が「租税条約に関する届出書」を、給与の支払者(雇用主)を経由して所轄の税務署長に提出する必要があります。この手続きを怠ると、免税が受けられませんので注意が必要です。
所得税以外の税金と社会保険の取扱いはどうなる?
外国人雇用においては、所得税だけでなく、住民税や社会保険についても正しく理解しておく必要があります。
住民税について
住民税(都道府県民税・市町村民税)は、その年の1月1日時点で日本国内に住所がある人(対象年度の1月1日時点で住民票が国内にある場合など)に対して、前年中の所得を基に課税されます。
したがって、年の途中に来日して入社した外国人従業員はその年の住民税は課税されません。住民税がかかるのは、翌年1月1日時点で日本に住所があり「居住者」とみなされている場合です。
社会保険について
社会保険は、国籍を問わず、適用事業所で常時使用される従業員は原則として被保険者となります。つまり、外国人従業員であっても加入義務があります。
ただし、海外の社会保障制度にも加入している等の理由で厚生年金保険に係る年金拠出が二重払い(日本での年金拠出と外国での年金拠出)になってしまうケースがあります。こうした二重の負担を軽減するため、日本は多くの国と「社会保障協定」を結んでいます。この協定により、相手国の社会保障制度に加入していることが証明されれば、日本の社会保険(厚生年金保険)への加入(年金拠出)が免除される場合があります(一般に、健康保険については免除されません)。なお、適用を受けるには相手国の社会保障当局が発行する「適用証明書(Certificate of Coverage)」の提出が必要となります。
まとめ:外国人雇用の税務は基本の理解と適切な手続きが鍵
外国人従業員を日本で雇用する際の税務について一般論を解説しました。最後に重要なポイントをまとめます。
- 最初のステップは「居住者」と「非居住者」の区分を正しく行うこと。
- 「居住者」であれば、原則として日本人従業員と同様の取扱い(全世界所得課税、年末調整あり)。
- 「非居住者」であれば、原則として国内源泉所得に一律20.42%を源泉徴収(年末調整なし)。
- 「非居住者」でも、租税条約により所得税が免除される場合がある(租税条約適用のための事前届出が必要)。
- 住民税や社会保険についても、それぞれルールを正しく理解し、手続きを行う。
外国人雇用に関する税務は、個々の従業員の滞在目的や期間、家族の状況などによって判断が複雑になることがあります。特に「居住者」と「非居住者」の判定や、租税条約の適用については、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。本記事にて取り上げた基本ルールを理解した上で、もし判断に迷うようなケースがあれば、自己判断で進めるのではなく、所轄の税務署や国内法に精通した税理士などの専門家に相談することをお勧めします。適切な対応が、将来の税務リスクを回避し、企業と従業員の双方にとって良好な関係を築くための第一歩となります。