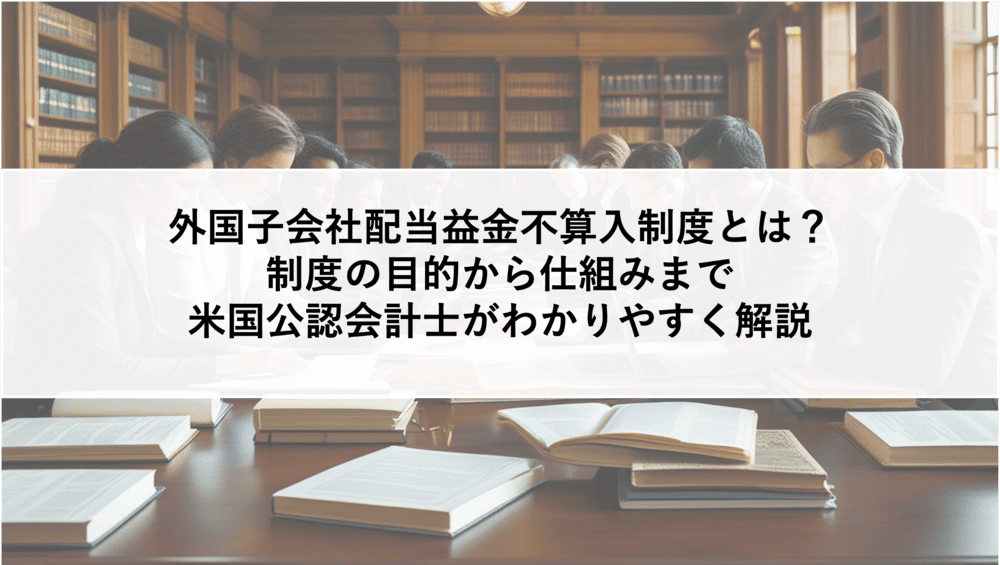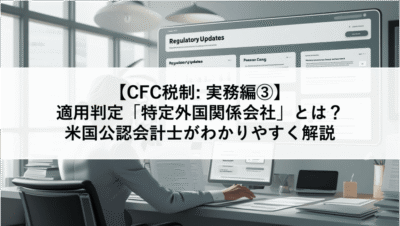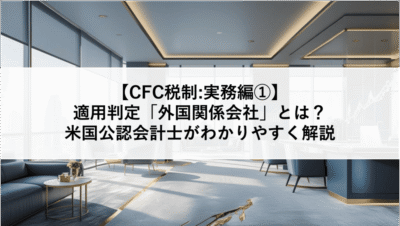「海外子会社からの配当金には外国側と日本側で二重で税金がかかるのか?」そのように考える方も少なくないのではないでしょうか。「外国子会社配当益金不算入制度」は、このような国際取引における二重課税を解消する重要な仕組みです。制度の目的から基本用語まで、国際税務に精通した会計士が丁寧に、わかりやすく解説します。
はじめに:海外子会社からの配当、税金はどうなっていますか?
海外に子会社を設立し、グローバルに事業を展開する日本企業は年々増加しています。事業が軌道に乗り、現地の利益を配当として日本に還流させる場面も出てくるでしょう。その際に、多くの経理・財務担当者が直面するのが「税金の問題」です。
「海外の子会社で法人税を支払った後の利益から配当を受け取っているのに、この受け取った配当に対して日本でもう一度法人税がかかるのだろうか?」
このような疑問は当然のものです。もし同じ利益に対して二重に税金が課されるとすれば、企業の国際競争力は大きく削がれてしまいます。この「国際取引における二重課税」の問題を解決するために設けられている重要な制度が、本記事で解説する「外国子会社配当益金不算入制度」です。
この記事では、国際税務の第一歩として、「この制度がなぜ必要なのか」「どのような仕組みなのか」その全体像を分かりやすく解説していきます。
なぜこの制度が必要なのか?国際的な「二重課税」の問題
外国子会社配当益金不算入制度の目的を理解するためには、まず「国際的な二重課税」という根本的な問題を理解する必要があります。
国際的な二重課税とは
例えば、日本の親会社(P社)が、米国にある子会社(S社)から配当を受け取るケースを考えてみましょう。
- まず、米国のS社は、米国内での事業活動によって得た利益に対して、米国の法人税を納税します。
- S社は、税金を支払った後の利益の中から、日本の親会社P社へ配当を支払います。
- 日本のP社がその配当金を受け取ると、日本の税法上、それはP社の「益金(収益)」として扱われます。
- その結果、P社は他の収益と合算して日本の法人税を計算するため、S社から受け取った配当金に対しても日本の法人税が課されることになります。
このように、元は同じ一つの利益(S社の事業利益)に対して、米国の法人税と日本の法人税が二重に課されてしまう。これが「国際的な二重課税」です。これでは企業が海外で得た利益を国内に還流させる意欲が削がれてしまいますよね。具体例で言えば、本国の親会社へ配当をせず、米国の子会社に利益を留保し続けるインセンティブが働くわけです。
そこでこの問題を解決するため、主に二つの方法が採用されています。一つは「外国税額控除方式」、そしてもう一つが「国外所得免除方式」です。「外国子会社配当益金不算入制度」は、後者の「国外所得免除方式」にあたる考え方に基づいています。
外国子会社配当益金不算入制度の仕組み
それでは、この制度がどのように二重課税を解消するのか、その核心部分を見ていきましょう。制度の名前を分解すると、その意味が見えてきます。
「益金不算入」をわかりやすく解説
まず、法人税の計算における「益金」とは、会計上の「収益」に似た概念で、税法上の儲けを指します。そして「不算入」とは、文字通り「算入しない」、つまり「含めない」という意味です。したがって、「外国子会社からの配当を益金に算入しない」とは、「外国子会社から受け取った配当金は、日本の法人税を計算する際の儲け(益金)として扱わなくてよい」という意味になります。
先ほどの例で言えば、P社がS社から受け取った配当金がP社の課税対象となる所得に含まれなくなるため、結果として配当金に対して日本の法人税が課されなくなり、二重課税が回避されるのです。
制度の仕組み:なぜ「95%」を非課税にするのか
この制度では、外国子会社から受け取った配当のうち「95%」に相当する金額が益金不算入とされます。
「なぜ100%が益金不算入にならないのか?」と疑問に思われるかもしれません。これは、日本の親会社が配当を受け取るにあたり、管理部門の人件費などの間接的な経費を親会社側で負担していると考えられているためです。そのため、こうした経費に対応する部分として配当額の5%相当分が益金に算入(=課税対象)される仕組みになっています。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
制度を理解するための基本用語
この制度の適用を考える上で、最低限おさえておきたい基本的な用語がいくつかあります。ここでは、その中でも特に重要なものを解説します。
対象となる「外国子会社」とは?
この制度が適用できる配当は、どの海外企業からのものでも良いわけではなく、「税法上の外国子会社」から受け取ったものである必要があります。
「税法上の外国子会社」に該当するための要件はいくつかありますが、特に重要なのが株式の保有割合と保有期間です。具体的には、配当等の支払義務が確定する日(効力発生日)において、日本の内国法人がその外国法人の発行済株式等の25%以上を、6ヶ月以上継続して保有していることなどが要件とされています(租税条約により、より緩やかな保有割合が定められている場合もあります)。
つまり、一時的に少額の株式を保有しているだけでは、この制度の対象とはなりません。一定期間、継続して、相当程度の資本関係があることが求められます。
「剰余金の配当等」とは?
この制度の対象となるのは、一般的にイメージされる「配当金」だけではありません。法人税法ではこれを「剰余金の配当等」と広く定義しており、会社が株主に対して行う利益の分配行為全般が含まれます。具体的には、以下のようなものが該当します:
-
定時配当(通常の期末配当や中間配当)
-
特別配当(臨時的に実施される配当)
-
剰余金の分配(解散時の残余財産の分配なども含む)
-
みなし配当(資本の払い戻しや自己株式の取得等で、実質的に利益分配とみなされるもの)
たとえば、外国子会社が日本の親会社に対して「自己株式を買い戻した結果、資本剰余金が減った」というような場合でも、その実態が利益の還元と評価されれば「剰余金の配当等」として課税対象となります。
「剰余金の配当等」という表現は、形式的に「配当金」と書かれていなくても、経済的に株主への利益の移転とみなされるもの全般を広く含んでおり、みなし配当の扱いが非常に重要です。この点は、特に組織再編や資本取引を通じた利益還元が行われる場合に留意が必要です。
もう一つの方法「外国税額控除」との違いは?
国際二重課税を排除する方法として、この益金不算入制度のほかに「外国税額控除」という制度があることを少しだけ述べました。この二つの制度は、二重課税を排除するという目的は同じですが、そのアプローチが異なります。
- 外国子会社配当益金不算入制度(所得免除方式): 配当収益そのものを、そもそも日本の課税所得に含めない、という考え方。
- 外国税額控除制度(税額控除方式): 配当収益は日本の課税所得に含めて法人税額を計算した上で、その法人税額から、外国子会社が現地で納付した法人税のうち配当に対応する部分を直接差し引く、という考え方。
日本の法人税制において、外国子会社から受け取る配当については、原則として「外国子会社配当益金不算入制度」(所得免除方式)が適用されます。つまり、本制度の適用対象となる配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、外国税額控除の対象とならず(外国子会社配当益金不算入制度との併用は不可)、損金算入もできない点に注意が必要です。
まとめ
今回は、外国子会社配当益金不算入制度の基本的な考え方と仕組みについて解説しました。最後に、本記事の要点を振り返ります。
- この制度の目的は、海外子会社の利益が現地と日本の両方で課税される「国際的な二重課税」を排除することにある。
- 仕組みはシンプルで、要件を満たす外国子会社からの配当金の95%を、日本の法人税の課税対象となる所得(益金)に含めない(不算入)というもの。
- 適用を受けるためには、株式の保有割合(25%以上)や保有期間(6ヶ月以上)といった要件を満たす必要がある。
この制度は、日本企業が海外で得た利益を有効活用し、さらなる国際競争力を高めるために不可欠なものです。ただし実際の適用にあたっては、外国子会社が所在する国の税制や、子会社がペーパーカンパニー等(特定外国子会社等)に該当しないかどうかの判定など、非常に専門的で複雑な検討が必要となるケースも少なくありません。
まずはこの制度の存在意義と全体像を正しく理解し、具体的な適用で判断に迷うことがあれば、必ず国際税務に精通した専門家に相談することをお勧めします。適切な税務処理は、グローバルな事業活動における重要なリスク管理の一つと言えるでしょう。