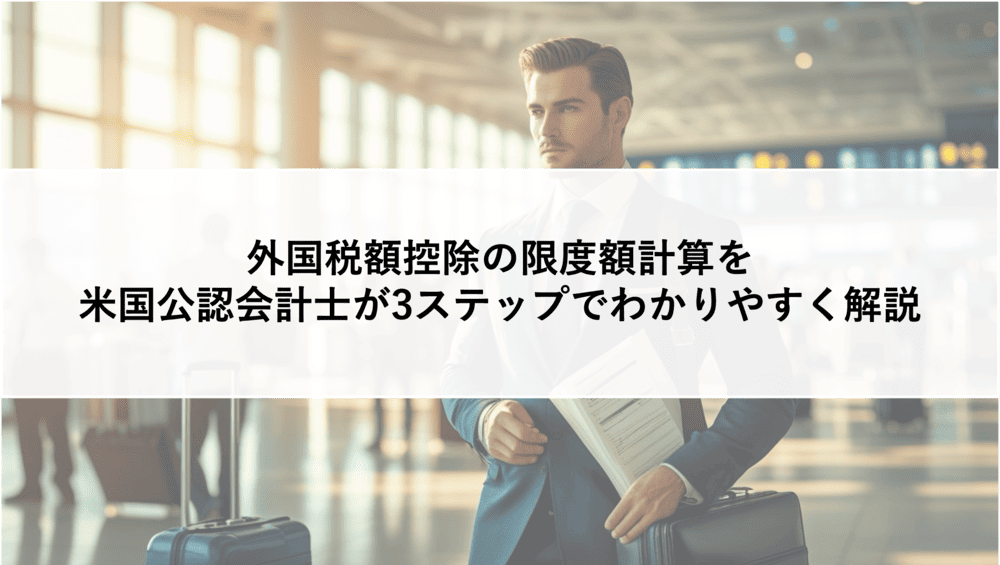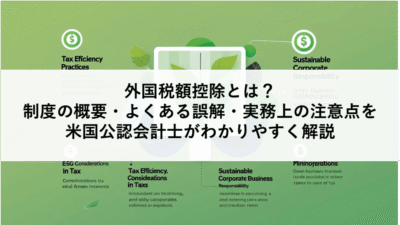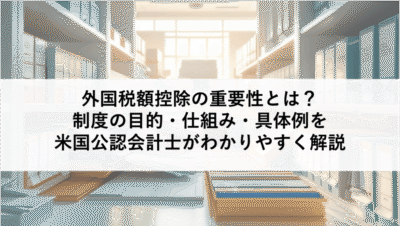本記事では、外国税額控除制度の基本から具体的な計算方法、繰越制度に至るまでを、3つのステップに分けてわかりやすく解説します。海外で税金を支払った際に同じ所得に対して自国でも課税される「二重課税」を回避するための重要な制度であり、国際税務に関わる実務担当者にとっては避けて通れないテーマです。今回は、制度の概要的な基本事項には深く触れず、「どの税金が対象になるのか」「控除の上限はどう決まるのか」といった実務上の疑問を中心に丁寧に解説していきます。
また、設例を交えながら、実際の計算方法や繰越控除の適用場面についても具体的に解説します。制度の条文を読むだけでは理解が難しいと感じる方にも、実務でのイメージを持ってもらえるよう工夫しました。海外進出企業の税務を担う方や、これから国際税務に携わる方にとって、“明日から使える”実践的な知識を提供できれば幸いです。
はじめに:国際的な二重課税を防ぐ「外国税額控除」とは
グローバルに事業を展開する日本企業にとって、国際的な二重課税の問題は避けて通れない課題です。日本の法人税法は、法人が国内で得た所得(国内源泉所得)だけでなく、国外の支店などで得た所得(国外源泉所得)も含めた全世界の所得に対して課税を行う「全世界所得課税方式」を採用しています。一方で、国外で得た所得に対しては、その所得が生じた国(源泉地国)の法令によっても法人税が課されるのが一般的です。その結果、同一の所得に対して日本と外国の双方で税金が課される「国際的二重課税」という状態が発生します。この二重課税を放置すれば、海外で事業を行う企業の税負担が過重になり、国際的な経済活動の大きな障壁となります。このような不利益を排除し、企業の国際競争力を維持するために設けられているのが「外国税額控除」制度です。
制度の趣旨は明快ですが、その適用、特に控除できる金額の上限(控除限度額)の計算は非常に複雑であり、実務上、細心の注意が求められます。本稿では、この外国税額控除の仕組み、特に法人税務担当者が最も頭を悩ませる控除限度額の計算方法について、具体的なステップと設例を交えながら、専門的な観点から深く掘り下げて解説していきます。
外国税額控除の対象となる「外国法人税」の範囲
外国税額控除を適用する第一歩は、控除の対象となる「外国法人税」が何かを正確に理解することです。外国で納付した税金であれば、すべてが控除対象になるわけではありません。控除の対象となるのは、外国の法令に基づき法人の「所得」を課税標準として課される税金、すなわち日本の法人税に相当する税金に限られます 。法人税法施行令では、超過利潤税や法人所得税への附加税なども、控除対象の外国法人税に含まれると具体的に定められています。
一方で、以下のような税金は控除の対象外となります。
- 納税者が任意に還付請求できる税金
- 納税者が納付猶予期間を任意に定められる税金
- 法人税の延滞税や過少申告加算税といった附帯税
- 付加価値税(VAT)や売上税(GST)などの間接税(これらは法人の所得ではなく、取引や消費に対して課されるため)
ここで、実務で特に注意すべき重要なルールが二つあります。
一つ目は、「高率負担部分の除外」ルールです。外国での法人税率が35%程度を超える場合、その超えた部分に相当する税額は原則として控除対象外国法人税額から除外されます。これは、日本の税制が他国の高すぎる税率までを日本の税収で補填(事実上の補助)することを避けるための規定です。外国税額控除はあくまで二重課税の排除が目的であり、他国の高税率政策を日本が負担する制度ではない、という政策的意図が背景にあります。
二つ目は、租税条約との関係です。日本が相手国と租税条約を締結している場合、配当や利子、使用料などに対して課税できる上限税率(限度税率)が定められていることがあります。もし相手国がその限度税率を超えて課税してきた場合、その超過部分は条約違反の課税とみなされ、原則として外国税額控除の対象にはなりません。この場合、控除を求めるのではなく、相手国に対して減免や還付を請求するのが本来の手続きとなります。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
【3ステップで解説】外国税額控除の限度額計算の全体像
外国で納付した法人税は、全額が必ずしも日本の法人税から控除できるわけではありません。控除できる金額には上限、すなわち「控除限度額」が設けられています。この控除限度額は、日本の税率で計算した場合の国外所得に対する法人税額を実質的な上限とするためのものです。もし限度額がなければ、日本より税率が高い国で納付した税金を使って、国内で稼いだ所得に対する日本の法人税まで減らすことができてしまい、国内の税収基盤を損なうことになりかねません。
法人税における外国税額控除の限度額は、以下の基本算式によって計算されます。
この算式は、「法人の全世界所得のうち国外所得が占める割合を算出し、その割合を日本の法人税額に乗じることで、国外所得に対応する日本での法人税相当額を計算する」という構造になっています。具体的な計算方法については、以下の3つのステップに分解して進めていきます。
- ステップ1:算式の3つの構成要素(法人税額、全世界所得金額、調整国外所得金額)をそれぞれ正確に把握する。
- ステップ2:算式に各要素を当てはめ、具体的な控除限度額を計算する。
- ステップ3:計算された限度額と、実際に納付した外国法人税額を比較し、最終的な控除額を決定するとともに、繰越制度を理解する。
ステップ1:控除限度額の計算要素を理解する
控除限度額を正しく計算するためには、算式を構成する3つの要素の定義を正確に理解することが不可欠です。
① その事業年度の法人税額
算式の最初の要素である「その事業年度の法人税額」とは、外国税額控除やその他の特定の税額控除を適用する前の法人税の額を指します 。法人税申告書別表一(一)で言えば、差引法人税額(36欄)から特定の税額控除額を調整した後の金額がベースとなります。各種税額控除を差し引いた後の最終的な税額ではない点に注意が必要です。
② 全世界所得金額
分母となる「全世界所得金額」は、その事業年度における法人の全ての所得、つまり国内源泉所得と国外源泉所得を合計した課税所得の総額です。重要なのは、この所得金額は、繰越欠損金を控除する前の金額であるという点です 。これは、控除限度額の計算においては、その事業年度単体での所得創出能力を基準とする考え方に基づいています。
③ 調整国外所得金額 – 最重要ポイント
分子となる「調整国外所得金額」は、3つの要素の中で最も複雑であり、実務上の誤りが生じやすい最重要ポイントです。具体的には、「調整国外所得金額」は単純な国外所得の金額ではなく、いくつかの重要な調整を経て算出されます。
まず、「国外源泉所得」の範囲を特定します。法人税法では、国外支店の事業所得、国外にある資産の運用・保有・譲渡による所得、国外での人的役務の提供による所得などが国外源泉所得として定められています。
次に、この国外源泉所得金額から、外国では非課税とされる国外源泉所得(例えば、租税条約や現地の優遇税制により免税となる配当金など)の額を控除します 。これは、そもそも外国で税金が発生していない所得を限度額計算の基礎に含めることで、不当に控除枠を拡大させることを防ぐための調整です。
そして、最も重要な調整が「90%シーリング(上限)ルール」です。調整後の国外所得金額は、いかなる場合も全世界所得金額の90%を超えることはできません。もし計算上の国外所得金額が全世界所得金額の90%を超過した場合は、全世界所得金額の90%の金額に切り下げられます。
この90%シーリングは、極めて重要な租税回避防止規定です。例えば、外国税率が高い国(A国:税率40%)での所得と、税率がゼロのタックスヘイブン国(B国)での所得が両方ある法人を想定します。もしシーリングがなければ、B国で多額の所得を稼ぐことで算式の分子(国外所得)を大きくし、控除限度額を不当に引き上げることが可能になります。その結果、「A国で支払った高税率の税金を使って、本来日本で課税されるべき国内所得に対する税金まで控除できてしまう」という問題が生じます。90%シーリングは、このような国外の低税率所得を利用した過大な控除枠の創設を防ぎ、国内税源の浸食を防止する役割を果たしています。
ステップ2:設例で学ぶ、外国税額控除の限度額計算
ここまでのステップで理解した計算要素を使い、具体的な設例で控除限度額を計算してみましょう。
【設例】 日本の内国法人であるA社の当期の税務データは以下の通りとします。
- 全世界所得金額:1億円
- 国外源泉所得金額:4,000万円(全額が源泉地国で課税対象)
- 当期の法人税額(外国税額控除前):2,500万円
- 当期に納付した外国法人税額:1,200万円
【計算プロセス】
- 各計算要素の特定
- その事業年度の法人税額:2,500万円
- 全世界所得金額:1億円
- 国外源泉所得金額:4,000万円
- 調整国外所得金額の計算
- まず、非課税の国外源泉所得がないか確認します。本設例では、4,000万円全額が課税対象のため、この段階での控除はありません。
- 次に、90%シーリングを判定します。全世界所得金額(1億円)の90%は9,000万円です。国外源泉所得金額(4,000万円)は9,000万円以下であるため、シーリングは適用されません。
- したがって、「調整国外所得金額」は4,000万円となります。
- 控除限度額の計算
- 基本算式に各要素を当てはめます。
【計算結果】 この設例におけるA社の当期の外国税額控除の「控除限度額」は1,000万円となります。これは、A社が当期に日本の法人税から控除できる外国法人税額の上限が1,000万円であることを意味します。
ステップ3:控除額の決定と繰越制度の活用
従い、当期に控除できる外国税額控除の額は以下のいずれか少ない方の金額となります。
- その事業年度に納付した控除対象外国法人税の額
- ステップ2で計算した控除限度額
ステップ2の設例では、納付した外国法人税額は1,200万円、控除限度額は1,000万円でした。したがって、A社が当期に控除できる金額は控除限度額である1,000万円までとなります。
上記のように控除限度額が計算できたら、最終的に当期に控除できる金額を決定し、控除しきれなかった金額(上の設例では200万円が控除しきれなかった部分)や、逆に控除枠に余りが生じた場合の処理を理解する必要があります。
控除限度額を超えた場合:控除限度超過額の繰越
設例では、実際に納付した1,200万円のうち1,000万円しか控除できませんでした。この控除しきれなかった200万円(1,200万円 – 1,000万円)は「控除限度超過額」と呼ばれます。この超過額は切り捨てられるわけではなく、翌事業年度以降3年間にわたって繰り越すことが可能です 。そして、繰り越された先の事業年度で控除枠に余裕(控除余裕額)が生じた場合に、その余裕額の範囲内で控除することができます。
控除限度額に満たない場合:控除余裕額の繰越
設例のケースとは逆に、納付した外国法人税額が控除限度額よりも少ないケースもあります。例えば、設例で納付した外国法人税額が800万円だったとします。この場合、控除限度額1,000万円に対して200万円の余裕があり、この余裕分を「控除余裕額」と呼びますが、こちらについても控除限度超過額と同様に3年間の繰越が可能です(繰越控除余裕額)。尚、地方法人税について繰り越しが出来ない点は控除限度超過額と同様になります。
地方税への影響
外国税額控除は、国税である法人税だけの話ではありません。地方税である法人住民税(道府県民税・市町村民税)および地方法人税にも同様の控除制度が存在します。これらの地方税の控除限度額は、法人税の控除限度額を基にして以下の算式で計算されます(最新の標準税率の場合)。
- 地方法人税の控除限度額 = 法人税の控除限度額 × 10.3%
- 道府県民税の控除限度額 = 法人税の控除限度額 × 1.0%
- 市町村民税の控除限度額 = 法人税の控除限度額 × 6.0%
法人税で控除しきれなかった外国法人税額は、まず地方法人税から、次に道府県民税、市町村民税の順で、それぞれの控除限度額の範囲内で控除されていきます。この点も申告実務では忘れてはならない重要なポイントです。
外国税額控除の適用に必要な申告手続
外国税額控除は自動的に適用されるものではなく、法人が確定申告書でその適用を主張して初めて認められます。適用を受けるためには、法人税の確定申告書に加えて、以下の書類を添付または保存する必要があります。
- 外国税額の控除に関する明細書(法人税申告書 別表六(二)):控除額の計算過程を詳細に記載する中心的な書類です。
- 外国法人税額を課されたことを証明する書類:現地の申告書の写しや納税証明書、源泉徴収票など、外国法人税の存在と金額を証明する公式な書類です。
- 国外源泉所得の計算に関する明細書:国外所得の内訳や計算根拠を明らかにする書類です。
- 繰越控除に関する書類:前年度以前から繰り越された控除限度超過額や控除余裕額がある場合に、その金額を証明する書類です。
これらの書類を正確に作成・準備し、法人税の申告期限までに提出することが求められます。特に外国の書類については、税務調査等に備え、内容を日本語で説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。なお、各種申告様式については国税庁のウェブサイトで最新のものを確認することが重要です。
まとめ
外国税額控除は、グローバルに事業を展開する企業にとって国際的な二重課税を排除し、税務コストを適正化するために不可欠な制度です。しかし、その適用は、本稿で詳述した通り、専門的で複雑な計算を伴います。
特に、控除限度額の計算における「調整国外所得金額」の概念と、それに付随する「90%シーリング」ルールは外国税額控除制度における重要ポイントの一つであり、正確な理解が不可欠です。また、3年間の繰越制度を戦略的に活用することで、複数年度にわたる税負担の最適化を図ることが可能となります。
特に、複数の国で事業を展開している場合、租税条約の解釈が絡む場合、あるいは組織再編が関わる場合など、個別の状況はさらに複雑化します。計算の誤りは、追徴課税や加算税のリスクに直結しますので、自社での対応に少しでも不安がある場合は、国際税務に精通した税理士などの専門家に相談し、万全の体制で申告に臨むことを推奨いたします。本記事が少しでもお役に立てれれば幸いです。