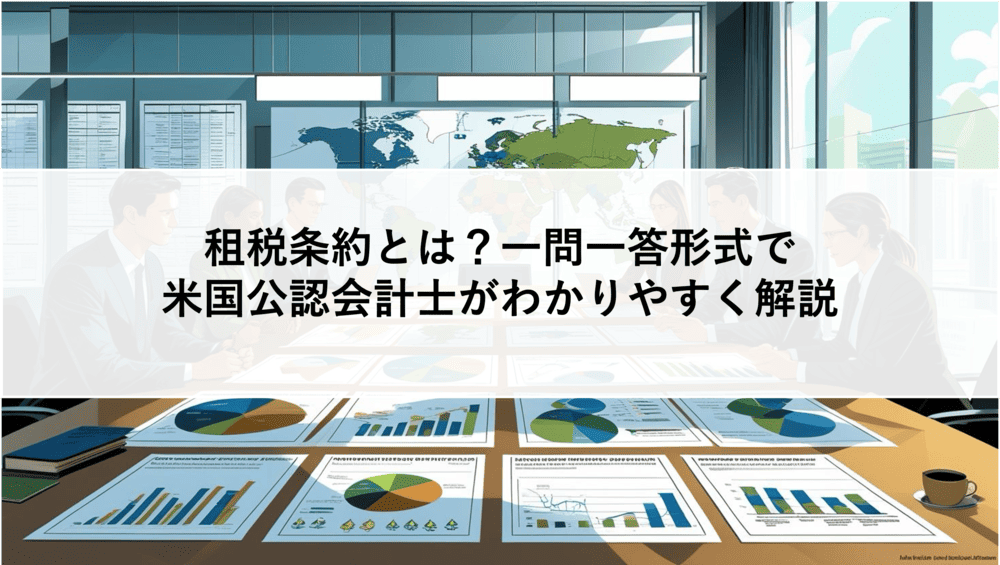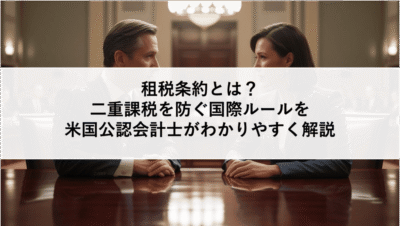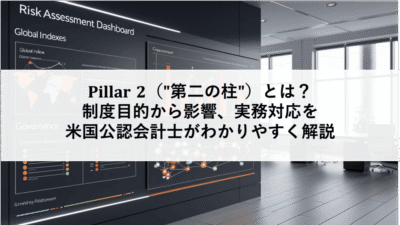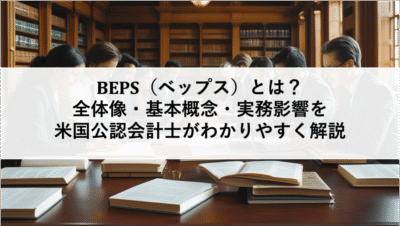租税条約の一問一答|国際税務の「なぜ?」に専門家が答えます
海外との取引や海外進出が当たり前になった現代において、「租税条約」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。しかし、言葉は知っていても、その中身は複雑で分かりにくいと感じる方が多いのも事実です。この記事では、米国を中心に国際税務の実務に携わってきた会計士の視点から、租税条約に関する初歩的かつ重要な疑問について、一問一答形式で分かりやすく解説していきます。一つひとつの疑問を解消していくことで、国際ビジネスを守るための重要なルールや租税条約の全体像が自ずと見えてくるはずです。
Q1. そもそも「租税条約」とは何ですか?
A1. 国と国との間で結ばれる「税金に関する特別な約束事」です。
租税条約とは、二国間で締結される税金に関する条約です。その主たる目的は、国際的な二重課税を排除すること、そして脱税や租税回避行為を防止することにあります。通常、国内の税金はその国の法律(日本では法人税法や所得税法など)に基づいて課されます。しかし取引が国境を越えると、一つの所得に対して複数の国が課税権を主張し、二重に税金がかかってしまう「国際的な二重課税」という問題が発生します。
このような問題を解決し、個人や企業の国際的な活動を円滑にするために、国内の税法に優先して適用される特別なルールを定めたものが租税条約です。2025年7月現在、日本は多くの国・地域と租税条約を締結しており、そのネットワークは世界の主要国を網羅しています。
Q2. なぜ「二重課税」が起きてしまうのですか?
A2. 各国が持つ二つの課税ルール、「居住地国課税」と「源泉地国課税」が衝突するためです。
国際的な二重課税が発生する背景には、各国が持つ二つの基本的な課税権の考え方があります。
一つは「居住地国課税」です。これは、個人であればその人の住所がある国、法人であれば本店や主たる事務所がある国が、課税権を持つという考え方です。この居住地国は、納税者が世界中で得た所得(全世界所得)に対して課税するのが一般的であり、これを「全世界所得課税」と呼びます。例えば日本の居住者や法人はこの原則に基づき、海外で稼いだ所得も日本で申告する義務があります。
もう一つは「源泉地国課税」です。これは、所得が発生した国(源泉地国)が、その所得に対して課税するという考え方です。例えば、日本の企業がアメリカの企業に技術指導を行い、その対価(ロイヤルティ)を受け取った場合、所得の源泉であるアメリカが課税権を主張します。
この二つの課税権が同時に行使されると、日本の企業は同じロイヤルティ所得に対して、アメリカで源泉徴収され、さらに日本でも法人税を課されるという二重課税の状態に陥ります。租税条約は、このような事態を避けるために、どちらの国が、どの所得に対して、どの範囲まで課税できるのかを調整する役割を担っています。
Q3. 租税条約は、具体的にどうやって二重課税を防ぐのですか?
A3. 主に「課税権の配分」と「税率の軽減」という二つの方法で解決します。
租税条約は、二重課税を解決するために所得の種類に応じて精緻なルールを定めています。その仕組みは大きく二つに分けられます。
一つ目は「課税権の配分」です。特に事業から得られる利益(事業所得)については、「恒久的施設(PE)」という概念を用いて課税権を配分します。これは「PEなければ課税なし」という国際課税の大原則で、「外国企業が進出先の国に支店や工場といった恒久的な拠点(PE)を持たない限り、その国はその企業の事業所得に対して課税できない」というルールです。これにより、海外での一時的な活動や市場調査などでは、現地の税金が発生しないことが保証されます。
二つ目は、配当・利子・使用料といった「投資所得」に対する「源泉地国での税率の制限」です。これらの所得はPEがなくても所得の発生した国で課税されますが、租税条約によってその国が課せる税率の上限(限度税率)が定められています。例えば、日本の国内法では非居住者への配当に対する源泉税率は20.42%ですが、相手国との租税条約によっては、これが10%、5%、あるいは免税にまで引き下げられます。
それでもなお二重課税が残る場合には、居住地国側で「外国税額控除」という制度を適用し、外国で支払った税金を自国で納める税金から差し引くことで、最終的な調整が行われます。
Q4. 租税条約のメリットを受けるには、どうすればよいですか?
A4. 原則として、事前に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
租税条約による税率の軽減や免除といった恩恵は、自動的に受けられるわけではありません。
これらの特典を受けるためには、所得を支払う者(例えば、日本の会社が海外の取引先にロイヤルティを支払う場合)を通じて、その支払が行われる日の前日までに所轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出するのが原則的な手続きです。
この届出書を提出することで、所得の支払者は租税条約で定められた軽減税率で源泉徴収を行うことができます。もし届出書の提出が間に合わず、国内法の高い税率で源泉徴収されてしまった場合には、後日「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を提出することで払い過ぎた税金の還付を受けることも可能です。
この届出は、海外から所得を受け取る個人にとっても同様に重要です。例えば、海外勤務から日本に帰国した駐在員が退職時に海外の企業年金を受け取るようなケースでは、この届出を行うことで現地での過大な源泉徴収を免れることができる場合があります。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
Q5. 租税条約があれば、誰でもメリットを受けられますか?
A5. いいえ、条約の恩恵を受ける資格がない「条約の濫用」と見なされる場合は適用が否認されます。
租税条約は、二国間の健全な投資交流を促進するためのものですが、この仕組みを悪用して税金を不当に免れようとする「条約漁り(トリーティショッピング)」という行為が存在します。
例えば、本来は租税条約の恩恵を受けられない第三国の居住者が、税率の低い国(例えば、日本との間で配当への課税が免除される条約を結んでいる国)にペーパーカンパニーを設立し、その会社を経由して日本から配当を受け取ることで、本来課されるべきであった日本の税金を逃れるようなケースです。
このような条約の濫用を防ぐため、多くの租税条約(特に先進国との条約)には「特典条項(Limitation on Benefits, LOB条項)」という厳しいフィルターが設けられています。この条項は、条約の相手国に設立された法人であってもその法人の株主構成や事業の実態などを細かくチェックし、「適格な居住者」でないと判断した場合には租税条約の特典を与えないとするものです。
したがって、「相手国に会社があるから」という理由だけで租税条約が使えるわけではなく、その会社が条約の特典を受けるにふさわしい経済実態を有するかどうかが問われる、という点を理解しておく必要があります。
Q6. 租税条約のルールは、一度決まったら変わらない?
A6. いいえ、経済のグローバル化に対応するため、常にアップデートされています。
かつては数十年単位で改定されるのが普通だった租税条約ですが、近年その改正のスピードは劇的に上がっています。その大きなきっかけとなったのが、OECD/G20が主導した「BEPSプロジェクト」です。
これは、多国籍企業による国際的な租税回避行為に対抗するための世界的な取り組みであり、その成果として多くの租税条約の規定がアップデートされました。特に、PE認定の基準が厳格化されたり、条約の濫用を防止するための包括的なルールが導入されたりしています。この改正を効率的に進めるため、「BEPS防止措置実施条約(MLI)」という画期的な多国間条約が作られました。これにより、世界中の膨大な数の二国間租税条約があたかもOSのアップデートのように一括で上書き修正されています。従い、国際ビジネスを行う上では、締結されている条約の原文だけでなく、このMLIによってどの条項がどのように変更されたかまで確認しないと、思わぬところで判断を誤る可能性があります。
まとめ:租税条約はグローバルビジネスの「羅針盤」
ここまで、租税条約に関するよくあるご質問にお答えしてきました。租税条約は単なる税金の割引ルールではありません。国際的な二重課税という荒波から企業を守り、国家間の公平な課税を実現し、そしてグローバル経済の健全な発展を支えるための極めて重要な「羅針盤」だと言えます。その内容はたしかに専門的で複雑ですが、基本的な目的と仕組みを理解しておくだけで、海外取引における税務リスクに対する感度は格段に高まります。
国際税務のルールは国ごとに異なり、また常に変化しています。具体的な取引に際して判断に迷うことがあれば、自己判断で進めてしまう前に、必ず国際税務に精通した専門家に相談することをお勧めします。国際税務総合研究所では、このような国際税務に関する皆様の疑問にお答えするため、無料・匿名で相談できる窓口「みんなの国際税務Q&A」を設けております。個別の税理士に相談する前の第一歩として、ぜひご活用ください。