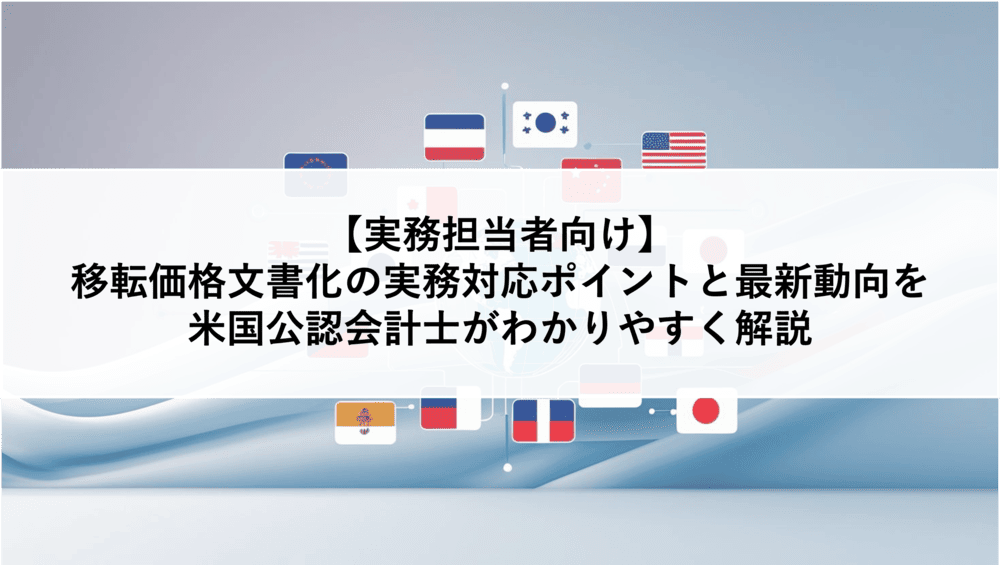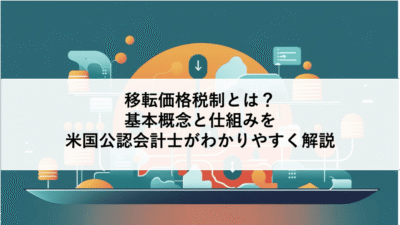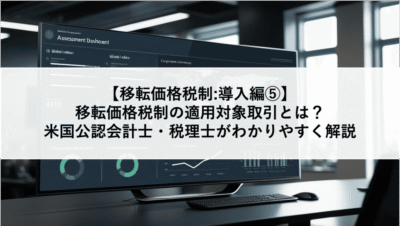「移転価格文書化」と聞くと、『うちのような規模の会社にはまだ早い』『法律で定められた義務の基準額に達していないから大丈夫』と考える方も少なくないのではないでしょうか。もしそうであれば、その認識は将来の経営に大きなリスクをもたらす可能性があるといえます。移転価格文書化はもはや一部の大企業だけのものではありません。海外に子会社や関連会社を持つすべての企業にとって、税務調査に対する不可欠な「防御策」であり、グローバルな事業運営の根幹を支える「経営管理ツール」となり得ます。
この記事では、国際税務を専門とする米国公認会計士の立場から、移転価格文書化の基本である「3つの文書」の役割から、具体的な作成ステップ、さらにはBEPS2.0といった国際課税の最新動向が実務に与える影響まで、体系的かつ分かりやすく解説していきます。
そもそも移転価格文書とは?なぜ今、重要性が増しているのか
移転価格文書とは、一言で言えば「国外の関連会社との取引価格が独立した第三者間で行われる価格(独立企業間価格)に基づいて決定されていることを、客観的な証拠をもって説明するための文書」のことです。この制度は、国際的なルールに基づいて設計されており、その重要性は年々高まっています。
BEPSプロジェクトが生んだ「3つの文書」
現在の移転価格文書化制度は、経済協力開発機構(OECD)が主導した「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクト」の勧告に基づき、世界共通の枠組みとして整備されました。これにより、多国籍企業グループは国際的に整合性のとれた以下の3種類の文書を作成することが求められるようになりました。
- 国別報告書(Country-by-Country Report / CbCレポート)
- マスターファイル(Master File / 事業概況報告事項)
- ローカルファイル(Local File / Transfer Pricing Report)
これら3つの文書は、それぞれ異なる視点から多国籍企業グループの活動を明らかにし、税務当局が移転価格リスクを評価するための情報を提供する役割を担っています。
文書化の目的:税務調査への「防御」と「説明責任」
移転価格文書を作成する最大の目的は、税務調査の際に自社の国外関連取引の価格設定が経済的に合理的であることを、税務当局に対して明確に説明し、立証することにあります。
移転価格調査では、調査官は企業の価格設定ポリシーの合理性を徹底的に検証します。その際、説得力のある文書が準備されていなければ、企業の主張は単なる「言い分」としか受け取られません。逆に、論理的に構築された文書があれば、それは調査官との対話の土台となり、無用な誤解や一方的な課税を避けるための強力な防御ツールとなるのです。文書化は単なるコンプライアンス上の作業ではなく、自社の正当性を主張し、予期せぬ追徴課税リスクから経営を守るための極めて重要な戦略的活動とも言えます。
3種類の移転価格文書:それぞれの役割と作成・提出義務
それでは、3つの文書それぞれについて、どのような企業に作成・提出義務があり、どのような内容を記載するのか、具体的に見ていきましょう。
① 国別報告書(CbCレポート):グループ全体の透明性を確保
国別報告書は、多国籍企業グループがどの国・地域でどれだけの経済活動を行い、どれだけの税金を納めているかを一覧にしたものです。税務当局がグループ全体の利益配分と納税状況を俯瞰し、移転価格リスクの高い領域を大局的に把握するために利用されます。
- 提供義務者:直前の会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループに属する日本の法人が対象です。
- 主な記載内容:国・地域ごとの収入金額、税引前利益、納付税額、従業員数、有形資産の額などです。
- 提供期限・方法:最終親会社の会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxを通じて英語で提供する必要があります。
② マスターファイル(事業概況報告事項):グループの事業概要を俯瞰する
マスターファイルは、多国籍企業グループ全体の事業内容、組織構造、無形資産の管理方針、金融活動、財務・納税状況などを文章で説明する文書です。ローカルファイルで示される個別の取引価格の妥当性を、グループ全体の事業戦略という大きな文脈の中で理解するために用いられます。
- 提供義務者:国別報告書と同様、直前の会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループに属する日本の法人が対象です。
- 主な記載内容:グループの組織図、事業の概況、無形資産に関する戦略、グループ内金融活動の方針、連結財務諸表などです。
- 提供期限・方法:最終親会社の会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxを通じて日本語または英語で提供します。通常、グループ内の1社が代表して提出します。
③ ローカルファイル:個別の国外関連取引を詳細に立証する
ローカルファイルは、日本の法人が行った個別の国外関連取引について、その価格が独立企業間価格であることを具体的に証明するための最も重要な文書です。多くの中堅・中小企業にとって、移転価格文書化対応とは、実質的にこのローカルファイルの作成を指します。
- 作成・保存義務者:①前事業年度における国外関連取引の合計金額が50億円以上の法人、または②前事業年度における無形資産取引の合計金額が3億円以上の法人、のいずれかに該当する法人は、いわゆる「同時文書化義務」として確定申告書の提出期限までに書類を作成・保存しなければなりません:
- 主な記載内容:自社と取引相手の概要、国外関連取引の詳細、取引当事者が果たす機能や負担するリスク(機能・リスク分析)、市場分析、そして最も重要な「独立企業間価格の算定方法とその結果」などが含まれます 。
ここで、最も注意すべき「罠」があります。それは「同時文書化義務」の基準です。金額基準だけを見て、『うちは取引額が小さいからローカルファイルは不要だ』と判断するのは極めて危険です。なぜなら、この基準はあくまで「確定申告期限までに作成する義務」を定めたものに過ぎず、移転価格税制そのものの適用が免除されるわけではないからです。
具体的には、国税庁のサイトには以下のような記載があります。
同時文書化義務が免除された取引(以下「同時文書化免除取引」といいます。)であっても、移転価格税制の対象となりますので、税務調査時に書類の提示又は提出を求めることがあります。
つまり、上記の金額基準に満たない企業であっても、税務調査の際に調査官はローカルファイルに相当する書類の提出を求めることができます。その要求に対し、指定された期限内(通常60日以内)に合理的な文書を提出できなければ、税務当局は同業他社の利益率など、税務当局が収集した情報に基づいて課税所得を計算する「推定課税」を行うことが可能になります。一般に、推定課税は納税者にとって不利な結果を招く可能性が高く、これを避けるためにも、取引規模にかかわらずローカルファイルを準備しておくことが最善の策といえます。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
ローカルファイル作成の実務ポイント
では、実際にローカルファイルを作成するには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは、専門家でなくとも理解しておくべき基本的な流れを解説します。
ステップ1:自社の国外関連取引を特定する
まず、自社と国外関連者との間で行われている取引をすべてリストアップします。製品や部品の売買といった棚卸資産取引だけでなく、経営指導や業務代行などのグループ内役務提供(IGS)、親子間の資金貸付(親子ローン)、ブランドや特許の使用許諾(ロイヤルティ)など、あらゆる取引が対象です。
ステップ2:機能・リスク分析を行う
次に、洗い出した取引ごとに関連当事者(日本の親会社と海外子会社など)が、各々の取引においてどのような「機能」を果たし、どの程度の「リスク」を負担しているかを分析します。これを「機能・リスク分析」と呼びます。
例えば、製品開発、製造、マーケティング、販売、在庫管理、品質保証といった機能はどちらが担っているか。また、開発失敗のリスク、在庫陳腐化のリスク、売掛金の回収不能リスクなどはどちらが負っているか、といった点を整理します。この分析は、後の価格算定方法の選定において最も重要な基礎となります。
ステップ3:最適な独立企業間価格算定方法を選定する
機能・リスク分析の結果を踏まえ、国外関連取引の価格の妥当性を検証するための最も適切な「独立企業間価格算定方法」を選定します。日本の税法では、OECDガイドラインに準拠した複数の算定方法が認められています。
例えば、海外子会社が単純な販売機能のみを担っている場合は「再販売価格基準法」が、限定的な製造機能のみを担っている場合は「原価基準法」が、より複雑な機能や無形資産が絡む場合は「取引単位営業利益法(TNMM)」や「利益分割法」が候補となります。なお、各手法の具体的な算定方法や適用判断には高度な専門知識が求められるため、本記事では詳細な解説は割愛し、別記事にて個別に取り上げる予定です。
ステップ4:比較対象企業・取引を探し、価格を算定・検証する
選定した算定方法に基づき、独立企業間価格レンジ(比較可能な独立企業群の利益率のレンジなど)を算定します。具体的には、企業データベースを用いて、自社の取引と事業内容、機能、市場などが類似した「比較対象企業」を複数選定し、その財務データを分析する作業が必要になります。最終的には、自社の国外関連取引から得られる利益率がこの算定されたレンジ内に収まっていることを検証します。
ステップ5:すべてのプロセスを文書として記録・保存する
ステップ1から4までの全プロセス、つまり、どのような取引を対象とし、どのような機能・リスク分析を行い、なぜその算定方法を選び、どのように比較対象企業を選定して価格を検証したのか、その一連の論理的な流れを一つの文書にまとめ上げます。実務上、対象取引に係る契約書や価格決定プロセスを記録した議事録なども重要な補足資料となります。
移転価格文書化の最新動向と注意点
移転価格を取り巻く環境は、常に変化しています。ここでは、企業が特に注意すべき最新の動向を2つ紹介します。
BEPS2.0「グローバルミニマム課税」がもたらす新たな緊張
近年、国際課税の最大のトピックは「BEPS2.0」です 。特にその「第2の柱」であるグローバルミニマム課税は、各国の法人税率が15%に満たない場合に、その差額を親会社等の所在国で課税するという画期的なルールです。
これにより、従来のように極端な低税率国へ利益を移転させることによる節税効果は薄れます。しかし、これが移転価格リスクの低下を意味するわけではありません。むしろ、新たな緊張関係を生んでいます。
それは、各国の税務当局による「税源争奪」の激化です 。自国の税収を確保するため、グローバルミニマム課税が適用される前に、移転価格調査を強化して「まず自国で課税する」というインセンティブが働く可能性があります。企業は、これまで以上に厳格な目で国外関連取引の価格設定を検証されることを覚悟しなければなりません。
税務調査の厳格化と指摘事項の変化
国税当局は国際課税を重点課題と位置づけ、調査体制を強化しています。調査対象も大企業だけでなく、中堅・中小企業へとすそ野が広がっているのが実情です。特に、以下のような取引は指摘を受けやすい典型的な論点です。
- 実体の乏しい経営指導料:契約書や具体的な成果物(報告書など)がなく、対価の算定根拠が不明確な経営指導料は、寄附金と認定されるリスクがあります。
- 不適切な親子ローン金利:無利息や市場金利から乖離した低利での貸付は、利息相当額の利益移転とみなされます。
- 無償の役務提供:親会社による無償の技術支援や業務代行は、対価の取り漏れとして指摘の対象となります。
まとめ
移転価格文書化への対応は、決して単なるコストや手間のかかる作業ではありません。それは、予期せぬ巨額の追徴課税リスクから会社を守るための、不可欠な経営投資です。移転価格文書を作成するプロセスは、自社のグループ内取引の価格設定ポリシーを客観的に見つめ直し、体系化する絶好の機会ともいえます。
もしこの記事を読んで「うちの対応は大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じたなら、それはまさに今、見直しを始める良いきっかけかもしれません。問題が表面化する前に、まずは国際税務に詳しい専門家に相談し、自社の状況を冷静に確認してみることをおすすめします。国際税務総合研究所では、このような国際税務に関する皆様の疑問にお答えするため、無料・匿名で相談できる窓口「みんなの国際税務Q&A」を設けております。個別の税理士に相談する前の第一歩として、またセカンドオピニオンとしても、ぜひご活用ください。