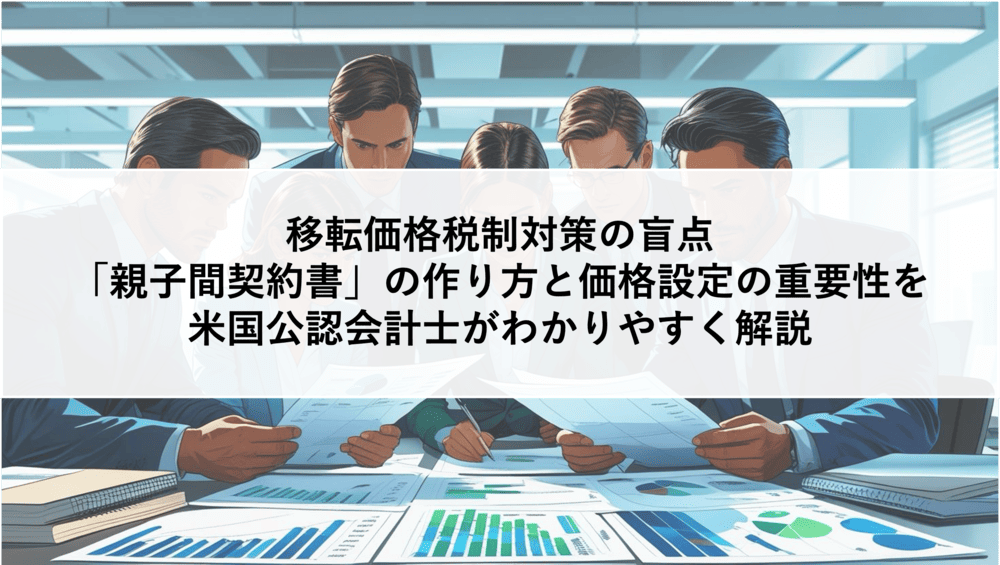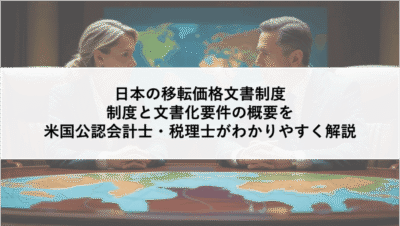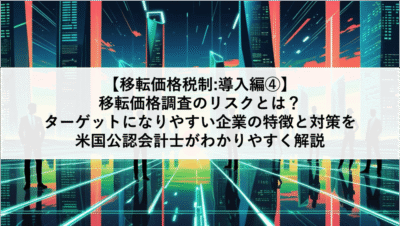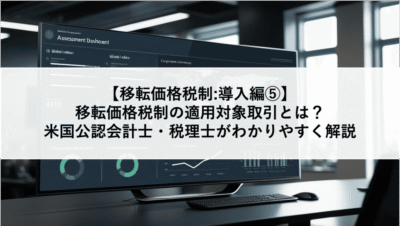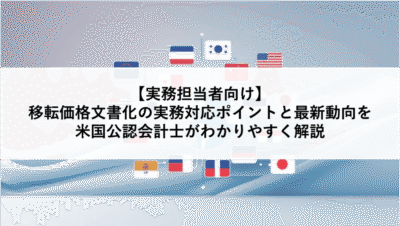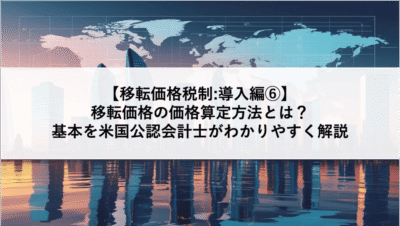海外子会社との取引において、「グループ内の取引なのだから、細かい契約書は用意しなくても大丈夫」「口約束やメールでのやり取りで十分だろう」と考えてはいないでしょうか。もしそうであれば、その認識は移転価格税制の観点から非常に危険な状態にあると言わざるを得ません。移転価格調査において、税務当局がまず確認するのは「取引の事実」を客観的に証明する契約書の存在です。契約書がない、あるいは内容が実態と乖離している場合、企業の主張は単なる「言い分」としか見なされず、予期せぬ巨額の追徴課税につながる重大なリスクを抱えることになります。
本記事では、米国で国際税務の実務経験を積んだ米国公認会計士の立場から、なぜ親子間契約書が移転価格対策の「土台」となるのか、そして取引の種類ごとにどのような条項を盛り込み、いかに価格設定の根拠を示すべきか、その具体的な実務ポイントを体系的かつわかりやすく解説します。
なぜ「親子間契約書」が移転価格対策の第一歩なのか?
移転価格文書(ローカルファイル)の作成や事前確認(APA)の検討は移転価格税制の対応として非常に重要ですが、それらすべての大前提となるのが、個々の取引を規律する「契約書」の存在です。その重要性を理解することが、リスク管理の出発点となります。
税務調査における「契約書」の役割
一般に、移転価格調査が始まると調査官はまず、国外関連者との間でどのような取引が行われているのか、その全体像を把握しようとします。その際、最も基本的かつ重要な証拠となるのが、当事者間で締結された契約書です。もし契約書が存在しなければ、税務当局は企業の口頭での説明や断片的な資料から取引の実態を推測せざるを得ません。その結果、納税者にとって不利な事実認定が行われるリスクが格段に高まります。
「口約束」「暗黙の了解」が招く最悪のシナリオ
中小企業によく見られるのが、親子会社間の信頼関係を前提とし、正式な契約書を交わさずに取引を行っているケースです。特に、子会社への経営支援といった役務提供が無償で行われる場合、そのリスクはより高まります。例えば、親会社が海外子会社へ無償で製造技術に関する技術指導を行ったとします。契約書もなければ対価の請求もない場合、税務上、この行為は「経済的利益の無償の供与」とみなされ、「寄附金」として認定される可能性があります。国外の関連会社に対する寄附金は、税法上ほとんどが損金(税務上の経費)として認められませんので、こうした「寄附金」認定は思わぬ追徴課税(想定外のキャッシュアウト)を招く可能性があります。
さらに深刻なのは、寄附金認定された場合、国際的な二重課税を解消するための最終手段である「相互協議」の対象外となるのが一般的であるという点です 。つまり、日本で課税された上に、相手国での税金は外国税額控除等の適用ができず、二重の税負担が確定してしまうという、も回避すべき事態に陥るのです。善意で行った子会社支援が、契約書一つないために、取り返しのつかない結果を招くことがあるという点に注意が必要です。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
取引タイプ別:契約書に盛り込むべき条項と価格設定のポイント
では具体的にどのような契約書を準備し、何を記載すればよいのでしょうか。ここでは、日系企業の親子会社間で行われる典型的な4つの取引タイプについて、契約書に盛り込んでおくべき条項と価格設定における留意点を解説します。
① 棚卸資産取引(例:製品・部品等の売買)
日本の親会社が製造した製品を海外の販売子会社に販売する、といった取引は最も典型的です。契約書は、実際の取引内容と利益・リスクの分担が実態に一致していることを明らかにし、後から税務当局に説明できるようにしておくことが大切です。以下に契約書に盛り込むべき条項を記載します。
契約書に盛り込むべき条項
- 取引の対象となる製品:製品名、品番、仕様などを明確に特定します。
- 取引価格の条件:単価、数量割引の有無、価格改定のルールなどを定めます。
- 引渡条件:インコタームズ(FOB, CIFなど)を明記し、どの時点で費用負担やリスクが売り手から買い手に移るのかを明確にします。
- 支払条件:支払通貨、支払期日、支払方法(T/T送金など)を定めます。
- 所有権の移転時期:どの時点で製品の所有権が売り手から買い手に移るのかを明記します。
- 品質保証・瑕疵担保責任:製品に欠陥があった場合の責任分担を明確にします。
- 経済的リスクの分担:製造遅延、為替変動(どの通貨建で取引を行うか)、市場価格の変動などの経済リスクをどちらが負担するかを明記しておくことが好ましいです。
価格設定において重要なのは、親会社と子会社の取引価格が第三者同士であっても成立し得る水準(独立企業間価格)であることです。契約書に記載されているからといって、その価格が自動的に独立企業間価格と認められるわけではありませんが、上記に挙げたような取引条件が明確に定められていれば、その価格が合理的であることを説明する材料になります。したがって、価格の設定根拠と契約書に記載された内容との整合性を確保することが不可欠です。
② 役務提供(例:経営指導・技術支援・業務代行)
親会社が子会社に対して行う経営指導、経理・総務業務の代行、技術者の派遣といったサポート業務も、移転価格税制の対象となります。
契約書に盛り込むべき条項
- 役務の具体的な内容:どのようなサービスを提供するのか、可能な限り詳細かつ具体的に記述します。できる限り「経営指導」といった曖昧な表現ではなく、「月次での財務分析レポートの提供」「年4回の役員派遣による経営会議への参加」のように特定します。
- 対価の算定方法:対価をどのように計算するのか、その算定根拠を明確にします。例えば、「本役務提供に要した人件費及び諸経費の合計額に10%の利益を加算した金額(10%マークアップ)」といった原価基準(コストプラス)での算定方法が一般的です。
- 報告義務:提供した役務の内容を証明するため、定期的な業務報告書の提出を義務付ける条項を設けることも非常に有効です。
- 支払条件:請求・支払のタイミングを定めます。
価格設定に関する留意点として、役務提供に対する対価は客観的かつ合理的な根拠に基づいて算出する必要があります。対価が不当に高額であったり、無償で提供されていた場合には、税務調査において問題視される可能性が非常に高くなります。特に無償提供については、寄附金課税として否認されるリスクが大きいため、たとえ少額であっても適正な対価を受け取り、その証拠として契約書、請求書、入金記録をしっかりと残しておくことが極めて重要です。
③ 金融取引(例:親子ローン)
海外子会社の設立資金や運転資金を親会社が貸し付けるケースも、日系企業の親子会社間で見られる典型的な取引です。
契約書に盛り込むべき条項
- 貸付の元本金額:貸し付ける金額の元本を明記します。
- 利率:適用する金利を年率で明確に定めます。
- 返済方法と返済期間:元本と利息の返済スケジュールを具体的に定めます。返済期間については、貸し手側の状況や資金計画も踏まえ、一般的に妥当と考えられる期間内で設定することが望まれます。
- 遅延損害金:返済が遅れた場合のペナルティを定めます。
- 契約締結日:契約書には必ず日付を記載し、当事者双方が署名・捺印します。
親子間の貸付取引における金利は、市場金利を基準としつつ、子会社の信用状況や貸付期間などを踏まえて、客観的に妥当と認められる水準で設定する必要があります。「無利息」や市場水準とかけ離れた低金利での貸付は、実質的に利息分を無償で供与したものと見なされ、移転価格課税や寄附金課税の対象となるリスクが極めて高くなります。そのため、契約書を適切に整備し、契約内容に沿って利息の受け取りおよび元本の返済を確実に履行することが、贈与と見なされないための重要な前提となります。
④ 無形資産取引(例:ライセンス契約)
親会社が持つブランド、特許、製造ノウハウなどの無形資産を海外子会社が使用する場合には、その対価(ロイヤルティ)の支払いが必要になります。
契約書に盛り込むべき条項
- 対象となる無形資産の特定:ライセンスの対象となる特許番号、商標登録番号、ノウハウの範囲などを明確に特定します。
- ライセンスの範囲:使用を許諾する地域、期間、ライセンスは独占的か非独占的か、といった条件を定めます。
- ロイヤルティの算定方法:ロイヤルティをどのように計算するかを明記します(例:対象製品の売上高のX%)。
- 支払条件:支払時期や方法を定めます。
- 品質管理・ブランド保護:ブランド価値を毀損しないための子会社の義務などを定めます。
ロイヤルティ料率を設定する際は、ライセンスの対象となる無形資産の価値や親会社および子会社が担っている機能(開発、改良、維持、保護、活用など)を適切に分析した上で、合理的な水準に設定することが求められます。親会社が保有する重要な無形資産を子会社が対価を支払わずに利用している場合には、ロイヤルティの収受漏れとして税務当局から厳しく追及されるリスクがあります。
契約書と実態の一致がすべて ― 契約管理の重要ポイント
どれほど完璧な契約書を整備しても、それだけで移転価格リスクが完全に排除されるわけではありません。本当に重要なのは、契約内容と実際の事業活動がきちんと整合していることです。そこで、実務上必ず押さえておきたい重要なポイントを、以下の3つに整理しました。
1.「契約書は作っただけ」では意味がない
税務調査では、契約書の内容だけでなく、実際の業務がどのように行われているかが検証されます。例えば、契約書上は子会社が在庫リスクを負うことになっていても、実際には売れ残った製品をすべて親会社が引き取っているような事実があれば、契約書の記述は意味をなさず、「リスクを負担しているのは実質的に親会社である」と認定されます。契約は、実態を正しく反映したものでなければ、いざという時に会社を守る盾にはなりません。
2. 契約内容を社内に周知徹底する
移転価格ポリシーや親子間契約の内容は、法務・経理部門だけでなく、実際に取引価格を決定し、業務を執行する営業、製造、開発といった事業部門にも正しく理解され、遵守される必要があります。部門間の連携不足から契約内容と異なる運用がなされてしまうと、それが移転価格リスクの火種となります。
3. 定期的な見直しと更新の必要性
とはいえ、事業環境は常に変化しています。子会社の機能が拡大したり、新たな取引が始まったりすれば、契約書の内容もそれに応じて見直し・更新する必要があります。実際の移転価格の実務では、数十年前に締結された契約が、いかなる修正条項も交わされないまま放置され、現時点の取引実態と大きく乖離しているというケースが非常によく見受けられます。一度作成した契約書を何年も見直さずに放置することは、こうしたリスクを高める要因となりますので、契約書台帳を整備し、内容を定期的に確認・更新する運用体制を整えることが極めて重要です。
まとめ
海外子会社との取引における親子間契約書は、単なる形式的な書類ではありません。それは、移転価格という複雑な税務リスクに対応するための、すべての基礎となる「設計図」となり得ます。移転価格対策というと、専門家による高度な分析や文書化をイメージしがちですが、その第一歩は、自社の足元にある親子間の取引関係を契約書という形で明確に整理することから始まります。これは、比較的低コストで着手できる、最も費用対効果の高いリスク管理策の一つです。
もし本記事を読んで、自社の契約管理体制に少しでも不安を感じたならば、まずは海外子会社との間でどのような契約書が交わされているかを確認し、その契約内容が取引の実態と合っているかを見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。その地道な作業が、将来の予期せぬ税務リスクから会社を守る最も確実な一歩となるはずです。