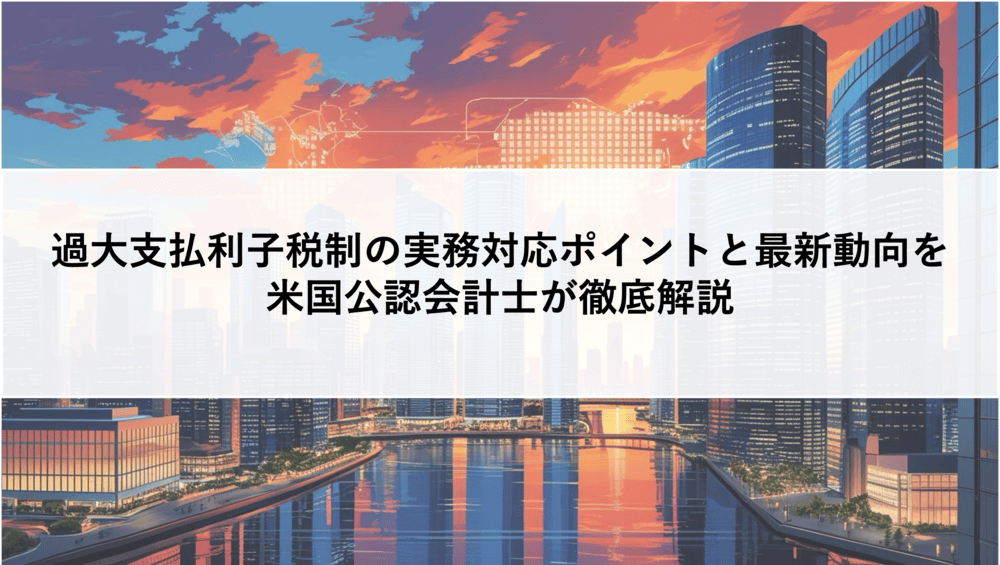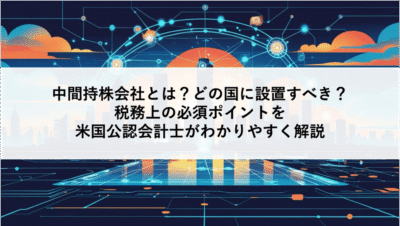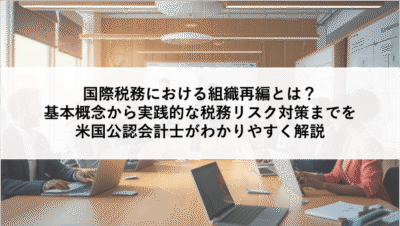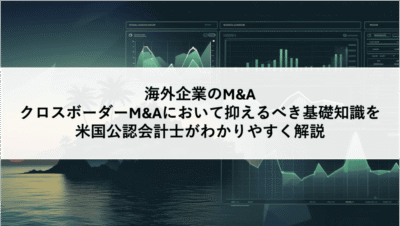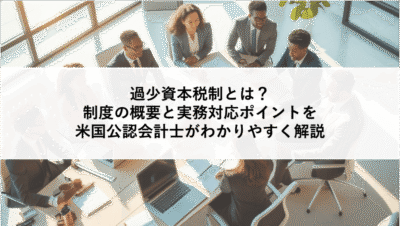海外親会社からの借入や国外関連会社への資金貸付は、グローバル企業にとって日常的な資金調達・運用の手段です。しかし、その際に発生する「支払利子」が、日本の税務上、予期せず損金として認められないケースがあることをご存知でしょうか。本記事では、国際税務における重要な租税回避防止ルールである「過大支払利子税制」に焦点を当て、制度の基本から具体的な計算方法、適用が免除されるケース、そしてもう一つの利子制限ルールである「過少資本税制」との関係性まで、実務担当者が押さえるべきポイントを最新の国際課税動向を交えながらわかりやすく解説します。
過大支払利子税制とは?制度の目的と概要
まず、過大支払利子税制がどのような制度であり、なぜ導入されたのか、その基本的な枠組みを理解することから始めましょう。
なぜ支払利子が制限されるのか?制度の趣旨
法人税の計算上、支払利子は原則として損金に算入されます。この仕組みを利用し、多国籍企業グループが税率の高い国にある子会社に過大な借入れをさせて多額の支払利子を計上させ、利益を意図的に圧縮する、という租税回避(タックスプランニング)が国際的に問題視されてきました。このような、利子の損金算入を利用した課税ベースの浸食(Base Erosion)を防ぐ目的で導入されたのが、過大支払利子税制です。
この制度を端的に言えば、「企業の所得(稼ぐ力)に比べて支払利子の額が過大である場合に、その超過部分の損金算入を認めない」というものです。
過大支払利子税制の核心は、非常にシンプルなルールに基づいています。法人の各事業年度において、その年度の「対象純支払利子等の額」が「調整所得金額」の20%を超える場合、その超える部分の金額は損金の額に算入されません。
これを計算式で示すと以下のようになります。
損金不算入額 = 対象純支払利子等の額 - (調整所得金額 × 20%)
この計算式の各項目が具体的に何を指すのかは、後述の「【実務の最重要ポイント】計算要素の具体的な定義」にて詳しく解説しますね。
BEPSプロジェクトによる改正の経緯(旧制度との比較)
現在の過大支払利子税制は、2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用されているもので、それ以前の制度から大幅に内容が変更されています。この改正はOECD(経済協力開発機構)が主導した、国際的な租税回避を防止するための「BEPSプロジェクト」の勧告内容を国内法に取り入れたものです。
実務上、特に重要な変更点は以下の2点です。
- 対象範囲の拡大:旧制度では国外の関連会社への支払利子のみが対象でしたが、改正後は、関連者以外への支払利子、すなわち第三者への支払利子も含む全ての支払利子が原則として対象となりました。
- 損金算入限度額の引き下げ:損金算入が認められる所得に対する利子の割合が、調整所得金額の50%から20%へと大幅に引き下げられました。
この改正により本制度が適用される可能性のある企業が大きく広がり、より多くの企業にとって注意すべき税制となっています。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
【実務の最重要ポイント】計算要素の具体的な定義
損金不算入額を正しく計算するためには、計算式を構成する各要素の定義を正確に理解することが不可欠です。特に「対象純支払利子等の額」と「調整所得金額」の計算は、実務上の最重要ポイントとなります。
① 対象純支払利子等の額
「対象純支払利子等の額」とは、その事業年度における「対象支払利子等の額」の合計から、「控除対象受取利子等の額」の合計を差し引いた金額を指します。
「対象支払利子等の額」とは:この制度でいう「支払利子等」は、単なる借入金の利子に限りません。租税特別措置法では、負債の利子に加え、手形の割引料や一定のリース取引における利息相当額、さらには「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」まで広く含まれると規定されています 。例えば、資金調達と経済的に密接な関係にある金利スワップ取引によって支払う金利なども、この「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」に該当する可能性があります。会計上の科目名だけで判断するのではなく、取引の経済的実質で判断する必要がある点に注意が必要です。
一方で、支払利子等であっても、その利子を受け取る側(相手先)において日本の法人税や所得税の課税対象となるものは本制度の対象から除かれます。これは、利子の受領者側で適切に課税されているのであれば課税ベースの浸食は生じないという考え方に基づいています。
「控除対象受取利子等の額」とは: 支払利子だけでなく、法人が受け取る利子等も考慮されます。ただし、その法人で発生した受取利子等の全額が控除できるわけではなく、その法人で発生した全体の支払利子等に占める対象支払利子等の割合に応じて按分計算された金額のみが控除対象となります。
② 調整所得金額
「調整所得金額」は、支払利子の負担能力を測るための指標であり、大まかにはEBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)に近い概念です。計算方法は、その事業年度の所得金額(税務上の課税所得)をベースに、以下の主要な項目を加算して算出します。
調整所得金額 = 税務上の課税所得 + 対象純支払利子等の額 + 損金算入された減価償却費の合計額 ±(その他一定の調整)
実務の観点で極めて重要なのが、受取配当等の益金不算入額や外国子会社配当等の益金不算入額は、調整所得金額の計算上の加算対象とならないという点です。従い、配当金を多く受け取っている企業の場合は調整所得金額が旧制度に比べて小さく計算されるため、結果として損金算入限度額(調整所得金額 × 20%)が低くなり、本制度の適用を受ける可能性が高まります。
なお、計算した調整所得金額がマイナスになる場合は、ゼロとして扱われ、この場合は「対象純支払利子等の額」の全額が損金不算入となります。感覚的には「調整所得金額がない、つまりビジネスとして赤字に近い状態で借金してる会社がさらに節税できるのはおかしいので、利子の損金算入は全額認めないよ」というイメージを持っていただければ良いかと思います。
適用が免除されるケース(適用除外基準)
前段では計算過程について具体的に解説しましたが、実は全ての法人にこの複雑な計算が求められるわけではなく、事務負担の軽減などの観点から以下のいずれかの基準を満たす場合には過大支払利子税制の適用が免除されます。
基準1:対象純支払利子等の額が2,000万円以下
その事業年度における「対象純支払利子等の額」が2,000万円以下である場合には、本制度は適用されません 。比較的利子の支払額が少ない企業は、この基準によって適用対象外となります。
基準2:国内企業グループ全体での判定
もう一つの免除基準は、企業グループ全体で判定するものです。判定対象の法人とその法人との間に50%超の資本関係がある他の内国法人(国内企業グループ)全体で見て、「対象純支払利子等の額」の合計額が、「調整所得金額」の合計額の20%以下である場合には、適用が免除されます。これは、グループ内の個々の法人単位では基準を超えていても、グループ全体としては支払利子等が過大ではない場合にまで適用を及ぼさないようにするための規定です。
損金不算入額の繰越制度
過大支払利子税制によって損金不算入とされた金額(「超過利子額」といいます)は、永久に消滅するわけではありません。その事業年度以降7年間(注:令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始した事業年度分は10年間)にわたって繰り越すことができます。
そして、繰り越された先の事業年度で、対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%に満たない場合(つまり、損金算入の「枠」に余裕がある場合)、その余裕額を限度として、繰り越されてきた超過利子額を損金の額に算入することが認められています 。この適用を受けるためには、法人税申告書別表への記載など、継続的な管理が必要となりますので実務上ご注意ください。
もう一つの利子制限ルール「過少資本税制」との関係
国外関連者への支払利子を制限する税制としては、過大支払利子税制のほかに古くから「過少資本税制」が存在します。この章では二つの制度の関係性についてわかりやすく説明してきます。
過少資本税制とは?
過少資本税制は、国外の支配株主等からの借入金がその株主等が出資している資本金の額に比して過大である場合に、その過大な部分に対応する支払利子の損金算入を認めない制度です。一般的に、国外支配株主等からの負債の額が、自己資本の額の3倍を超える場合に適用が検討されます。これは、資本(出資)で資金調達すべきところを、過度に負債(借入)に依存することで租税回避を図ることを防止するものです。
どちらが優先される?損金不算入額の比較
国外関連者への支払利子について、過大支払利子税制と過少資本税制の両方の適用対象となる可能性があります。この場合、どちらか一方を選択して適用するわけではありません。実務では、まず両方の制度に基づいて、それぞれの損金不算入額を計算します。そして、その計算した結果、損金不算入となる金額のいずれか大きい方の金額が、実際に損金不算入として適用されることになります 。したがって、どちらか一方の基準をクリアしているからといって安心はできず、必ず両方の制度について検討し、比較する必要があります。
まとめ
過大支払利子税制は、BEPSプロジェクト以降、その対象範囲と厳格さが格段に増した国際税務における重要なルールです。実務担当者としては以下の点を常に意識し、適切な対応を取ることが求められます。
- 対象範囲の広さを認識する:国外関連者への支払利子だけでなく、金融機関からの借入利子なども含めて検討が必要です。また、「利子」の定義が経済的実質で判断されるため、金利スワップなども含めた幅広い金融取引が対象になり得ることを理解しておく必要があります。
- 計算要素を正確に把握する:「調整所得金額」の計算では、受取配当等の益金不算入額が加算されないなど特有のルールを正確に適用することが重要です。
- 二つの制度を常に比較検討する:国外関連者への支払利子がある場合は、必ず過少資本税制と過大支払利子税制の両方を計算し、不利な(損金不算入額が大きくなる)方の規定が適用されることを念頭に置く必要があります。
- 繰越額を管理する:損金不算入となった超過利子額は、将来の税負担を軽減する可能性のある資産です。申告書上で適切に管理し、繰越控除の適用漏れがないように注意が必要です。
これらの制度は複雑であり、今後の国際的な議論(BEP2.0など)の進展によっては、さらなる変更が加えられる可能性もあります。自社の資本政策や資金調達方法が税務上どのような影響を及ぼすか、少しでも不安や疑問がある場合は、安易に判断せず、国際税務に精通した専門家へ相談することをお勧めします。当サイトが運営する「みんなの国際税務Q&A」なども活用し、まずは一般的な情報を収集することから始めるのも一つの有効な手段です。