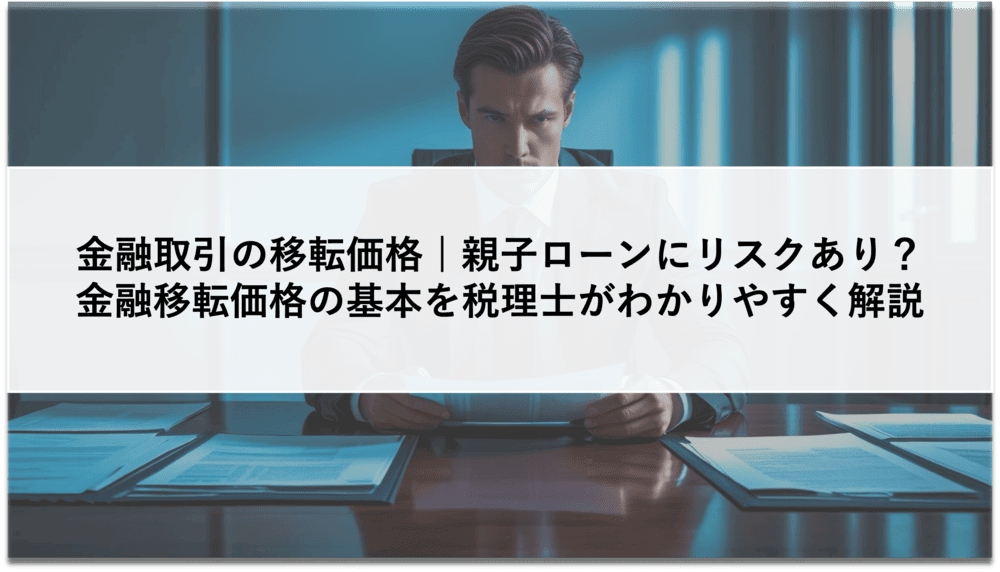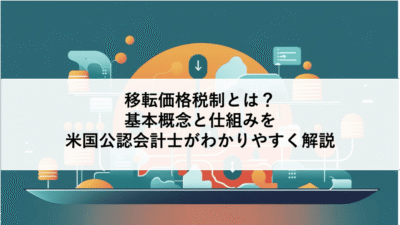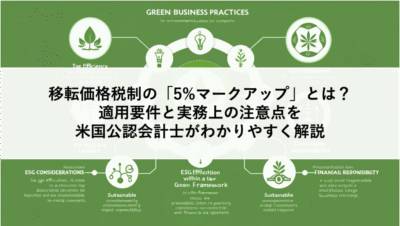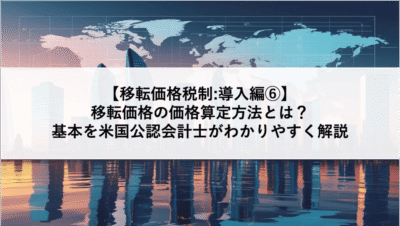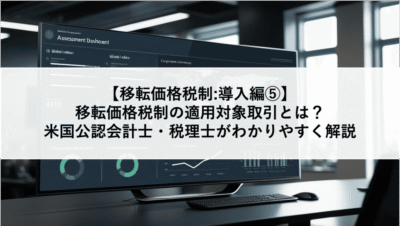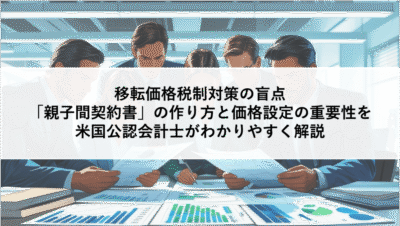海外に展開する子会社への運転資金の貸付けや現地での銀行融資に対する債務保証。これらはグローバルな企業グループにとってごく自然な支援活動に思えるかもしれません。
しかし、税務の世界、特に国際税務の観点から見ると、これらの行為は「移転価格税制」というルールの下で厳しく評価される対象となります。もし取引条件が税務当局に不適切だと判断されれば、意図せずして多額の追徴課税を受けることになりかねません。
この記事では具体的な計算方法といったテクニカルな話に入る前に、そもそも「なぜ親子間の金融取引が移転価格税制の対象となるのか」、そして「どのような考え方・概念を理解しておくべきか」という本質的な部分に焦点を当て、国際税務の専門家が丁寧に解説していきます。
重要コンセプト1:「もし、取引相手が”赤の他人”だったら?」で考える
移転価格税制のすべてを貫く大原則は、非常にシンプルです。それは、「もし、その取引相手が資本関係のない全くの第三者(赤の他人)だったら、どのような条件で取引しただろうか?」と考えることです。
移転価格税制の目的は「利益移転の防止」
移転価格税制は企業が海外の子会社との取引価格を意図的に操作し、税率の低い国に利益を移転させて、グループ全体の税負担を不当に軽くすることを防ぐための制度です。
例えば、親会社が製造した製品を海外子会社に極端に安く販売すれば、親会社の利益は減り、それと同時に海外子会社の利益が増えます。そして子会社の国の税率が日本より低ければ、グループ全体で納税額を圧縮できてしまいます。こうした事態を防ぐのが、移転価格税制の役割です。
すべての取引を「第三者との取引」に置き換える
このルールを適用するため、税務上は、親子会社間の取引であってもあたかも独立した第三者同士の取引(これを「独立企業間取引」と呼びます)であるかのように評価し直します。
そして、その取引から生じる価格や利益が第三者間で行われた場合に想定される価格(独立企業間価格)とかけ離れている場合、その差額は親会社から子会社への贈与(寄附金)や、逆に子会社から親会社への利益の付け替えとみなされ、課税対象となってしまいます。
この大原則は、モノの売買だけでなく、金銭の貸し借りや保証といった金融取引にも、全く同じように適用されます。
重要コンセプト2:親子間の金利を”言い値”で決めてはいけない
この原則を踏まえ、親会社が海外子会社に融資をするケースを考えてみましょう。
「利息」もモノの値段と同じ「価格」
この取引における「価格」は、融資の対価である「金利(利息)」です。
親子間だからといって無利子にしたり、親会社が銀行から借りている金利をそのまま適用したりするのは、移転価格税制上、必ずしも適切とは言えません。「もし、子会社が”赤の他人”の会社だったら、本当にその金利で貸しますか?」と問われてしまうわけです。
考えるべきは「借り手(子会社)の信用力」
では、何を基準に金利を考えればよいのでしょうか。最も重要なコンセプトは、「借り手である子会社の、独立した企業としての信用力」です。具体例を考えてみましょう。
もしあなたが銀行の融資担当者だったら、という仮定をしてみましょう。あなたの銀行に新たに融資を申し込んできた会社が銀行とは全く無関係な会社(つまり、あなたの銀行と全くの資本関係がない会社)だったとしたら、果たしてあなたの銀行はいくらの金利を提示するでしょうか?この場合、当然その会社の財政状態や将来性(つまり信用力)を厳しく審査し、リスクに見合った金利を設定するはずです。返済が滞るリスクが高いと判断すれば金利は高くなりますし、安定した優良企業であれば金利は低くなります。
移転価格税制が求めているのは、まさにこの考え方です。親会社という後ろ盾を一旦考慮から外し、「子会社が金融機関等から単独で資金調達した場合に適用されるであろう金利水準」を客観的に検討することが、独立企業間金利を考える上での出発点となります。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
重要コンセプト3:親子間の「債務保証」においてタダの信用供与は存在しない
次に、親会社が子会社の銀行借入に対して債務保証を行うケースを考えてみましょう。これも一見すると単なる支援行為に見えますが、税務上は明確な役務提供取引とみなされます。
保証の本質は「信用の切り売り」
債務保証とは、親会社が持つ高い信用力を子会社のために「分け与える」行為です。その結果、子会社は単独では借りられなかったであろう金額をより低い金利で借りることが可能になります。これは子会社にとって明確な経済的便益です。
ここでも、「もし、取引相手が”赤の他人”だったら?」の原則に立ち返ってみましょう。
全く無関係な第三者の会社の借金のために、自社の信用を危険に晒してまで保証人になることは通常ありえません。 もしなるとすれば、そのリスクに見合うだけの「見返り(保証料)」を必ず要求するはずです。
「保証料」はリスクに対する対価
移転価格税制では、この「見返り」をゼロ、つまり無償で保証を行うことは原則として認められません。親会社の信用力を利用して子会社が得た便益(例えば、保証のおかげで節約できた金利分)に対して、相応の対価(保証料)を子会社から受け取るべきだと考えます。
つまり、タダで保証をすることはその便益分を子会社に無償で贈与したのと同じこととみなされ、寄附金課税などのリスクを生じさせるのです。
重要コンセプト4:「なぜこの条件なのか」を合理的に説明できるように
ここまでは金融取引における移転価格の基本的な考え方を解説しました。重要なのは完璧な正解を一つだけ見つけることよりも、「自社が設定した取引条件が、独立企業間原則に照らして合理的である」ということを客観的な根拠をもって説明できるように準備しておくことです。
一般に、これを「移転価格文書化」と呼びます。税務調査で問われるのは、まさにこの「なぜ?」の部分です。「なぜ、この貸付金利なのですか?」「なぜ、保証料を無償にしているのですか?(あるいは、その保証料なのですか?)」これらの問いに対して「親子会社だからです」という答えは通用しません。「子会社の信用力をこのように評価し、類似のリスクを持つ第三者間取引の市場データを参考にこの金利を決定しました」というように、論理的なストーリーを構築し、それを裏付ける資料を提示する必要があります。
まとめ
親子間の金融取引における移転価格の問題は一見すると複雑で難解に思えるかもしれません。しかし、その根底にあるのは「もし取引相手が第三者だったらどうするか?」というシンプルな大原則です。まずはこの大原則を社内で共有し、自社のグループ内金融取引がこの考え方から大きく外れていないかを確認することから始めてみることをお勧めします。