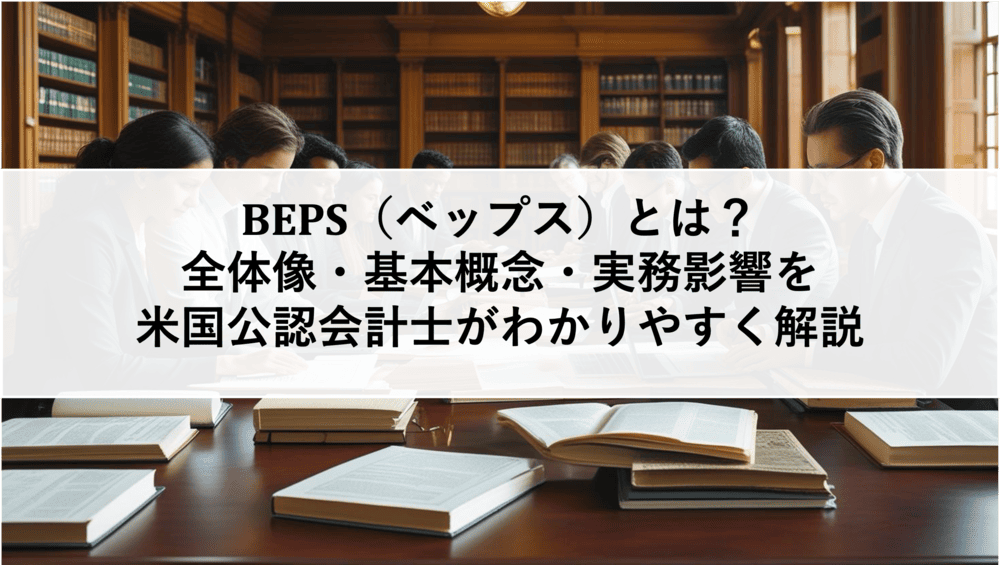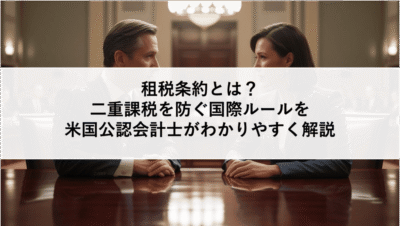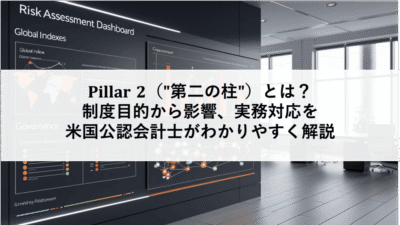BEPS(ベップス)の基本概念から背景、実務への影響まで、実務担当者が押さえるべきポイントを米国BIG4出身の会計士が丁寧に解説します。実務経験に基づいた視点で、BEPSプロジェクトの注意点をわかりやすくお伝えします。
BEPS(ベップス)とは何か?
BEPSとは、「Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)」の略称です。直訳では意味がつかみにくいため、もう少しかみ砕いて言えば、「企業が意図的に利益を低税率国へ移し、課税所得を減らす行為」を指す用語です。
このような行為は必ずしも違法とは限りません。むしろ、合法的な制度の隙間(抜け穴)を利用した「国際課税のグレーゾーン」として、長年世界中の税務当局が課題視してきました。
OECD(経済協力開発機構)はこの問題に国際的に対処するため、2013年から「BEPSプロジェクト」を立ち上げ、世界中の国々と連携して課税ルールの再設計を進めてきました。
企業がBEPSを通じて行ってきたこと
企業が行っていた典型的なBEPSスキームには、以下のような手法があります。
-
高収益ビジネスの知的財産(特許や商標など)を低税率国の関連会社に移転し、高税率国の事業会社がその使用料(ロイヤリティ)を支払う
-
移転価格を調整し、利益を税率の低い国の関連会社に集中させる
-
タックスヘイブンに子会社を設立し、資金や利益を移動させることで課税回避を図る
こうしたスキームの多くは、法の抜け道を利用した結果であり、企業にとっては「節税」、各国政府にとっては「税逃れ」となる構造でした。
BEPSプロジェクトとは何か?15の行動計画
OECDが推進するBEPSプロジェクトでは、15の「行動計画(Action Plans)」を柱とし、国際課税の抜け穴をふさぐためのルール整備が行われました。
その中でも特に実務に影響が大きかったのは、以下のような取り組みです。
-
移転価格ルールの見直し(実体ある活動への利益配分)
→ アクション8〜10:移転価格に関する指針の見直し
(無形資産の配分、リスクの配分、資本の機能と実体の整合性など) -
タックスヘイブン対策税制(CFCルール)の整備
→ アクション3:CFC(Controlled Foreign Company)ルールの強化 -
租税条約の乱用防止策(Principal Purpose Testなど)
→ アクション6:租税条約の濫用防止
(主たる目的テスト(PPT)や制限的居住者条項の導入など) -
多国籍企業による国別報告書(CbCR)の義務化
→ アクション13:移転価格文書化とCbCRの導入 -
ハイブリッド取引を用いた二重非課税の防止
→ アクション2:ハイブリッドミスマッチ取引への対応
(異なる課税制度の差異を利用した二重控除や非課税の防止)
これらのルールは多くの国で国内法化され、現在では国際課税の基本枠組みとして実務の中に組み込まれています。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
BEPSと「実務」の関係:どう対応すべきか
実務担当者にとって、BEPSというテーマはもはや理論ではなく、日常業務と密接に関わるものとなっています。特に以下のような領域で注意が必要です。
-
グループ間取引の価格設定と文書化
移転価格の設定根拠を第三者にも説明できるよう、適切なローカルファイル・マスターファイルを整備することが求められます。 -
所得・税負担の国別分布の透明化
国別報告書(CbCR)を通じて、各国での利益・従業員数・税金支払額の整合性が問われるため、統一された財務・税務データ管理が必要です。 -
実体の伴った海外子会社運営
“紙だけの会社”による利益集中はリスクが高まり、各国の税務調査においても強く問題視される傾向があります。 -
租税条約の適用根拠の見直し
従来の“形式上の居住者”では通用しなくなり、条約適用の理由付けと文書管理がより厳格化しています。
おわりに
BEPSとは、「グローバル企業における税金のあり方そのものを再定義する」大きな流れの中で生まれた国際課税の改革です。各国の法制度が整備されたことで、単なる節税テクニックとしてのBEPSは過去のものとなりつつあります。
現在の実務に求められるのは、「透明性と説明責任を前提とした税務体制の構築」です。特に中堅以上のグローバル企業においては、税務部門だけでなく、財務・法務・事業部門とも連携しながら、BEPS対応を“組織的に”行う体制が求められています。
本記事が、BEPSの全体像を理解する第一歩として役立てば幸いです。