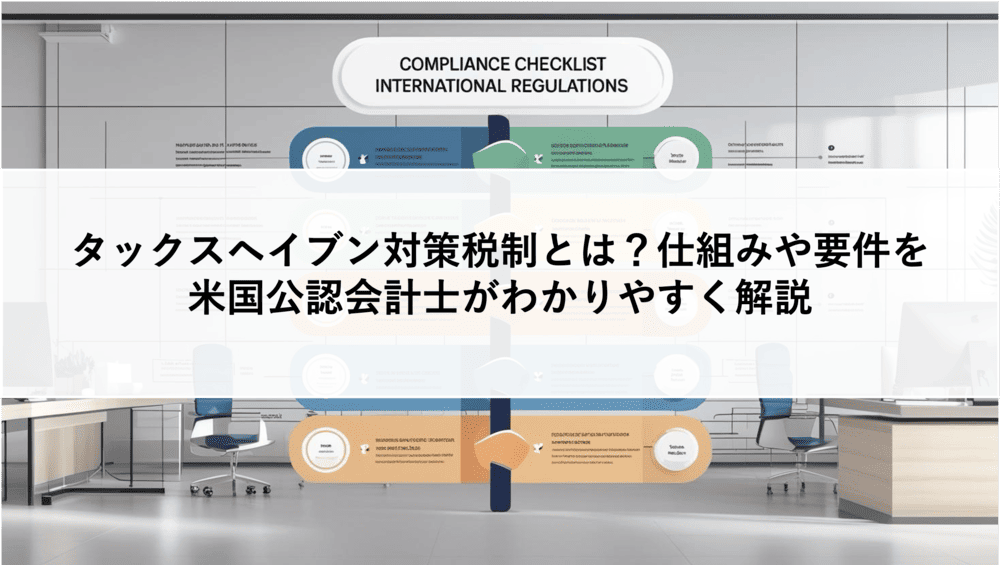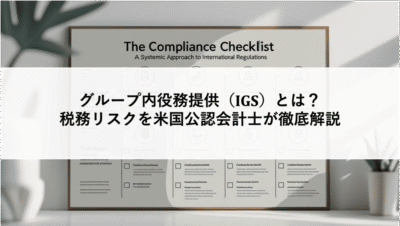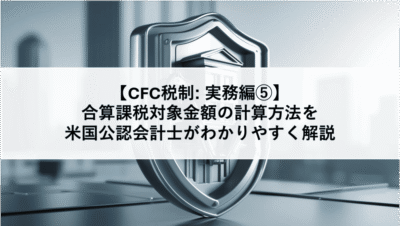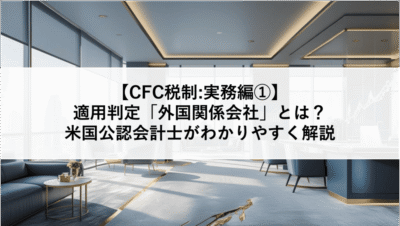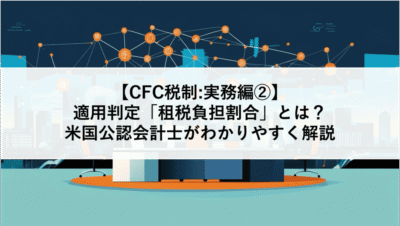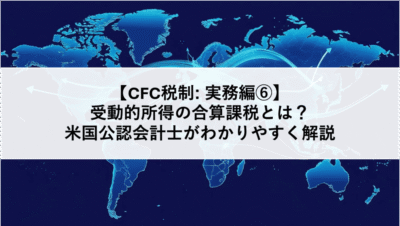海外子会社の利益が日本の課税対象になるCFC税制(タックスヘイブン対策税制)。その仕組みや適用要件、判定フローについて、その全体像から実務上の注意点までわかりやすく解説します。
全体像だけをサクッと知りたい方にはこちらの2本がオススメ👇
【CFC税制:導入編①】全体像が5分でわかる|米国公認会計士・税理士がわかりやすく解説
【CFC税制:導入編②】適用判定フローの全体像が5分でわかる|米国公認会計士・税理士がわかりやすく解説
CFC税制(タックスヘイブン対策税制)とは何か?
CFC税制とは、日本の親会社などが、税率の低い国や地域(いわゆるタックスヘイブン)に設立した子会社に利益を留保することで、日本で本来課されるべき税負担を不当に免れる行為を防止するための制度です。この制度は、日本における正式名称である「外国子会社合算税制」のほか、その目的から「タックスヘイブン対策税制」とも呼ばれます。これらの名称はすべて同じ仕組み・制度を指しており、国際税務の文脈で頻繁に登場するため、まずは同義語として認識しておいて差し支えありません。
この制度の核心は、一定の条件を満たす海外子会社の所得をあたかも日本の親会社の所得であるかのように「合算」し、日本で課税するという点にあります。通常、海外子会社は独立した法人格を持つため、その利益は現地で課税され、日本で課税されるのは親会社が海外子会社から配当を受け取った時などに限られます。しかし、CFC税制が適用されると、子会社が現地で利益を留保している段階においてその一部または全部が日本の親会社の所得とみなされ、日本の法人税の課税対象となってしまうのです。
なぜCFC税制は存在するのか?租税回避の基本的な仕組みと歴史的背景
この複雑な制度がなぜ必要なのかを理解するためには、まず「タックスヘイブン」を利用した租税回避の基本的な仕組みと、それに対抗してきた国際的な歴史的背景を知ることが不可欠です。
タックスヘイブンとは何か
タックスヘイブン(租税回避地)とは、法人税や所得税が全くかからない、あるいは税率が著しく低い国や地域を指します。これらの地域は「相対的に低い税率」を戦略的に用いて海外から企業や資本を誘致し、経済を発展させようという狙いがあります。代表的な地域としては、カリブ海のケイマン諸島やヴァージン諸島、アジアの香港やシンガポール、ヨーロッパのルクセンブルクなどが挙げられます。
重要なのは、タックスヘイブンに子会社を設立すること自体が違法行為ではないという点です。問題となるのは、これらの地域の低い税率を悪用して事業の実態を伴わない形で利益をタックスヘイブンへ移転させ、本来税負担を負うべき国での納税を回避する行為です。
租税回避のスキーム
CFC税制がなければ、どのような租税回避が可能になるのでしょうか。典型的なスキームは以下の通りです。
- 日本の親会社(A社)が、法人税率が極めて低い国(B国)に子会社(B社)を設立します。
- A社は、本来であれば日本で計上されるべき利益を、何らかの名目(例えば、実態にそぐわない高額な経営指導料やブランド使用料など)でB社に移転させます
- その結果、A社の利益は圧縮され、日本の法人税は減少します。一方、B社に移転された利益は、B国の低い税率でしか課税されません。(*下段で補足します)
- B社がその利益を配当としてA社に支払わない限り、日本の課税は無期限に繰り延べられ、グループ全体としての税負担が大幅に軽減されることになります。
CFC税制は、このような「実態のない子会社」を利用した利益の移転と、それによる課税の繰り延べを阻止するために設計されています。
制度の歴史と目的の変遷
このような租税回避への対抗策は、日本独自の制度ではありません。経済のグローバル化が進む中で、資本の国際的な移動が容易になり、各国が同様の問題に直面しました。世界で最初に包括的なCFC税制を導入したのは米国で、なんと60年以上も前、1962年のことです。その後、現在のドイツ、フランス、イギリスといった欧米の先進国が追随し、日本でも1978年(昭和53年)に導入されました。これは、CFC税制が特定の国の特殊なルールではなく、自国の税基盤を守るための国際標準的な税制であることを示しています。
また、制度の目的も時代と共に変化しています。導入当初の主な目的は、海外子会社での利益留保による「課税の繰り延べ防止」にありました。しかし、その後、一定の要件を満たす海外子会社からの配当を親会社の益金に算入しない「外国子会社配当益金不算入制度」が導入されたことで、状況は変わりました。配当を日本に還流させても課税されないのであれば、「課税の繰り延べ」自体の意味が薄れるからです。
このため、近年のCFC税制は、単なる課税のタイミングの問題ではなく、より根源的な「租税回避行為そのものの防止」に重点を置くようになったと解釈されています。これは、子会社の事業に正当な理由があったとしても、その実態が租税回避の手段として利用されていると判断されれば、課税対象となる可能性が高まったことを意味します。税務当局は、海外子会社の存在理由や事業の経済的合理性を、より厳しく問うようになっているのです。
CFC税制の適用判定:あなたの海外子会社は対象か?(判定フロー解説)
CFC税制が適用されるかどうかの判定は、海外子会社がタックスヘイブンにあるかどうかという単純な所在地主義ではなく、株式の保有関係、現地の税負担率、そして事業の実態という複数の要素を総合的に勘案して行われます。
この判定フローは、いわば「推定」の連続です。法律はまず、低税率国にある子会社を「租税回避の疑いあり」と推定し、納税者側がその推定を覆すための証拠(事業の実態など)を提示する責任を負う、という構造になっています。これは、通常の税務調査で税務当局が課税の根拠を立証するのとは逆の、納税者にとって非常に重い負担を課す仕組みです。以下、判定のステップを順に解説します。
Step 1: 「外国関係会社」に該当するか?
最初の関門は、海外子会社がCFC税制の対象となりうる「外国関係会社」に該当するかどうかです。これは主に株式の保有割合によって判定されます。
具体的には、日本の法人や居住者(株主グループ)が、外国法人の発行済株式等のうち、直接または間接に50%超を保有している場合、その外国法人は「外国関係会社」となります。また、株式保有が50%以下でも、契約などによって実質的に支配していると認められる場合も同様に扱われます。つまり、形式的な持分比率だけではなく、「実質的に支配関係にあるか」という定性的な観点も加味されます。
このステップで該当しなければ、CFC税制の検討はここで終了します。しかし、日系企業の多くの海外子会社はこの要件を満たすため、次のステップに進むことになります。
Step 2: 租税負担割合によるスクリーニング(トリガー税率)
次に、外国関係会社の所得に対して、その本店所在地国でどれくらいの税金が課されているか、すなわち「租税負担割合」が問われます。この税率が、CFC税制の本格的な適用の引き金(トリガー)となるため、「トリガー税率」とも呼ばれます。
租税負担割合に応じて、扱いは以下の3つに分かれます。
- 30%以上の場合:租税負担が十分に高いとみなされ、原則としてCFC税制の適用は免除されます。この場合、後述する「特定外国関係会社」に該当するかどうかの判定資料の提出も不要となり、コンプライアンス負担は大幅に軽減されます。
- 20%以上30%未満の場合:この場合も、原則としてCFC税制の適用は免除されます。ただし、後述する「ペーパーカンパニー」などの「特定外国関係会社」に該当しないことを証明する責任が納税者側にあります。税務当局から資料の提出を求められた場合、それに応じなければ特定外国関係会社に該当すると推定される可能性があります。
- 20%未満の場合:租税負担が低いと判断され、その外国関係会社は「対象外国関係会社」として、CFC税制の本格的な検討対象となります。この場合、原則として所得の合算課税の対象となりますが、次のステップで解説する「経済活動基準」をすべて満たすことで、それを免れる道が残されています。
Step 3: 「特定外国関係会社」の厳しい判定(要注意)
租税負担割合が20%以上30%未満であっても、あるいは20%未満であっても、その会社が実質的な活動を伴わないとみなされる特定の類型に該当する場合、「特定外国関係会社」として厳しい扱いを受けます。これらに該当すると、後述する経済活動基準による免除の機会なく、原則としてその所得のすべてが合算課税の対象となります。(注意:従来は、租税負担割合が「30%以上の場合に(特定外国関係会社の)適用免除」というルールでしたが、令和6年4月1日以降開始の事業年度からは「27%以上の場合に適用免除」というルールに変更されています。)
特定外国関係会社には、主に以下の3つの類型があります。
- ペーパーカンパニー:法人登記はされているものの、事業活動の実態がない会社を指します。具体的には、以下の2つの基準をいずれも満たさない外国関係会社を指します。
-
- 1. 実体基準: その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を本店所在地国に有していること。
- 2. 管理支配基準: その事業の管理、支配および運営を、自ら本店所在地国において行っていること。つまり、物理的な拠点もなければ、自律的な経営も行われていない会社がペーパーカンパニーと判定されます。
-
- キャッシュボックス (Cash Box):その資産や所得の大部分が、株式の配当や有価証券の売買益といった受動的なものから構成されている会社です。これは、事業実態はあっても、その実態が資産運用(金庫番)に過ぎない会社を捕捉するための規定です。具体的には、以下の2つの基準をいずれも満たす外国関係会社が該当します。
-
- 1. 受動的所得(配当、利子、有価証券譲渡損益など)の合計額が、総収入金額の30%超であること。
- 2. かつ、受動的所得を生み出す資産(有価証券、貸付金など)の合計額が、総資産の価額の50%超であること。
-
- ブラックリスト国所在の法人:租税に関する情報の交換に非協力的であるとして、財務大臣が指定した国や地域に本店を置く外国関係会社です。これらの地域に会社を置くこと自体が、租税回避のリスクが高いとみなされます。
Step 4: 事業実態を証明する「経済活動基準」
租税負担割合が20%未満であり、かつ上記の「特定外国関係会社」に該当しない外国関係会社は、最後の砦である「経済活動基準」の判定に進みます。ここで、以下の4つの基準をすべて満たすことを証明できれば、会社単位での全面的な合算課税を免れることができます。しかし、1つでも満たせない基準があれば、原則として所得の全部が合算課税の対象となります。
1. 事業基準:主たる事業が、株式の保有、債券の保有、工業所有権等の提供、著作権等の提供、有価証券の保有といった、受動的な性質の強い事業ではないことが求められます。
2. 実体基準:本店所在地国に、主たる事業を行うために必要な事務所等の固定的な施設を有していることが必要です。これはペーパーカンパニー判定における実体基準と同じものです。
3. 管理支配基準:本店所在地国において、事業の管理、支配、運営を自ら行っていることが求められます。これもペーパーカンパニー判定の基準と共通です。
4. 所在地国基準 または 非関連者基準:業種に応じて、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
所在地国基準: 卸売業、銀行業、保険業などの特定の業種を除き、主たる事業を主としてその本店所在地国で行っていること。
非関連者基準: 卸売業、銀行業、保険業、海運業、航空運送業などの場合、主たる事業を主として関連者以外の者との間で行っていること。
この判定構造は、税率の低い国(20%未満)での事業活動に対して、税務当局が段階的に厳しい目を向けていることを示しています。まずペーパーカンパニーでないことを証明し(実体基準・管理支配基準)、さらに事業内容が能動的であり(事業基準)、かつその活動が現地に根差しているか、あるいは独立した第三者との取引が中心であること(所在地国基準・非関連者基準)まで求められます。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
課税される所得の範囲:「全部合算」と「部分合算」の違い
CFC税制の適用判定の結果、課税対象となった場合に、どの範囲の所得が日本の親会社で合算されるのでしょうか。これには大きく分けて「会社単位の合算課税(全部合算)」と「部分合算課税」の2種類があります。
会社単位の合算課税(全部合算)
これは最も厳しい措置であり、以下のいずれかの場合に適用されます。
- 外国関係会社が「特定外国関係会社」(ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリスト国所在法人)に該当する。
- 租税負担割合が20%未満の外国関係会社が、「経済活動基準」のいずれか1つでも満たさなかった。
この場合、その外国関係会社の所得の全額(日本の税法に基づいて計算し直したもの、もしくは海外子会社の現地法令に基づいて算定したもの)が、日本の親会社の所得に合算され、課税対象となってしまいます。
部分合算課税(受動的所得の合算)
一方、外国関係会社が「特定外国関係会社」には該当せず、かつ「経済活動基準」をすべて満たした場合でも、完全にCFC税制から解放されるわけではありません。事業実態が認められたとしても、その会社が保有する資産から生じる「受動的所得」については、合算課税の対象となります。
この制度の背景には、たとえ現地で正当な事業活動を行っていたとしても、その会社を「金庫」として利用し、配当、利子、有価証券の譲渡益といった、本来であれば日本で課税されうる金融所得などを蓄積させることによる租税回避を防ぐ狙いがあります。
ただし、事務負担への配慮から、この部分合算には適用免除の特例があります。合算対象となる受動的所得の金額が2,000万円以下、またはその外国関係会社の税引前利益の5%以下である場合には、部分合算課税は免除されます。
二重課税を防止する「外国税額控除」の仕組み
CFC税制によって海外子会社の所得が日本で合算課税される場合、当該所得にはすでに現地国で法人税が課されていることも多く、結果として経済的な二重課税が生じる可能性があります。こうした課税の重複は、企業の海外展開における税務コストの増加を招くため、租税負担の適正化という観点からも制度上の配慮が必要とされています。
この問題に対応するために設けられているのが「外国税額控除」の制度です。これは、CFC税制の適用により日本で合算課税される所得に関して、海外子会社が現地で納付した法人税額を、日本の親会社が納める法人税額から一定の範囲で控除できることを認める仕組みです。
例えば、合算された所得に対して計算された日本の法人税額が300万円で、その所得について子会社が現地で100万円の法人税を納付済みであった場合、その100万円を差し引いた200万円を日本で納税することになります(計算は簡略化しています)。
この仕組みにより、CFC税制は罰則的な二重課税ではなく、現地での税負担が日本の税負担に満たない場合に、その差額分を日本で追加的に納税させる「トップアップ税」としての性格を持つことになります。これは、制度の国際的な正当性を担保する上で極めて重要な役割を果たしています。
企業が知っておくべき実務上の注意点と最新の税制改正
CFC税制は、その複雑さに加え、国際的な租税回避への対抗策の進展に伴い、頻繁に改正が行われる分野です。ここでは、企業が実務上特に注意すべき点と、最新の動向について解説します。
書類の準備と立証責任
CFC税制の適用判定において最も重要な実務は、経済活動基準などを満たしていることを客観的に証明するための書類を整備・保存しておくことです。税務当局は、租税負担割合が一定以下の外国関係会社について、経済活動基準を満たすことを明らかにする書類の提出を求めることができ、納税者がこれに応じられない場合、基準を満たさないものと「推定」する権限を持っています。
具体的には、外国関係会社の財務諸表はもちろんのこと、本店所在地の賃貸借契約書、従業員リスト、組織図、取締役会議事録、事業計画書、主要な取引契約書など、事業の実体や管理支配の実態を示すあらゆる資料を、いつでも提示できるよう準備しておく必要があります。
令和7年度税制改正:合算時期の変更
実務に大きな影響を与える改正として、令和7年度税制改正大綱に盛り込まれた合算時期の変更が挙げられます。
従来、外国関係会社の所得を日本の親会社の所得に合算する事業年度は、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から「2月」を経過する日を含む親会社の事業年度とされていました。今回の改正で、この期間が「4月」に延長されます。この変更は、一見すると軽微な修正に見えますが、実務上のコンプライアンス負担を大きく左右します。例えば、3月決算の日本親会社と12月決算の海外子会社という一般的なケースで考えてみましょう。
- 改正前(2月ルール): 子会社の2025年12月期の所得は、期末(12月31日)の翌日から2ヶ月後である2026年2月28日を含む親会社の事業年度、すなわち親会社の2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)に合算する必要がありました。これは、子会社の決算が確定してから親会社の決算・申告準備に含めるまでの期間が非常に短く、実務上大きな負担となっていました。
- 改正後(4月ルール): 子会社の2025年12月期の所得は、期末の翌日から4ヶ月後である2026年4月30日を含む親会社の事業年度、すなわち親会社の2027年3月期(2026年4月1日~2027年3月31日)に合算されることになります。
このように、「合算年度が1年後ろにずれる」ことで、親会社は子会社の決算数値を十分に確認し、日本の税法に合わせた調整を行うための時間を確保できるようになります。これは、税務当局が企業の現実的な事務負担に配慮した、実務上非常に意義のある改正と言えます。
グローバル・ミニマム課税との関係
近年、国際課税の分野で最も大きな変化が、OECD/G20が主導する「グローバル・ミニマム課税(第2の柱)」の導入です。これは、年間総収入金額が7.5億ユーロ以上の巨大多国籍企業グループを対象に、子会社が所在する国の税率に関わらず、最低15%の税負担を確保しようという国際的なルールです。
日本のCFC税制とグローバル・ミニマム課税は、どちらも低税率国を利用した租税回避に対処するという点で共通していますが、その目的と仕組みは異なります。CFC税制が個別の租税回避スキームを対象とするのに対し、グローバル・ミニマム課税は国際的な法人税率の引き下げ競争に歯止めをかけることを目的としています。
例えば、ある子会社の所在地国の実効税率が10%だった場合、まずグローバル・ミニマム課税により15%への「トップアップ税」が検討されます。さらに、日本のCFC税制における20%のトリガー税率との比較によって、合算課税の要否も判断されます。現時点では両制度の適用対象や課税方法が異なるため、同一の所得に対して二重に課税調整が行われる可能性があり、両制度の整合的な運用ルールの策定が今後の実務上の重要な課題となっています。
まとめ:CFC税制と向き合うために
CFC税制(タックスヘイブン対策税制)は、一見すると非常に複雑で難解な制度です。しかし、その根底にあるのは、「事業の実態(サブスタンス)が伴わない海外利益には、日本の税を課す」という、シンプルかつ合理的な思想です。
本記事で解説した通り、適用の可否は、子会社が所在する国がタックスヘイブンかどうかという形式的なレッテルだけで決まるわけではありません。租税負担割合、法人の類型、そして何よりも事業の経済的合理性という、多段階の客観的な基準に基づいて判定されます。現代の国際税務において最も重要な原則は「実態主義」です。企業は、海外子会社の設立や運営にあたり、法的な形式を整えるだけでなく、その事業目的や活動内容について、説得力のあるストーリーとそれを裏付ける証拠を常に準備しておく必要があります。
CFC税制の適用判定は個別性が高く、また、グローバル・ミニマム課税の導入など、国際的なルールは常に変化し続けています。自社の海外事業が意図せずして課税リスクに晒されることのないよう、海外に子会社をお持ちの、あるいはこれから設立を検討されている企業は、必ず国際税務に精通した専門家に相談し、自社の状況を的確に評価・管理することが不可欠です。