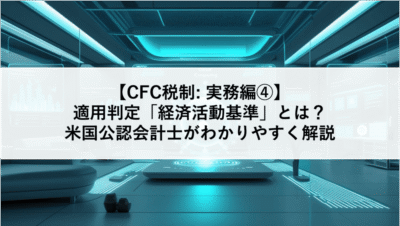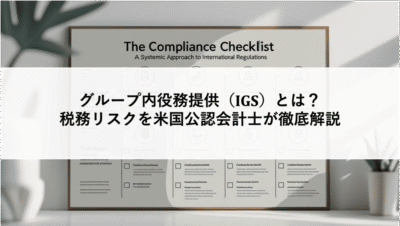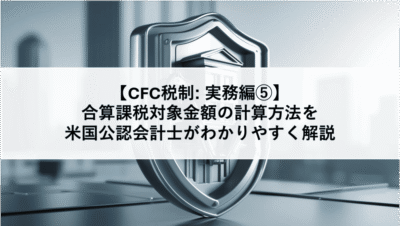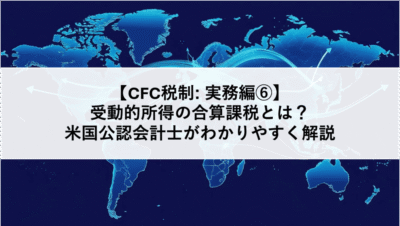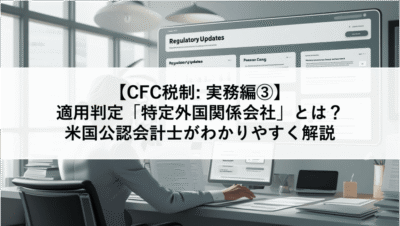海外子会社のCFC税制、適用判定と所得合算は「いつ」行うかご存知ですか?外国関係会社の判定日と親会社の合算年度が決まる「期末後2か月ルール」を具体例を交えて国際税務の専門家がわかりやすく解説します。
はじめに:実務担当者が必ず押さえるべき「タイミング」の問題
これまでの解説でCFC税制(タックスヘイブン対策税制)の複雑な判定フローや合算すべき所得金額の計算方法を見てきました。しかし、実務の現場で経理担当者が直面するもう一つの重要な問いが「その判定や所得の合算は、一体『いつ』の時点で行うのか」というタイミングの問題です。
本記事では、この実務上不可欠なCFC税制の「判定タイミング」と「合算課税のタイミング」について、その基本ルールから決算月が異なるケースの具体例まで、実務上のポイントを分かりやすく解説していきます。
【完全ガイド】CFC税制(タックスヘイブン対策税制)とは?基礎から実務対応まで総まとめ | 米国公認会計士・税理士がわかりやすく解説
【CFC税制: 実務編⑥】受動的所得の合算課税とは?実務ポイントを米国公認会計士がわかりやすく解説
判定と合算課税の2つの基本ルール
CFC税制のタイミングを理解する上でまず押さえるべき基本ルールが2つありますので、以下で詳しく見ていきましょう。
ルール1:CFC適用判定の基準日は「外国関係会社の事業年度終了の日」
CFC税制の適用があるかどうかの一連の判定(外国関係会社に該当するか、租税負担割合はいくらか、経済活動基準を満たすか等)は、すべて外国関係会社の事業年度終了の日(期末日)の現況に基づいて行います。例えば期中に株式の保有割合が変わったとしても、最終的に期末時点で要件を満たしているかどうかで判断することになります。
ルール2:合算年度は「期末後2か月ルール」で決まる
合算課税の対象となった場合、その所得は「外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2か月を経過する日」が含まれる日本の親会社の事業年度の所得に合算します。
この「期末後2か月ルール」は少し分かりにくいため、多くの日本企業で見られる具体的なケースを例に、次のセクションで詳しく見ていきましょう。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
【具体例】決算月で変わる合算タイミング
このルールは、海外子会社と日本の親会社の決算月が異なる場合に特に注意が必要となります。
ケース1:海外子会社が12月決算、親会社が3月決算
これは非常によく見られるパターンですが、この場合、子会社の2025年12月期の所得は親会社の2026年3月期の所得に合算されることとなります。
- 親会社: 3月決算(例:2026年3月期は、2025年4月1日~2026年3月31日)
- 海外子会社: 12月決算(例:2025年12月期は、2025年1月1日~2025年12月31日)
【具体的な判定の流れ】
- 子会社の事業年度終了の日: 2025年12月31日
- 上記の日から2か月を経過する日: 2026年2月28日
- 2026年2月28日が含まれる親会社の事業年度: 2026年3月期
このケースでは、親会社は3月末の決算日までに、外子会社の12月期の数値を基にしたCFC税制の計算を完了させる必要があります。しかし、子会社側ではまだ決算が確定していないことも多く、非常にタイトなスケジュール管理が求められる点に実務上の注意が必要です。
ケース2:海外子会社・親会社ともに3月決算
両社の決算月が同じ場合はどうでしょうか。この場合、子会社の2026年3月期の所得は親会社の2027年3月期の所得に合算されます。
- 親会社: 3月決算(例:2027年3月期は、2026年4月1日~2027年3月31日)
- 海外子会社: 3月決算(例:2026年3月期は、2025年4月1日~2026年3月31日)
【具体的な判定の流れ】
- 子会社の事業年度終了の日: 2026年3月31日
- 上記の日から2か月を経過する日: 2026年5月31日
- 2026年5月31日が含まれる親会社の事業年度: 2027年3月期
このケースでは、決算月は同じでも、合算されるのは親会社の翌事業年度になるという点がポイントです。
まとめ
今回は、CFC税制の判定と合算課税のタイミングについて実務的な観点から解説しました。
- 判定の基準日は、常に外国関係会社の期末日となります。
- 合算する年度は、外国関係会社の期末日から2か月後の日が含まれる日本の親会社の事業年度となります。
CFC税制はその内容だけでなく、いつ、どの期間を対象とするのかという時間軸の理解も必要となる複雑な制度です。特に決算・申告業務やM&Aの検討に際してはこれらのタイミングルールを念頭に置き、必要に応じて専門家にご相談いただくことをお勧めします。