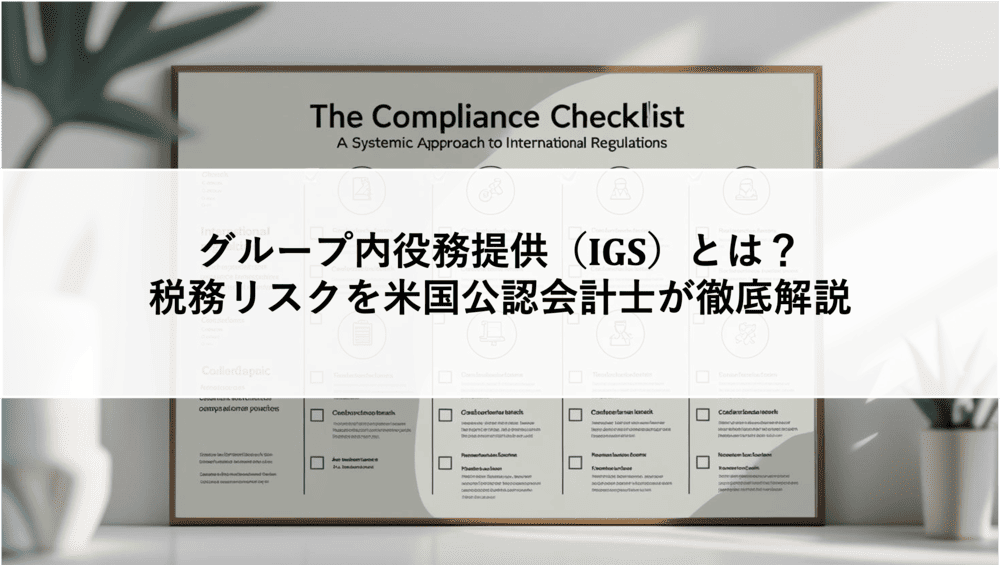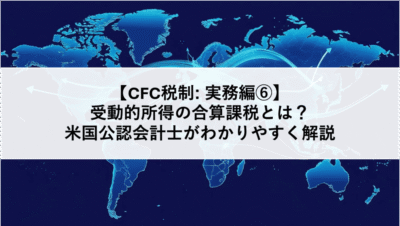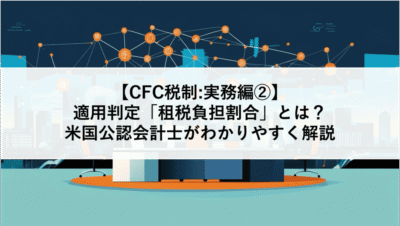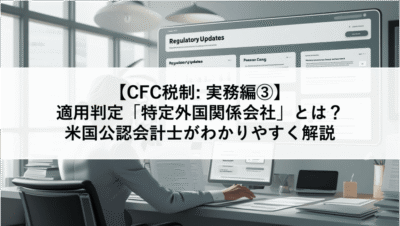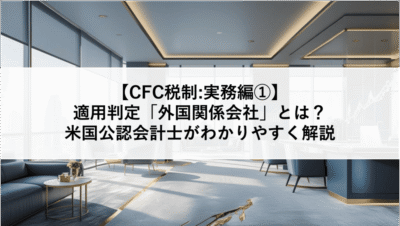国際税務の世界では、多国籍企業グループ内で日常的に行われる支援業務等は「グループ内役務提供(IGS)」と呼ばれ、税務担当者が日々アンテナを張っている分野の一つです。これが国際税務、特に移転価格税制においてなぜ重要なのか、その基本概念から具体的な対象範囲、税務調査での指摘リスクまで、国際税務の専門家が初学者にも分かりやすく解説します。海外子会社を持つ企業であれば規模の大小を問わず関わるこのテーマについて、その本質と実務的な対応策を深く掘り下げていきましょう。
はじめに:見過ごされがちな「グループ内役務提供」の税務リスク
グローバルに事業を展開する企業にとって、日本の親会社が海外の子会社に対して経理や法務、ITシステムの運用支援などを行うことはごく当たり前の光景かもしれません。これらの活動は、グループ全体の効率化やガバナンス強化のために不可欠なものであり、多くの場合は「社内での当然の協力」として認識され、特別な対価の請求は行われていないのが実情でしょう。しかし、税務の世界、特に国際税務の観点からは、この「無償の支援」が予期せぬ税務リスクになることがあります。税務当局はこのようなグループ企業間の支援活動を「無償の役務提供(サービス提供)」とみなし、独立した第三者間であれば当然支払われるべき対価(通称、「独立企業間価格」)が回収されていないとして、課税を行う可能性があるのです。
この記事では、多くの企業が見過ごしがちな「グループ内役務提供(Intra-Group Services、以下「IGS」)」というテーマに焦点を当てます。IGSとは何かという基本的な定義から、なぜ移転価格税制の対象となるのか、そして最も恐れるべき「寄附金」と認定された場合のリスク、逆に対価の請求が不要となるケース、さらには実務的な対価の算定方法まで、段階を追って丁寧に解説していきます。本稿を通じて、IGSに関する税務上の基本的な考え方を整理し、将来の税務調査に備えるための一助となれば幸いです。
1. グループ内役務提供(IGS)とは?基本概念を理解する
まず、国際税務の文脈で語られる「グループ内役務提供(IGS)」が具体的に何を指すのか、その定義と判断基準を明確にしましょう。
1.1. IGSの定義と移転価格税制上の位置づけ
IGSとは、その名の通り、同一の企業グループに属する法人(例えば、親会社と子会社、または子会社同士)の間で提供される、有形資産の売買以外のあらゆるサービスのことを指します 。一般的に、本社機能の一部として行われる経営指導、経理・財務・法務といった管理業務の支援、技術指導、ITサポートなどがこれに該当します。
ここで重要なのは、これらのサービス提供は物品の売買と同様に「取引」の一種と見なされ、国外の関連会社との間で行われる場合には移転価格税制の適用対象となる点です。サービスの提供方向は一方通行ではなく、つまり、「親会社から子会社への支援」だけでなく、「子会社から親会社へ」あるいは「子会社間」で提供されるサービスもすべてIGSに含まれます。
この定義の広さからわかるように、海外に拠点を一つでも持つ企業であれば、ほぼ間違いなく何らかの形でIGSを行っていると考えられます。大企業だけの特別な問題ではなく、グローバルにビジネスを展開する中堅・中小企業にとっても身近な税務課題である理由がここにあります。
1.2. IGSに該当するかどうかの判断基準
では、グループ内で行われる全ての活動が課税対象となるIGSに該当するのかというと、実はそうではありません。税務当局がIGSに該当するかどうかを判断する上で最も重要な基準が「そのサービスに有償性があるかどうか」です。
これは、サービスの受け手である関連会社が、その活動から「経済的または商業的な価値(便益)」を享受しているかどうかで判断する考え方です。具体的には、以下の2つの問いに対してともに「YES」の場合、その活動は受け手にとって価値のあるサービスであり、対価を収受すべきIGSに該当すると判断されます。
- もしその活動が提供されなかった場合、サービスの受け手(子会社など)は、自社で同様の活動を行うか、あるいは外部の第三者に対価を支払って依頼する必要があったか。
- 独立した第三者であれば、同様の状況下で、その活動に対して対価を支払う意思があるか。
ここで注意すべきは、サービス提供者(親会社など)の意図と、税務当局の視点にギャップが生じやすい点です。例えば、親会社がグループ全体のITインフラを標準化するために子会社のシステムを更新した場合、親会社はこれを「自社のための管理コスト」と認識するかもしれません。しかし、税務当局は「子会社が、本来であれば自ら調達すべきであった新しいITシステムという便益を享受した」と判断する可能性があります。重要なのは、提供側の意図ではなく、受け手側が経済的便益を得たかどうかという客観的な事実です。
1.3. IGSの具体的な活動例
受益者負担の原則をより具体的にイメージするために、国税庁の事務運営指針などでも例示されているIGSの典型的な活動例を以下に挙げます 。これらはあくまで一例であり、これら以外にも多種多様な活動がIGSに該当し得る点にはご留意ください。
- 経営・管理部門の支援
- グループ全体の経営戦略の企画・調整
- 子会社の予算策定支援や予実管理、財務に関する助言
- 会計処理、監査対応、税務申告、法務相談に関する支援
- 財務部門の支援
- キャッシュフローや支払能力の管理(CMSなど)
- グループ内金融(融資)や資金調達の支援
- 為替リスクや金利リスクの管理支援
- 事業部門の支援
- 製造、購買、販売、物流、マーケティングに関する業務支援
- 情報通信システム(IT)の運用、保守、管理
- 人事・総務部門の支援
- 子会社の人材採用活動の支援、従業員の教育・研修の実施
- 給与計算や労務管理に関する事務代行
- 広告宣伝活動の支援
これらの活動は海外子会社のために行われているにもかかわらず、そのコストを親会社が一方的に負担している場合、移転価格税制上の問題が生じることになります。
2. 移転価格税制におけるIGSの取扱いと法的根拠
IGSがなぜ税務上の問題となるのか、その背景にある移転価格税制の基本的な考え方と、根拠となる法律、そして最も注意すべきリスクについて解説します。
2.1. なぜIGSが移転価格税制の対象になるのか
移転価格税制の根本的な目的は、多国籍企業グループがグループ内の取引価格を意図的に操作することによって、税率の高い国から低い国へ利益を移転させることを防止することにあります。
例えば、税率30%の日本にある親会社が、税率10%の海外子会社に対して本来は100万円の価値がある経営指導サービスを無償で提供したとします。この場合、子会社は本来支払うべきであった100万円の費用を免れるため、その分利益が過大に計上されます。一方で、親会社は本来得られるはずだった100万円の収益を計上せず、サービス提供にかかったコストだけが費用となるため、利益が過少になります。結果として、グループ全体で見ると、利益が税率の低い国に100万円分移転し、企業グループとしての納税額が不当に圧縮されることになります。IGSはこのような利益移転に利用されやすい典型的な取引であるため、独立した第三者間で取引した場合の価格(独立企業間価格)で対価が授受されているかを厳しく問われるのです。
2.2. 根拠法令:租税特別措置法第66条の4(参考)
日本における移転価格税制の直接的な法的根拠は、「租税特別措置法」の第66条の4に規定されています 。この条文は、法人が国外関連者との取引を独立企業間価格で行わなかった結果、その法人の所得が減少している場合に、税務当局がその取引を独立企業間価格で行われたものとみなして所得金額を再計算し、課税できる権限を定めています。
租税特別措置法 第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例):法人が国外関連者(外国法人又は非居住者で当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数等の五十パーセント以上の数を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で行つた資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該取引の対価の額が独立企業間価格に満たない場合又は当該取引の対価の額が独立企業間価格を超える場合には、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
この条文中の「役務の提供」がまさにIGSを指しており、IGSに対して適切な対価を回収していない場合、この法律に基づいて課税が行われることになります。
2.3. 対価を回収しない最大のリスク:「寄附金」認定とその影響
IGSの対価を回収していなかった場合、税務調査で受ける指摘には大きく分けて2つのパターンがあり、そのどちらに該当するかによって企業が受けるダメージは天と地ほど異なります。これはIGSを理解する上で最も重要なポイントです。
パターン1:移転価格課税(所得の更正):これは、税務当局が「有償でのサービス提供の事実は認めるが、その対価が独立企業間価格よりも低い(またはゼロである)」と判断し、本来あるべき独立企業間価格との差額分だけ、親会社の所得を増額する処分です。この場合、親会社は日本で追徴課税を受けますが、一方でサービスを受けた子会社がある国との租税条約に基づき、二重課税を排除するための「相互協議(MAP)」を申し立てることも可能です。(通常、相互協議の合意手続きは長期に及ぶことが殆どですが)相互協議が合意に至れば、子会社側で対応する損金算入が認められるなどして、国際的な二重課税状態は解消される可能性があります。
パターン2:寄附金認定:これは、税務当局が「対価なく行われた経済的利益の供与」とみなし、その経済的利益の額を国外関連者に対する「寄附金」として認定する処分です。法人税法上、国外の関連会社に対する寄附金は原則としてその全額が損金の額に算入されません。つまり、移転価格課税と同様に親会社の所得が増加し、追徴課税が発生します。
ここでの最大の問題は、この寄附金認定による課税は、原則として相互協議の対象とならない点です。したがって、日本で寄附金として課税された部分について、相手国(子会社の所在地国)の税務当局が対応する調整(損金算入など)を行う義務はないため、グループ全体で見た場合に同一の所得に対して二重に課税された状態が永久に解消されなくなってしまうのです。これは企業グループにとって、回復不能なキャッシュアウトを意味します。
税務調査において、IGSに関する十分な説明や資料準備ができていない場合、安易に寄附金として認定されるリスクが高まります。この「寄附金認定リスク」こそが、IGSの対価管理を真剣に検討すべき最大の理由と言えるでしょう。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
3. IGSに該当しない活動:対価請求が不要な3つのケース
一方で、グループ内で行われる全ての支援活動に対して対価を請求しなければならないわけではありません。OECD移転価格ガイドラインや日本の事務運営指針では、受益者負担の原則に基づき、対価の請求が不要と考えられる活動類型が示されています。これらを正しく理解することは、不要な対価請求を避け、税務当局に対して適切な説明を行う上で重要です。
3.1. ケース1:株主活動
株主活動とは、親会社が子会社の株主という立場において、専ら親会社自身の利益のために行う活動を指します 。これらの活動は、子会社の事業運営に直接的な便益を与えるものではないため、子会社に対して対価を請求すべきIGSには該当しません。株主活動の典型例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 親会社自身の法人格の維持にかかる法務活動
- 親会社の株式上場に関連する活動や、株主総会の開催、増資手続きなど
- 親会社の投資家向け広報(IR)活動
- 親会社が法令等に基づき作成する連結財務諸表の作成・監査
ただし、実務上、株主活動とIGSの境界線は非常に曖昧であり、判断が難しいケースが少なくありません。例えば、親会社が子会社の業績をモニタリングする活動は、連結決算のためであれば「株主活動」ですが、子会社の経営改善を目的とした経営指導であれば「IGS」に該当する可能性があります。活動の「目的」が何であったかを、議事録などの客観的な資料で説明できるようにしておくことが極めて重要です。
3.2. ケース2:重複活動
重複活動とは、サービスの受け手である子会社が、既に自社で(あるいは外部の第三者に委託して)行っている活動と、内容が重複する活動を親会社が行う場合を指します 。子会社は親会社から追加的な便益を受けていないため、このような重複した活動は、原則として対価を請求すべきIGSには該当しません。
例えば、親会社の中央マーケティング部門がグローバルな広告宣伝の基本方針を作成していても、各国の子会社がそれぞれの市場に合わせて独自のマーケティング戦略を策定し、広告代理店も自ら選定しているような場合、親会社の活動は子会社にとって重複活動と見なされる可能性があります。ただし、企業グループの再編などに伴い、一時的に活動が重複する場合は例外的にIGSと認められることもあります。
3.3. ケース3:受動的関連による便益
受動的関連による便益とは、子会社が、有名で信用力の高い企業グループの一員であるという事実そのものから、意図的なサービス提供なしに受ける便益のことです 。例えば、親会社の信用格付が高いことにより、子会社が単独の場合よりも有利な条件で借入れができるといったケースがこれに該当します。このような受動的な便益は、特定の役務提供の対価として請求する性質のものではないため、IGSには該当しません。
しかし、ここにも注意点があります。この便益が「受動的」ではなく、親会社の「意図的かつ具体的な活動」によってもたらされた場合は、IGSと認定される可能性があります。例えば、親会社が子会社の特定の借入れに対して明示的に債務保証を行った場合や、グループ全体のブランド価値を高めるための具体的なグローバル・マーケティング活動を展開し、それによって子会社の売上が増加した場合などは、その活動がIGSとして対価請求の対象となる可能性があります。
4. IGS対価の算定方法:独立企業間価格の考え方
IGSに該当すると判断された活動について、次に問題となるのが「いくら請求すればよいのか」という対価の算定です。移転価格税制では、この対価を「独立企業間価格」で設定する必要があります。
4.1. 原則的な算定方法の概要
本来、IGSの独立企業間価格は、独立企業間価格算定方法(CUP法、RP法、CP法など)や、それに準ずる方法を用いて算定されます。例えば、比較可能な独立第三者間のサービス取引価格を見つけ出して比較したり(CUP法)、サービス提供にかかったコストに適切な利益マークアップを上乗せしたり(原価基準法、CP法)します。
しかし、特にサービスという無形の取引においては、比較可能な第三者間取引を見つけることが困難な場合が多く、独立企業間価格の算定は非常に複雑で難しい作業となりがちです。
4.2. 【重要】低付加価値グループ内役務提供(Low-Value-Adding IGS)の簡易算定法
このような実務上の困難さを背景に、OECDのBEPSプロジェクトの勧告を受け、日本の税制でも2018年の移転価格事務運営要領の改正により、「低付加価値グループ内役務提供(Low-Value-Adding IGS)」に関する簡易的な価格算定方法が導入されました。
これは、一定の要件を満たす付加価値の低い支援的なサービスについては、その提供にかかった総原価(直接費および間接費)の合計額に5%の利益マークアップを加えた金額を、独立企業間価格とみなすことができる、という画期的なルールです。これにより、対象となるサービスについては、複雑な価格算定を行うことなく、税務上の安全性を確保できる「セーフハーバー(安全港)」が設けられたことになります。
4.2.1. 低付加価値IGSの定義と適用要件
この5%マークアップの簡易算定法を適用するためには、対象となるサービスが以下の要件をすべて満たす必要がありますので、注意が必要です。
- 支援的な性質であること: 当該サービスが支援的な性質のものであり、企業グループの中核的な事業活動に直接関連するものではないこと。
- 重要な無形資産を使用しないこと: 当該サービスの提供に際して、提供者が独自の重要な無形資産(特許、ノウハウ、商標など)を使用・移転していないこと。
- 重要なリスクを負わないこと: 当該サービスの提供者が、重要なリスクの引受け、管理、創出を行っていないこと。
- 特定の活動に該当しないこと: 当該サービスが、後述する「対象外となる役務」のいずれにも該当しないこと。
- 非関連者向けに提供していないこと: 同様のサービスを、グループ外の独立した第三者に対して事業として提供していないこと。
このセーフハーバーは無条件に使えるわけではなく、納税者側がこれらの要件をすべて満たしていることを立証する責任を負う点に留意が必要です。
4.2.2. 対象となる役務・対象外となる役務の例
簡易算定法の対象となるか否かは、「グループの中核的事業活動かどうか」が大きな分かれ目となります。基本的には、バックオフィス的な支援業務が対象となり、企業の主たる価値創造プロセスに関わる活動は対象外とされています。
対象となる役務(低付加価値IGS)の例
- 会計、監査、予算管理に関する事務
- 債権・債務の管理に関する事務
- 人事(雇用、教育、給与計算など)、総務に関する事務
- ITシステムの保守・管理など(中核事業でない場合)
- 法務・税務のコンプライアンスに関する事務
対象外となる役務(高付加価値な活動)の例
- 研究開発(R&D)
- 製造、加工
- 販売、マーケティング、物流(原材料の購入を含む)
- 金融、保険、再保険
- 天然資源の探査、採掘、加工
上記の活動例はあくまで一般的な呼称であり、自社が行っているサービスがどちらに分類されるかについてはその実質的な活動を明確にしたうえ、慎重に検討する必要があります。
4.2.3. 文書化に関する留意点
低付加価値IGSの簡易算定法を適用する場合、その正当性を証明するために、以下の内容を含む書類を作成・保存することが義務付けられています。
- 役務提供者および受益者の名称・所在地
- 当該役務提供が低付加価値IGSの5つの要件を満たすことの説明
- 個々の役務提供の内容の説明
- 実際に役務提供が行われ、便益がもたらされたことの確認資料
- 総原価の算定根拠と、そのコストを各受益者に配分した方法の合理性の説明
これらの文書化は単なる推奨事項ではなく、セーフハーバーを適用するための必須要件です。文書がなければ、たとえサービス内容が要件を満たしていても、税務調査でその適用を否認されるリスクがあります。
4.3. 本来業務に付随する役務提供の取扱い
事務運営指針には、もう一つ、「本来の業務に付随して行われた役務提供」という類型が示されています 。これは、例えば機械を販売した親会社がその設置に関して付随的に行う技術指導など、役務提供を主たる事業としていない法人が本来の取引(この場合は機械販売)に関連して行うサービスを指します。
このような役務提供については、一定の条件下で、提供にかかったコストと同額(マークアップなし)を対価とすることが認められる場合があります。しかし、この取扱いの適用には厳しい制約があります。具体的には、以下のいずれかに該当する場合には適用できませんので、注意が必要です。
- その役務提供に要した費用の額が、提供者の総費用の中で相当な部分を占める場合
- 役務提供を行う際に、重要な無形資産を使用する場合
「付随的」の定義も曖昧であり、このコスト回収のみのアプローチは、低付加価値IGSの5%マークアップルールに比べて適用範囲が狭く、税務上のリスクも高いと言えます。安易にこの方法に依拠するのではなく、慎重な検討が求められるため、専門家へ相談することも検討されると良いかと思います。
5. 実務上の留意点と専門家への相談
最後に、IGSに関する税務リスクを管理するための実務的なアプローチと、専門家の活用について述べます。
5.1. グループ内役務提供ポリシーの策定と文書化の重要性
IGSに関する最も効果的なリスク管理策は、税務調査を待つのではなく、企業側が主体的にグループ内の方針(ポリシー)を策定し、それに基づいて運用することです。具体的には、以下のステップを踏むことが推奨されます。
- IGSの棚卸し: グループ内で行われている支援活動を網羅的に洗い出す。
- 活動の分類: 洗い出した活動を、「低付加価値IGS」「高付加価値IGS」「株主活動」などに分類する。
- 対価算定方法の決定: 分類に応じて、適切な対価の算定方法(例:5%マークアップ、個別算定など)を決定する。
- 文書化と契約: 上記のポリシーを文書化し、サービス提供者と受益者の間で役務提供契約を締結する。
このようなポリシーを策定し、それに基づいた運用と文書化を行うことで、税務調査官に対して、企業がIGSの問題を認識し、かつ合理的な根拠に基づいて真摯に対応していることを示すことができます。これは、対話の出発点を「何もしていない(寄附金リスク)」から「算定方法の妥当性に関する議論(移転価格課税)」へと引き上げ、致命的な寄附金認定リスクを大幅に低減させる上で極めて有効な防御策となり得ます。
5.2. 税務調査で指摘を受けないための準備
将来の税務調査に備え、日頃から以下の準備をしておくことが肝要です。
- 役務提供契約書の整備: 誰が、誰に、どのようなサービスを、いくらで提供するのかを明記した契約書を締結・保管する。
- コスト計算の根拠資料: サービス提供にかかった人件費や経費などの総原価を合理的に計算した根拠資料を保管する。
- 便益の立証資料: サービスを受けた子会社が、具体的にどのような便益を受けたのかを示す資料(メール、会議議事録、報告書など)を整理・保管する。
- 低付加価値IGSの適用要件資料: 簡易算定法を適用している場合は、その適用要件を満たしていることを証明する文書一式を準備する。
税務の世界では客観的な証拠が何よりも重要です。これらの資料を体系的に準備しておくことが、自社の立場を守るための最大の武器となります。
5.3. 専門家への相談を検討すべきタイミング
本稿ではIGSの基本的な考え方を解説しましたが、個別の事案を具体的なルールに当てはめる作業については専門的な判断を要する場面が多々あります。以下のような状況に当てはまる場合は、国際税務の専門家への相談を検討することをお勧めします。
- 自社にIGSに関するポリシーが全く存在しない。
- 特定の活動が、対価を請求すべきIGSなのか、株主活動なのかの判断に迷う。
- 研究開発や重要な無形資産が関わるような、高付加価値なサービスの対価算定が必要である。
- すでに税務調査の連絡を受けており、IGSについて説明を求められている。
国際税務の問題は、初期対応の巧拙がその後の結果を大きく左右します。もしこれらの点にご懸念があれば、まずは自社の状況を客観的に把握することが次の一歩となります。当サイトが運営する「みんなの国際税務Q&A」のような無料・匿名の場で専門家の一般的な見解を求めることも、具体的な税理士に相談する前の有益な情報収集の手段となり得ます。自社のリスクを正しく評価し、適切な対策を講じるための一助としてご活用ください。