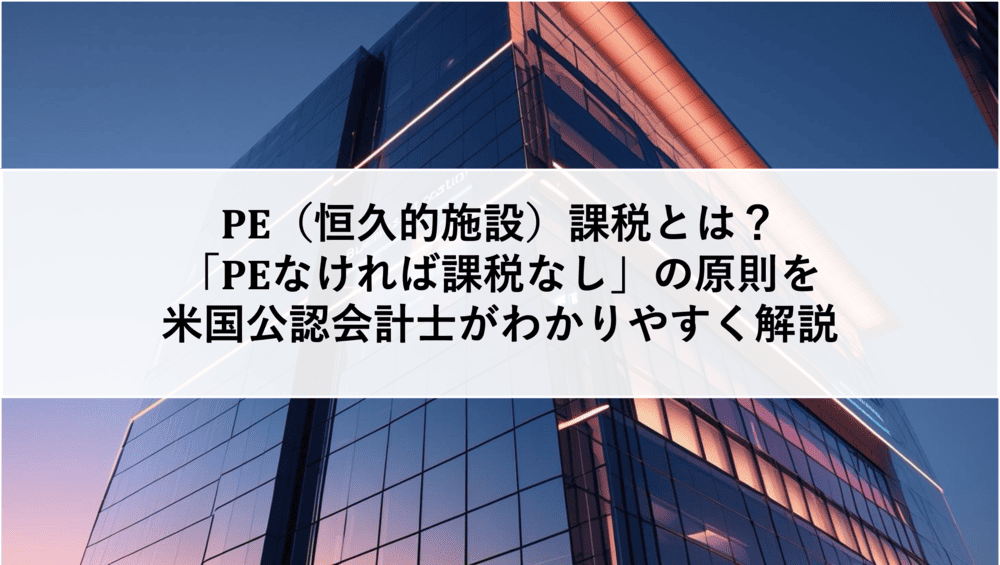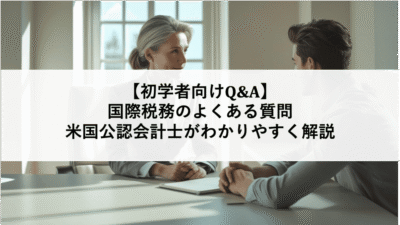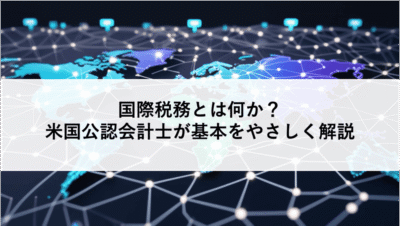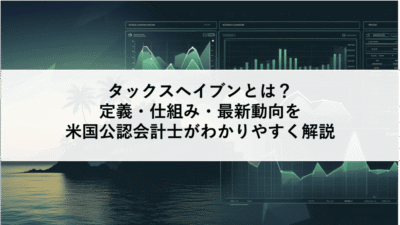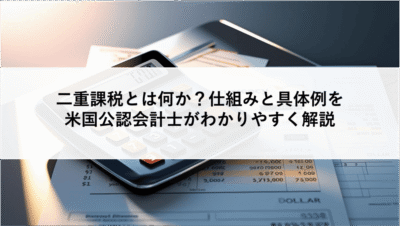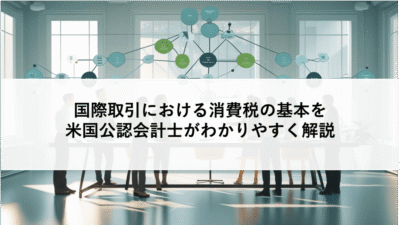グローバル化が進む現代において、海外に事業を展開することは多くの企業にとって重要な成長戦略です。しかし、国境を越えるビジネスには国内取引にはない特有のリスクが伴います。その中でも最も重要かつ基本的な概念の一つが「恒久的施設(Permanent Establishment、以下、PE)」です。
このPEという概念を理解することは、国際税務の第一歩と言っても過言ではありません。なぜなら、外国企業がある国で得た事業利益に対して、その国が課税できるかどうかを決定する国際的な基準が、このPEの有無にかかっているためです。
もしPEの知識なしに海外展開を進めてしまうと、ある日突然、進出先の税務当局から多額の追徴課税を受けるといった予期せぬ事態に陥りかねません。このような税務リスクは、企業のキャッシュフローを著しく悪化させ、時には海外事業の継続そのものを困難にすることもあります。
一方で、PEのルールは、国際的な二重課税を防止し、国家間の健全な投資や経済交流を促進するという重要な目的も担っています。各国が自国の都合だけで課税権を主張し始めると、企業は同じ利益に対して複数の国で税金を支払うことになり、国際取引が停滞してしまうからです。PEという共通の物差しを設けることで、課税関係に法的な安定性をもたらし、企業が安心して海外で活動できる環境を整えているのです。
恒久的施設(PE)課税の基本:「PEなければ課税なし」の大原則
国際的な事業活動に対する課税の仕組みを理解する上で、まず押さえるべきは「PEなければ課税なし」という国際税務の最も基本的な原則です。この原則がなぜ存在するのか、その背景から見ていきましょう。
国際課税の基本ルールを理解する
国が税金を課す権利(一般に、課税権と呼びます)には、大きく分けて二つの考え方があります。
一つは「居住地国課税」です。これは原則として、個人であれば「その人の住所がある国」、法人であれば「本店所在地がある国」が、その個人や法人が世界中で得たすべての所得(一般に、全世界所得と呼びます)に対して課税するという考え方です。日本の法人や居住者は、この原則に基づき、国内で得た所得も海外で得た所得も、原則として日本の税務当局に申告し納税する義務があります。
もう一つは「源泉地国課税」です。これは、所得が発生した国(一般に、源泉地国と呼びます)が、その所得に対して課税するという考え方です。例えば、日本の法人がアメリカで事業を行い利益を上げた場合、アメリカはその利益に対して課税権を主張します。
この二つの課税原則が衝突すると、「二重課税」という問題が生じます 。上記の例で言えば、日本の法人がアメリカで得た利益に対し、アメリカが源泉地国として課税し、さらに日本が居住地国として全世界所得の一部として課税すると、同じ利益に二度税金がかかってしまうのです。
「PEなければ課税なし」が意味すること
この二重課税問題を解決し、国際的な取引を円滑にするために設けられた国際的なルールが、「PEなければ課税なし」の原則です。
これは、外国企業がある国で事業活動を行っていても、その国内に「恒久的施設(PE)」と呼ばれる事業の拠点を持たない限り、その国(源泉地国)はその企業の「事業所得」に対しては課税できないというルールです。つまり、事業所得に関する課税権は、まずPEが存在する国に優先的に与えられる、という形で国家間の課税権の範囲を調整しているのです。
この原則は、経済協力開発機構(OECD)が策定した「OECDモデル租税条約」という国際的な雛形に明記されており、日本が世界各国と結んでいる多くの租税条約も、このモデルに準拠しています。
なぜこの原則が重要なのか:二重課税の回避と国際取引の促進
もしこの原則がなければ、企業は海外で商品を一つ売るだけでも、その国の税法に基づいて申告・納税をしなければならなくなるかもしれません。そのような状況では事務負担や税コストが膨大になり、企業は海外展開をためらってしまうでしょう。
「PEなければ課税なし」の原則は、企業がある国で本格的な事業活動を行うための物理的・人的な拠点(つまりPE)を設けて初めてその国での納税義務が生じる、という明確な線引きを提供します。これにより、企業は税務上の予測可能性を得ることができ、安心して国際的な投資や経済活動を行うことが可能になります。この法的安定性の確保こそが、この原則の最も重要な役割です。
事業所得と投資所得の課税の違い
ここで、国際税務の初学者が陥りやすい重要な注意点があります。「PEなければ課税なし」の原則は、あくまで「事業所得」に適用されるルールであるという点です。
配当、利子、使用料(ロイヤルティ)といった「投資所得」は、PEの有無にかかわらず、その所得が発生した国(源泉地国)で源泉徴収という形で課税されるのが一般的です。
例えば、日本の法人がアメリカにPEを持っていなくても、アメリカ企業から技術指導の対価としてロイヤルティを受け取れば、その支払い時にアメリカの税法に基づいて源泉徴収が行われます。
ただし、この場合も租税条約が重要な役割を果たします。租税条約では、これらの投資所得に対する源泉地国での税率の上限(限度税率)が定められていることがほとんどです。例えば、日本の国内法ではロイヤルティへの源泉税率が20%であっても、日米租税条約を適用すれば免税となる、といった具合です。
このように、国際課税では所得の種類によって課税のルールが大きく異なることを理解しておく必要があります。「PEがなければ海外では一切税金がかからない」というわけではないのです。この違いを認識することが、国際税務の正確な理解への第一歩となります。
PEとは具体的に何か?3つの基本類型を徹底解剖
「PEなければ課税なし」の原則を理解したところで、次に問題となるのは「では、何がPEに該当するのか」という点です。PEの定義は、日本の法人税法や所得税法といった国内法と各国と結んでいる租税条約の両方で定められています。両者の定義に違いがある場合は、租税条約の規定が国内法に優先して適用されるのが原則です。ここでは、多くの租税条約の基礎となっているOECDモデル租税条約の定義を基に、PEの3つの基本類型を解説します。
PEの定義:日本の国内法とOECDモデル租税条約
PEは一般的に「事業を行う一定の場所であって、企業がその事業の全部又は一部を行っている場所」と定義されます。この定義には、①事業を行うための施設(場所)が存在すること、②その場所が固定的(恒久的)であること、③その場所を通じて事業が行われていること、という3つの要素が含まれていると解釈されています。
この定義に基づき、PEは主に以下の3つの類型に分類されます。
類型1:支店PE(Branch PE)
これは最も直感的で分かりやすいPEの形態です。外国企業が事業を行うために設置した物理的な拠点がこれに該当します。具体的には、以下のようなものが例として挙げられます。
- 支店(Branch)
- 事務所(Office)
- 工場(Factory)
- 事業の管理の場所(Place of management)
- 作業場(Workshop)
- 鉱山、石油・天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
重要なのは、登記上の支店である必要はないという点です。実質的に事業の拠点として機能していれば、例えば継続的に使用しているホテルの客室などもPEに認定される可能性があります。この類型は物理的な存在が明確であるため、比較的認識しやすいですが、その場所が「固定的」であるかどうかが一つの判断基準となります。
類型2:建設PE(Construction PE)
建設工事現場や、機械の据付・組立工事なども、それらが一定期間以上継続する場合にはPEと見なされます。この「建設PE」の認定で最も重要な要素は「期間」です。日本の国内法および多くの租税条約では、その存続期間が「1年を超える」場合にPEに該当すると定めています。
税務当局が注視するのは、この期間要件を回避するための人為的な契約分割です。例えば、本来は1年半かかる工事を、1年と半年の二つの契約に分けて締結したとしても、実質的に一体のプロジェクトであれば、期間を通算して判断されます。形式的な契約内容だけでなく、プロジェクトの実態が問われる点に注意が必要です。
類型3:代理人PE(Agent PE)
支店PEや建設PEが「場所」を基準としたものであるのに対し、代理人PEは「人」の活動を基準とするもので、最も複雑でPEリスクが高い類型と言えます。これは、外国企業のために行動する代理人(Agent)が存在し、その代理人が「その企業の名において契約を締結する権限」を持ち、かつ、その権限を「恒常的に行使している」場合に、その代理人の存在自体がPEと見なされるというものです。物理的なオフィスがなくても、権限を持った営業担当者が国内で恒常的に契約活動を行っていればPEが存在すると判断され得るのです。
ただし、この代理人PEには重要な例外があります。それは「独立した地位を有する代理人」です。仲立人(ブローカー)や問屋(コミッション・エージェント)などが、その通常の事業の過程で活動を行う場合は、たとえ特定の外国企業のために契約を締結していたとしてもその外国企業のPEとは見なされません。代理人が法的にも経済的にも本人(外国企業)から独立しているかどうかが、判断の分かれ目となります。
近年のグローバルなビジネス環境の変化、特にリモートワークの普及やサプライチェーンの複雑化に伴い、PE課税のリスクの重心は大きく変化しています。かつては支店や工場といった目に見える「場所」のリスク(支店PE・建設PE)が中心でした。これらは不動産契約やプロジェクト管理で把握できるため、管理が比較的容易でした。
しかし現在、リスクの中心は目に見えない「活動」のリスク、すなわち代理人PEへとシフトしています。海外に出張する従業員や、現地で活動する営業担当者の「権限」や「行動」そのものが、予期せぬPE認定リスクを生み出す最大の要因となっているのです。これは、PEリスク管理が、もはや法務・税務部門だけの問題ではなく、営業部門や人事部門が密接に関わるべき経営課題であることを示唆しています。従業員の権限の範囲を契約書で明確に定め、実際の活動を適切に管理することが、現代のPEリスク管理の要諦と言えるでしょう。
これはPEに当たらない!「準備的・補助的活動」という例外
外国に事業を行うための固定的な場所があったとしても、それだけで直ちにPEに認定されるわけではありません。その場所で行われている活動が事業の本質的な部分ではなく、あくまで「準備的または補助的な性格」のものである場合には、PEには該当しないという重要な例外規定が存在します。
PE認定を免れる活動とは
多くの租税条約では、以下のような活動を行うためだけの場所は、PEに該当しないと例示されています。
- 企業に属する物品・商品の保管、展示または引渡しのためにのみ施設を使用すること。
- 保管、展示または引渡しのためにのみ、企業に属する物品・商品の在庫を保有すること。
- 他の企業による加工のためにのみ、企業に属する物品・商品の在庫を保有すること。
- 企業のために物品・商品を購入し、または情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
- 企業のために、その他の準備的・補助的な性格の活動を行うこと。
例えば、情報収集や市場調査、連絡業務のみを行う駐在員事務所は原則としてこれらの例外規定に該当し、PEとはなりません。
注意点:BEPS勧告を受けた税制改正と「全体として補助的」かの判断
しかし、この例外規定の適用にあたっては、近年、極めて重要な変化がありました。それは、OECD/G20が進めた「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクト」によるルールの厳格化です。
かつては、この例外規定を悪用し、事業の核となる重要な機能を細かく分割して、それぞれを「補助的活動」と主張することでPE認定を免れる租税回避スキームが存在しました 。例えば、巨大な物流センターを「商品の保管のためだけの施設」と主張するようなケースです。これに対処するため、BEPSプロジェクトの勧告(行動計画7)を受け、多くの国の国内法や租税条約が改正されました 。日本も平成30年度税制改正で対応しています。
改正後の重要なポイントは、リストにある活動に形式的に該当するかどうかだけでなく、その活動が企業全体の事業活動の中で、本当に準備的・補助的な性格のものかという実質で判断されるようになった点です。この変更は、PE認定の判断が、かつての形式的なチェックリスト方式から、事業全体における機能と重要性を分析する「実質主義」へと大きく舵を切ったことを意味します。例えば、インターネット通販企業にとっての物流センターは、もはや単なる「保管」施設ではなく事業の根幹をなす重要な機能の一部です。従い、現代のルールではPEと認定される可能性が非常に高くなります。企業は、自社の海外拠点の活動が自社のバリューチェーン全体の中でどのような役割を果たしているかを深く分析し、その「実施的な性質」を評価する必要があるのです。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
実務でよくあるPE認定リスクの具体例
理論的な定義を理解した上で、次に実務でどのような状況がPE認定のリスクを高めるのか、具体的なケーススタディを見ていきましょう。これらの事例は、多くの企業が意図せずPEリスクに直面する典型的なパターンです。
ケース1:駐在員事務所が営業活動を行っていると見なされるリスク
駐在員事務所は、その活動が市場調査、情報収集、連絡業務といった「準備的・補助的活動」に限定されていることを前提に、PEに該当しないとされています。
しかし、駐在員事務所のスタッフが良かれと思って営業活動に実務上深く関与してしまう事例が、PE課税のリスクを高めてしまうよくあるケースです。例えば、現地の顧客と価格交渉や契約条件の詰めの協議を行ったり、実質的な契約の最終合意を取り付けたりするような活動です。このような行為が恒常的に行われていると、税務当局は「その事務所は名目上は駐在員事務所だが、実態は営業拠点(支店)である」と判断し、PEとして認定する可能性があります。
特に、中国やインド、東南アジア諸国などでは、税務当局が駐在員事務所の活動を厳しく監視し、PE認定を積極的に行う傾向が見られます。また一般に、新興国では、PEの定義をいわば拡大解釈することにより課税権の根拠としようとする例が多くみられます。駐在員事務所の活動範囲については、社内で明確なガイドラインを設け、従業員に徹底させることが極めて重要です。
ケース2:海外子会社が親会社の「代理人PE」と認定されるリスク
海外に現地法人(子会社)を設立すれば、子会社は親会社とは別の法人格を持つため、原則として親会社のPEとはなりません。これは国際税務の基本です。しかし、ここにも「実質主義」の罠が潜んでいます。もしその海外子会社が独自の事業を持たず、実質的に親会社の指示通りに動く「手足」として機能している場合、税務当局はその子会社を親会社の「代理人PE」と見なす場合があります。
例えば、子会社の従業員が、親会社のために親会社の名で契約を締結する権限を恒常的に行使していたり、親会社の製品を販売するだけで自らは在庫リスクや事業リスクをほとんど負っていなかったりする場合です。このようなケースでは、子会社は独立した事業者ではなく、親会社の営業活動を代行しているに過ぎないと判断され、PE認定のリスクが高まります。これもインドや中国などで頻繁に問題となる論点です。
ケース3:海外での在宅勤務・リモートワークが「ホームオフィスPE」を生むリスク
ホームオフィスPEとは、働き方の多様化に伴い急速に顕在化してきたPEリスクです。日本企業の従業員が、海外にある自宅から恒常的に業務を行っている場合、その自宅(ホームオフィス)が、企業の事業のために継続的に使用される「固定的施設」と見なされ、PE認定されるリスクがあります。
OECDは、新型コロナウイルスのパンデミック下における不可抗力的な在宅勤務については、PEを構成しないという一時的なガイダンスを発表しました 。しかし、これはあくまで例外的な措置です。パンデミックが収束し、企業が恒久的な制度として海外リモートワークを認める場合、その従業員の自宅は企業の「事業の場所」として判断される可能性が十分にあります。この論点はまだ国際的にも議論が定まっておらず、非常に不確実性の高い領域となっています。
これらのケースに共通しているのは、法的な形式と事業の運営実態との間の乖離がPEリスクを生むという点です。税務当局は契約書や登記簿といった「形式」だけでなく、従業員が実際に何をしているのか、企業グループ内でどのような機能分担がなされているのかという「実態」を重視します。
したがって、PEリスクを管理するためには、法務・税務上の建付けと、実際のオペレーションを一致させることが不可欠です。具体的には、親子会社間の取引条件を定めた契約書を整備すること、駐在員や海外勤務者の役割と権限を雇用契約書や社内規程で明確に定義すること、そしてそれらの取り決めが遵守されていることを示す証拠(議事録、業務報告書など)を保管しておくことが、有効なリスク対策となります。
国際課税ルールの進化:BEPSプロジェクトとデジタル課税の衝撃
これまで見てきたPEの概念は、約100年にわたって国際課税の根幹をなしてきましたが、その伝統的な枠組みは今、大きな変革の波に直面しています。その背景にあるのが、経済のデジタル化と、それに伴うグローバル企業の租税回避問題です。
伝統的PE概念への挑戦
インターネットの普及により、企業は物理的な拠点(支店や工場)を持たなくても、国境を越えてサービスを提供し、巨額の利益を上げることが可能になりました。GAFAに代表される巨大デジタル企業は、まさにその典型です。
このようなビジネスモデルの前では、「物理的な拠点(PE)がなければ課税できない」という伝統的なルールは機能不全に陥ります 。企業が多くのユーザー(消費者)から収益を上げている国(市場国)に全く税金を納めないという事態が生じ、税の公平性の観点から大きな問題となりました。
BEPSプロジェクトによるPE定義の厳格化
この問題意識から、OECDとG20が主導して立ち上げたのが「BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト」です。このプロジェクトは、多国籍企業による租税回避を防止するための包括的な国際協定であり、その一環としてPEルールの見直しが行われました。
特に「BEPS行動計画7」では、PEの人為的な認定回避を防止することが目的とされました 。その結果、前述の通り、コミッショネア契約(問屋スキーム)などを通じた代理人PEの認定回避を封じるためのルール改正や、「準備的・補助的活動」の例外規定の厳格化が行われました。これらの改正内容は、「BEPS防止措置実施条約(Multilateral Instrument、通称MLI)」という画期的な枠組みを通じて、世界中の多くの二国間租税条約に一括で反映されています。これにより、PEの定義は国際的に、より実態を重視する形で厳格化されたのです。
デジタル課税の登場:「物理的拠点」の終わりと新たな「ネクサス(課税根拠)」
BEPSプロジェクトが既存のPEルールの「穴を塞ぐ」試みであったのに対し、さらに踏み込んだ革命的な改革が「デジタル課税」です。これは、OECDが主導する「第1の柱(Pillar One)」と呼ばれる新しい国際課税ルールです。
このルールの核心は、超巨大多国籍企業(年間連結売上高が200億ユーロ超など)を対象に、「PEなければ課税なし」の原則を根本から覆す点にあります。具体的には、物理的な拠点の有無にかかわらず、企業の製品やサービスの「市場となっている国(消費者がいる国)」に対して、新たな課税権を配分するものです 。そのために、「ネクサス(Nexus)」という新しい課税の根拠が導入されました。これは、物理的な拠点ではなく、市場国における一定規模以上の売上高(例えば100万ユーロ以上)を基準に課税権の有無を判断するものです。
この第1の柱は、国際税務の歴史における約100年ぶりの大転換であり、対象となる巨大企業にとっては、物理的なプレゼンスとは無関係に、世界中の市場国で新たな納税義務が発生することを意味します。
この一連の動きは、国際課税のルールが二極化しつつあることを示しています。中小企業を含む大多数の企業にとっては、今後もBEPSによって厳格化された伝統的なPEルールが適用され続けます。しかし、ごく一部の超巨大企業に対しては、それに加えて「第1の柱」という全く新しい概念の課税ルールが上乗せされるのです。この構造を理解することは、今後の国際税務の大きな潮流を掴む上で不可欠です。
もしPE認定されたら?課税の仕組みと対応策
万が一、海外の税務当局からPEが存在すると認定された場合、企業にはどのような影響が及び、何をすべきなのでしょうか。そのプロセスと対応策を解説します。
PEに帰属する所得(PE帰属所得)の計算方法
PE認定がなされると、その国(源泉地国)は、PEの活動によって生じた利益、すなわち「PE帰属所得」に対して課税することができます。
ここで重要なのは、PEの売上全体がそのまま課税対象になるわけではないという点です。PE帰属所得は、「独立企業原則(Arm’s Length Principle)」に基づいて計算されます 。これは、そのPEが本店から分離・独立した一個の企業であると仮定(擬制)した場合に、そのPEが得るであろう利益を算定するという考え方です。
この計算は非常に複雑です。PEが果たしている機能、使用している資産、負っているリスクなどを分析し、さらには本店とPEとの間の社内取引(例えば、本店からの技術指導や資金提供など)についても、あたかも第三者間の取引のように価格を設定し、損益を認識する必要があります 。これは、関連会社間の取引価格の妥当性を問う「移転価格税制」と同様の複雑な分析を社内の一部門に対して行うことを意味します。
申告・納税手続きの概要
PE認定された外国法人は、その国の国内企業と同様に、税務当局への登録、法人税申告書の提出、そして算出されたPE帰属所得に対する納税義務を負うことになります 。国によっては、所得の算定が困難な場合に、コストに一定の利益率を上乗せする「推計課税」が行われることもあり、税務当局との交渉が必要になるケースもあります。
二重課税の排除:外国税額控除の仕組み
PE認定によって源泉地国で納税すると、その利益は本国でも全世界所得の一部として課税対象となるため、二重課税が生じます。この問題を解決するため、通常、本国側で救済措置が用意されています。
最も一般的なのが「外国税額控除(Foreign Tax Credit)」という制度です。これは、外国(PE所在地国)で納付した法人税額を、自国(本店所在地国)で納付すべき法人税額から直接差し引くことができる仕組みです 。これにより、二重課税が排除または軽減されます。ただし、外国税額控除には控除できる金額に上限があったり、源泉地国での課税が租税条約の規定に適合しないと判断された場合には控除が認められなかったりと、必ずしも完璧に二重課税が排除できるとは限らない点には留意が必要です 。
予期せぬPE認定の本当のコストは、納税額そのものだけではありません。むしろ、PE帰属所得を算定するための専門家費用、税務調査に対応するための管理部門の膨大な時間、そして最終的な税額が確定するまでの事業上の不確実性といった、付随的な管理・コンプライアンスコストの方が企業にとって遥かに大きな負担となることが多いのです。この事実は、場当たり的な対応ではなく、専門家と共に事前の計画を立てることの重要性を強く物語っています。
まとめ:海外展開を成功させるためのPE課税の勘所
本記事では、国際税務の根幹をなす「恒久的施設(PE)」について、その基本原則から具体的なリスク、そして最新の動向までを包括的に解説してきました。海外展開を目指す、あるいは既に行っている企業にとって、PE課税の理解は避けて通れない重要な経営課題です。最後に、これからの海外展開を成功に導くための要点を改めて確認しましょう。
- 「PEなければ課税なし」は事業所得の基本だが、その適用は複雑化している。 この大原則は今なお国際課税の根幹ですが、投資所得には適用されない点や、例外規定が厳格化されている点を正確に理解する必要があります。
- PEリスクは「形式」ではなく「実態」で判断される。 税務当局は、登記や契約書の文面だけでなく、従業員が現地で何をしているのか、子会社が親会社からどれだけ独立して機能しているのかといった「事業の実態」を重視します。法的な建付けとオペレーションの実態を一致させることが、リスク管理の鍵です。
- PEの定義は常に進化している。 特にデジタル経済の進展やリモートワークの定着は、従来の物理的な拠点を前提としたPEの概念に大きな変化を促しています。最新の税制改正や国際的な議論の動向を常に把握しておくことが不可欠です。
- 予防的リスク管理が最善の策である。 PE認定されてからの対応は、多大なコストと時間を要します。海外進出の計画段階からPEリスクを織り込み、従業員の活動範囲を定めた社内規程の整備や、専門家による契約書のレビューなど、予防的な措置を講じることが最も効果的です。
PE課税の問題は、その複雑さと影響の大きさから、自己判断で進めるにはリスクが伴います。少しでも疑問や不安を感じた場合は、国際税務の専門家に相談することが、将来の予期せぬ損失を防ぎ、安全な海外展開を実現するための賢明な投資となります。国際税務総合研究所では、このような国際税務に関する皆様の疑問にお答えするため、無料・匿名で相談できる窓口「みんなの国際税務Q&A」を設けております。個別の税理士に相談する前の第一歩として、ぜひご活用ください。