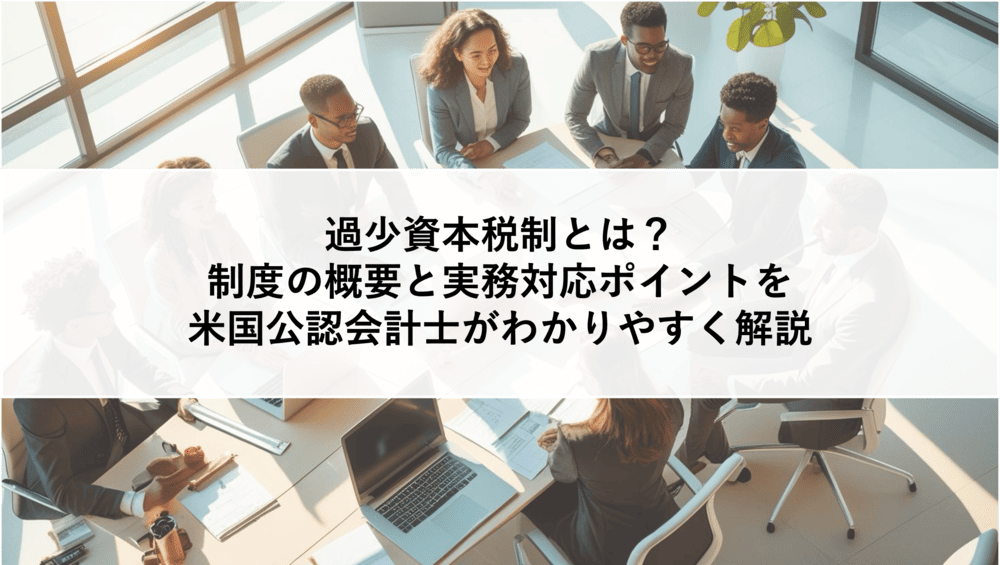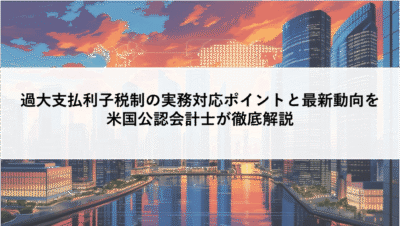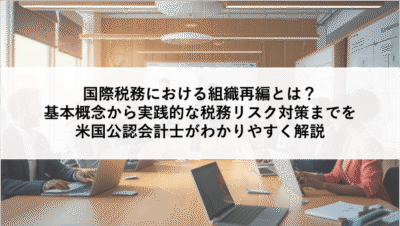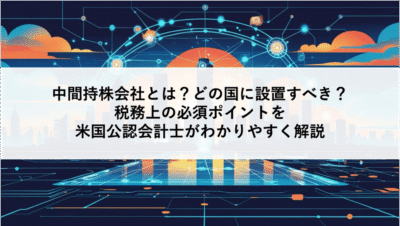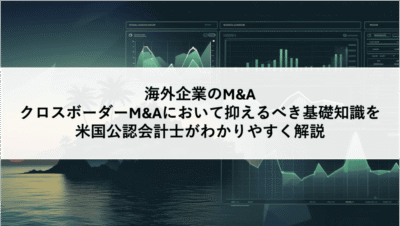過少資本税制は、海外親会社等(例:日本にある親会社)からの過大な借入による税負担の軽減を防ぐ重要な制度です。本記事では、国際税務の実務に精通した米国公認会計士が、制度の基本から具体的な計算方法、実務上の注意点、最新の規制動向まで、初学者にもわかりやすく徹底解説します。日本の親会社との資金のやり取りにおいて意図せず多額の追徴課税を受けないためにも、ぜひご一読ください。
はじめに:過少資本税制がなぜ重要視されるのか
グローバルに事業を展開する企業にとって、グループ内での資金調達は経営戦略の根幹をなす重要な活動です。特に、日本の親会社から海外の事業拠点である子会社へ貸付を行うことは、迅速かつ柔軟な資金供給手段として広く活用されています。しかし、この一見すると通常の企業活動に、国際税務の観点から大きなリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。
そのリスクの一つが「過少資本税制」です。この制度は、企業が海外の関連会社から資金を調達する際に、出資を意図的に少なくし、その代わりに過大な貸付を行うことで支払利子を増やし、税負担を不当に軽減しようとする行為を防止するためのものです。もしこの制度の適用対象となれば、支払った利子の一部が税務上の経費(損金)として認められず、結果として多額の追加納税が発生する可能性があります。
近年の国際税務の世界的な潮流として、OECD(経済協力開発機構)が主導するBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクト以降、各国税務当局は多国籍企業による利益移転に対して非常に厳しい姿勢で臨んでいます。これは、グループ企業間の取引価格の妥当性を問う移転価格税制だけでなく、過少資本税制が対象とするようなグループ企業間の金融取引にも当てはまります。
税務当局の監視が強化される中、単にルールを知らなかったという理由では通用しません。本記事では、この複雑でありながら実務上避けては通れない過少資本税制について、その仕組みから具体的な計算方法、そして税務調査で指摘を受けないための対策まで、専門家の視点から徹底的に掘り下げて解説していきます。
過少資本税制とは?制度の目的と仕組みを分かりやすく解説
過少資本税制を理解するためには、まず「なぜこのようなルールが必要なのか」という制度の根本的な目的を把握することが重要です。この制度は、企業の資金調達方法である「出資」と「貸付」の税務上の取扱いの違いを利用した、巧妙な租税回避行為を防止するために設計されています。
租税回避を防止するためのルール
法人税の基本的な仕組みでは、株主からの「出資」に対して支払われる「配当」は利益の分配と見なされるため、会社の経費(損金)にはなりません。一方で、銀行や関連会社からの「貸付(借入)」に対して支払う「利子」は、事業を行う上で必要な費用として扱われ、損金に算入することが認められています。支払利子が損金になれば、その分だけ会社の課税対象となる所得が減少し、結果として法人税の負担が軽くなるということです。
ではこの仕組みを、国境を越えた親子会社間の取引に適用するとどうなるでしょうか。例えば、日本の親会社がアメリカの完全子会社に100億円の資金を提供する場合を考えてみましょう。
- ケースA:全額を出資で賄う場合には、アメリカ子会社が利益を上げ、その結果として日本の親会社へ配当を行なったとしても、この支払いは税務上の損金になりません。従い、配当支払いを行なった米国子会社では損金として扱うことができない一方で、日本側で受け取った配当はそのまま日本の法人税の課税対象となります。
- ケースB:出資を1億円、残りの99億円を貸付で賄う場合には、米国子会社は日本の親会社に対して99億円の借入に対する支払利子を計上します。そして前述の通り、この支払利子は損金となるため、アメリカ子会社の課税所得を大幅に圧縮できます。結果として、「アメリカで生み出した利益を日本の親会社へ還元する」という目的において、配当の形であればアメリカで課税されるべきであった利益が「支払利子」という形で日本の親会社に移転し、配当のスキームを利用した場合に比べてアメリカの税収が減少することになります。
このように、「資本」を意図的に「過少」にし、その分を貸付で補うことで「税負担を軽減する」行為が過少資本税制の規制対象となる取引です。この制度は、このような取引に対して一定の制限を設け、過度な節税を防止することを目的としています。
制度の根拠条文(日本の場合)
過少資本税制は、通称であり、例えば日本の租税法上の正式名称は「国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例」といいます。この制度は、租税特別措置法第66条の5に定められています。条文では、内国法人が国外の親会社等から受けた貸付が、その親会社等からの出資額に比して過大であると判断された場合、その過大な部分に対応する支払利子等を損金の額に算入しない、と規定しています。これにより、実質的には出資と変わらないような過度な貸付を税務上も同様に取り扱い、課税の公平性を確保しているのです。
ここからは「日本国の過小資本税制」を前提に解説していきます
過少資本税制の適用対象となる法人とは?
過少資本税制が適用されるかどうかを判断する上では、まず自社が誰から資金を借り入れているのかを正確に把握する必要があります。この制度が対象とするのは、「国外支配株主等」および「資金供与者等」からの負債です。これらの定義は形式的な関係だけでなく実質的な関係性も含まれるため、特に注意が必要です。
「国外支配株主等」の定義
「国外支配株主等」とは、簡単に言えば、日本の内国法人を支配している海外の株主や関連会社のことです。この「支配」関係は、主に二つの基準で判定されます 。
- 形式基準(50%以上の株式保有関係) これは最も分かりやすい基準で、非居住者または外国法人が、内国法人の発行済株式等の50%以上を直接または間接に保有している関係を指します。直接の親子関係はもちろんのこと、例えば海外の同一の親会社によって支配されている兄弟会社関係も含まれます。
- 実質的支配関係 たとえ株式保有率が50%未満であっても、実質的に事業方針を決定できる関係にあれば「支配関係あり」と見なされます。租税特別措置法施行令第39条の13第12項では、以下のような事実がある場合に実質的支配関係があると定めています。
- 役員関係:内国法人の役員の半数以上、または代表権を持つ役員が、外国法人の役員や従業員である、またはあった者で、実質的に経営方針の決定を支配されている場合。
- 事業上の依存:内国法人の事業活動の重要な部分を、外国法人との取引(製造、販売、技術提供など)に依存している場合。
- 資金調達上の依存:事業資金の大部分を、外国法人からの借入や債務保証に依存している場合。
この「実質的支配関係」の判定には具体的な数値基準がないため、税務当局の判断に委ねられる部分が大きく、税務調査における重要な論点となり得ます。したがって、形式的に50%未満だからと安心せず、取引の実態を客観的に評価することが不可欠です。
「資金供与者等」の範囲
税務当局は制度の抜け道を塞ぐため、国外支配株主等からの直接的な借入だけでなく、第三者を介した実質的な資金提供も規制の対象としています。これを担うのが「資金供与者等」の定義です。例えば、以下のようなケースが該当する可能性があります。
- バック・トゥ・バック・ローン(Back to Back Loan):海外親会社が日本の銀行の海外支店に預金を行い、その預金を担保に日本の銀行が日本子会社に融資を行うケースです。こうした取引は、実質的には親会社が資金を提供していると見なされます。
- 第三者借入に対する債務保証:日本子会社が銀行から借入を行う際に、海外親会社がその債務を保証しているケースです。この保証によって子会社は融資を受けやすくなるため、これも親会社による実質的な資金供与の一環と見なされることがあります 。
このように、取引の形式だけではなくその経済的な実態が問われる点を十分に理解しておく必要があります。
【3ステップで理解】過少資本税制の判定と損金不算入額の計算方法
過少資本税制の適用判定と損金不算入額の計算は、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、3つのステップに分解することで理解しやすくなります。ここでは具体的な計算プロセスを順を追って解説します。
ステップ1:判定の基本となる「3倍基準」
過少資本税制が適用されるかどうかの基本的な判定ラインは「3倍基準」です。具体的には、内国法人の「国外支配株主等に係る平均負債残高」が、「国外支配株主等の資本持分額」の3倍を超えるかどうかで判断します。
この式が成り立つ場合には過少資本税制の適用対象となり、支払利子の一部が損金不算入となる可能性があります。この3:1という比率は、企業の財務健全性を示すデット・エクイティ・レシオ(Debt to Equity, D/E Ratio)の一つの目安として、グローバルに広く用いられている基準でもあります。
ステップ2:計算要素の算出方法
上記の判定式に含まれる二つの重要な要素、「平均負債残高」と「資本持分額」の計算方法を理解することが、正確な判定の鍵となります。
- 国外支配株主等に係る平均負債残高
これは、事業年度を通じて、国外支配株主等および資金供与者等からの負債が平均してどのくらいあったかを示す金額です。法律上は「合理的な方法」で計算すると定められていますが、実務では、期首と期末の残高を平均する方法や、より正確性を期すために各月末の残高を平均する方法などが用いられます。期末の一時点の残高だけではないのは、決算期末に一時的に負債を返済して比率を操作するといった租税回避行為を防ぐためです。 - 国外支配株主等の資本持分額
これは、国外支配株主等が内国法人の純資産のうち、どれだけの持分を有しているかを示す金額です。基本的には、以下の式で計算されます。
ただし、負債と同様に期末の純資産額だけでなく、事業年度中の平均的な純資産額を基に計算することが原則とされています 。
ステップ3:損金不算入となる支払利子等の計算式
ステップ1の判定で3倍基準を超えた場合、損金不算入となる支払利子等の額を計算します。注意すべきは、支払利子の全額が否認されるわけではないという点です。否認されるのは、あくまで「3倍を超えた過大な負債」に対応する部分のみです。計算式は以下の通りです。
計算式だけでは分かりにくいと思いますので、以下の条件で具体例を計算してみましょう。
- 国外支配株主等への平均負債残高:500億円
- 国外支配株主等の資本持分額:100億円
- 国外支配株主等への支払利子総額:20億円
- 判定: 平均負債残高500億円は、資本持分額100億円の3倍(300億円)を超えています。したがって、過少資本税制の適用対象となります。
- 超過負債額の計算: 超過負債額 = 500億円 – (100億円 × 3) = 200億円
- 損金不算入額の計算: 損金不算入額 = 20億円 × (200億円 ÷ 500億円) = 8億円
この結果、支払利子20億円のうち8億円が損金不算入となり、その分だけ課税所得が増加することになります。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
必ず知っておきたい「セーフハーバールール」と例外規定
過少資本税制には、納税者の実情に配慮した重要な例外規定が存在します。特に「セーフハーバールール」は、多くの企業にとって救済措置となり得るため、必ず理解しておきましょう。
全ての負債を対象とする3倍基準(セーフハーバールール)
国外支配株主等との関係だけで見ると負債比率が3倍を超えてしまう場合でも、直ちに過少資本税制が適用されるわけではありません。もう一つの判定基準として、会社全体の財務状況を見る「セーフハーバールール」が設けられています 。
具体的には、内国法人の総負債(国外支配株主等からの借入だけでなく、銀行など第三者からの借入もすべて含む)の平均残高が、その法人の自己資本の額(期末の純資産額)の3倍以下である場合には、過少資本税制は適用されないことになっています。このルールは、例えば「国外の親会社からの借入は多いものの、それ以外の借入が少ない」というケースを想定しており、会社全体としては財務的に健全と思われる企業が過少資本税制によって不利益を被ることを防ぐためのものです。
同業他社の負債資本比率を用いる方法
金融業やリース業など、そのビジネスモデルの特性上、一般的に高い負債比率で事業を運営することが当然とされる業種もあります。このような業種に対して一律に3倍基準を適用することは、事業の実態にそぐわない場合があります。そのため、租税特別措置法第66条の5第2項では3倍という比率に代えて、自社と事業内容や規模等が類似する他の内国法人の平均的な負債資本比率を用いることを認める例外規定を設けています。
しかし、この規定を適用するには客観的かつ信頼性のある比較対象企業を選定し、その企業の財務データを基に合理的な比率を算定し、税務当局に対してその正当性を立証する必要があります。適切な比較対象を見つけることは実務上非常に困難であり、データの入手や分析にも専門的な知見が求められるため、この例外規定の適用ハードルは極めて高いと言わざるを得ません。安易にこの規定に頼るのではなく、まずは原則である3倍基準やセーフハーバールールを念頭に置いた資金調達計画を立てることが賢明です。
実務上の重要論点と対策
過少資本税制を理解する上では、この制度単体だけでなく、移転価格税制や過大支払利子税制といった他の国際課税ルールとの相互関係を把握することが重要です。税務当局は国外関連者との金融取引に対して、複数の規制という「カード」を持っており、状況に応じて最も適切と思われるものを適用してくるケースが多くなっています。企業側は、これらのルールを包括的に理解し、多角的な視点からリスク管理を行う必要があります。
移転価格税制との関係
過少資本税制と移転価格税制は、どちらも国外関連者との取引における利益移転を防止する目的は共通していますが、着目するポイントが異なります。
- 過少資本税制:貸付の「元本」が資本に比して過大ではないか、という量に着目します。
- 移転価格税制:支払利子の「利率」が、独立した第三者間で設定されるであろう利率(独立企業間価格)と比較して高すぎないか、という価格に着目します。
例えば、海外親会社からの借入金に対して市場の水準よりも著しく高い金利を支払っている場合、たとえ負債比率が3倍以下であっても、移転価格税制の対象となり、その高すぎる利息部分が損金不算入となる可能性があります。また実務上、両方の制度が適用されうる状況ではまず移転価格税制によって適正な利率(独立企業間価格)が算定され、その適正利率に基づいて計算された支払利子額を前提として、次に過少資本税制の適用が判断される、という階層的な関係にあります。どちらか一方の有利な規定を選択できるわけではない点に注意が必要です。
過大支払利子税制との関係
BEPSプロジェクトの勧告を受け、日本では2019年度の税制改正で「過大支払利子税制」が大幅に強化されました 。これは、企業の支払利子等の合計額が、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)に近い概念である「調整所得金額」の20%を超える場合に、その超過額を損金不算入とする制度です。
この制度は、国外関連者への支払利子だけでなく第三者への支払利子も含むより広範なルールとなっています。過少資本税制と過大支払利子税制の両方の適用対象となる場合、計算の結果、損金不算入となる金額がより大きい方の規定が一つだけ適用されることになる点に注意しておきましょう。
税務調査で指摘されないための準備
税務調査においてこれらの複雑な規定に基づく指摘を受けないためには、日頃からの準備が何よりも重要です。以下に、3つの実務対応ポイントを解説します。
- 資本構成の合理性の文書化:なぜ出資ではなく借入という形で資金調達を行ったのか、その事業上の必要性や合理性を客観的に説明できる資料を準備しておくことが極めて重要です。例えば、設備投資計画や事業拡大計画に関する取締役会の議事録や稟議書などで、資金使途と調達方法の決定経緯を明確に記録しておくことが有効な防御策となります。
- 契約書等の整備:親子会社間の貸付であっても必ず金銭消費貸借契約書を作成し、貸付金額、返済期間、金利、担保条件などを明確に定めておくべきです。契約内容が曖昧であったり返済の実態が伴わなかったりすると、貸付そのものが実質的な贈与、すなわち「寄附金」であると認定されるリスクが生じます。国外関連者に対する寄附金と認定された場合、その全額が損金不算入となるだけでなく、二重課税を解消するための国家間の話し合いである「相互協議」の対象外となる可能性が高く、二重課税という企業にとって最も厳しい結果を招きかねません。
- 関連規定の総合的な検討:国外関連者との金融取引を行う際は、常に「過少資本税制」「移転価格税制」「過大支払利子税制」「寄附金課税」という主に4つの視点から取引全体のリスクを総合的に評価することが求められます。
まとめ:予期せぬ課税リスクを回避するために
本記事で解説した通り、過少資本税制は海外からの資金調達を行うグローバル企業にとって避けては通れない重要な税務リスクとなり得ます。その適用判定は単に負債と資本の比率を計算するだけの単純な作業ではありません。実質的な支配関係の有無、第三者を介した資金提供の実態、そして移転価格税制などの他の国際課税ルールとの複雑な相互作用を理解する必要があります。
国際税務のルールは年々複雑化しており、税務当局の執行も強化されています。自社の資金調達構造に少しでも不安がある場合や、これから大規模なグループ内金融取引を計画している場合には、問題が顕在化する前に、国際税務に精通した専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
国際税務総合研究所では、匿名・無料で専門家に質問できる「みんなの国際税務Q&A」を運営しております。個別の税理士に正式に相談する前の第一歩として、あるいは一般的な疑問の解消の場として、ぜひお気軽にご活用ください。皆様から寄せられた貴重なご質問とそれに対する私たち専門家の回答は、同じ悩みを抱える他の多くの企業の皆様にとっても有益な情報となります。