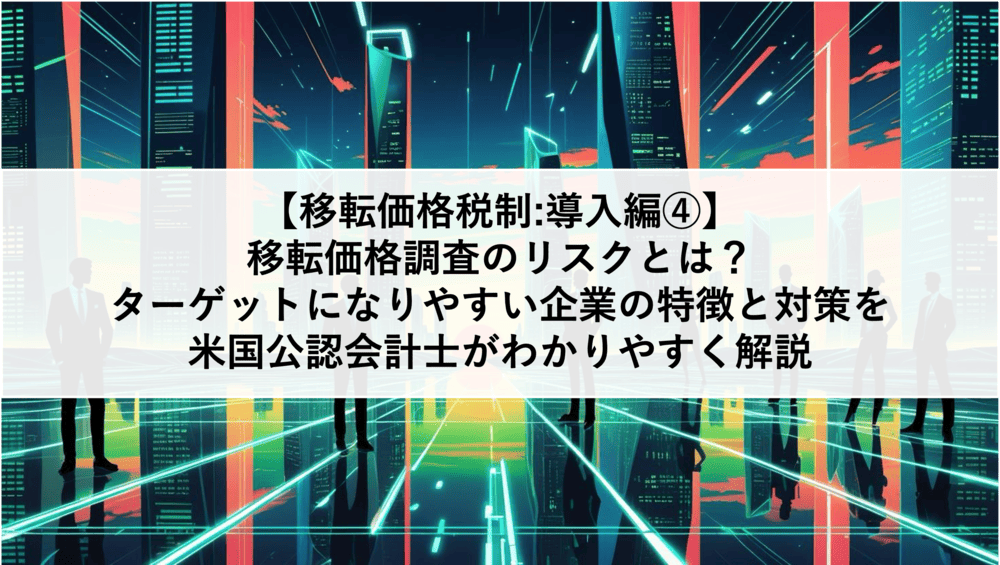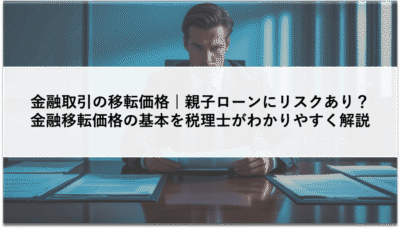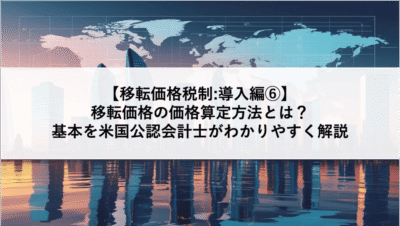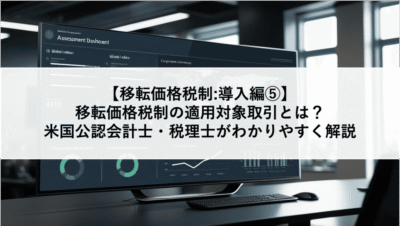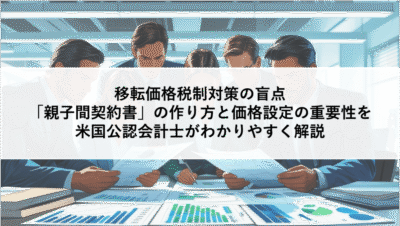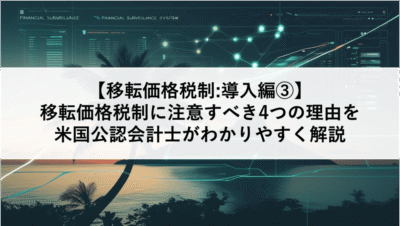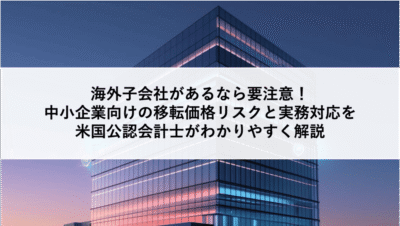海外に子会社や関連会社をお持ちの企業にとって「移転価格税制」は決して無視できない重要な税務リスクです。しかし、日々の業務に追われる中で「うちは取引規模も小さいし、大丈夫だろう」と、そのリスクを無自覚に抱えてしまっているケースが少なくありません。
移転価格に関する税務調査は一度指摘を受けると追徴税額が数億円、数十億円にのぼることも珍しくなく、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。重要なのは、税務当局がどのような点に着目し、どういった企業を調査のターゲットとみなしやすいのかを正しく理解し、備えることです。
この記事では、国際税務の実務に携わってきた専門家の視点から移転価格税制がもたらす具体的なリスク、そして税務調査の対象となりやすい企業の特徴について分かりやすく解説していきます。自社の状況と照らし合わせながら、リスクマネジメントの第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。
そもそも移転価格税制のリスクとは?なぜ対策が不可欠なのか
移転価格税制への対策を考える前に、まずそのリスクの深刻さについて改めて確認しておく必要があります。対策を怠った場合、企業は主に3つの大きな国際税務リスクに直面する可能性があります。前回の解説記事の復習になりますが、こちらでも軽くおさらいしておきましょう。
1. 深刻な「二重課税」の発生
移転価格調査で最も恐ろしいのが「二重課税」です。例えば、日本の税務当局が「海外子会社への販売価格が安すぎるため、日本の所得が不当に減少している」と判断した場合、日本で追加の税金(追徴課税)が課されます。
ここでよく勘違いされやすいのが、取引相手である海外子会社が所在する国の税務当局は日本の決定に関知しないという点です。子会社は、当初の安い価格を前提に既に税金を納めています。結果としてグループ全体で見ると、本来あるべき利益を大きく超える部分に対して日本と海外の両方で課税されてしまう「二重課税」状態に陥ることになります。
2. 追徴税額が多額になる傾向
移転価格調査は、個別の取引ではなく一定期間における国外関連者との取引全体が対象となります。たとえ一つひとつの製品の利益率のずれは小さくとも、取引総額が大きければ追徴課税の金額も巨額になります。
例えば、年間100億円の親子間取引で利益率が5%低いと指摘された場合、5億円の所得が日本から流出したと見なされます。さらに、この5億円に対して法人税が課されるだけでなく延滞税や過少申告加算税といった附帯税も加わり、最終的な納税額は非常に大きなものになり得ます。
3. 調査対応にかかる膨大な時間とコスト
移転価格調査は、他の税務調査と比べても特に時間と労力を要します。税務当局から取引価格の妥当性について説明を求められた場合、企業側は取引の実態、機能、リスク、使用資産などを詳細に分析し、その価格が独立した第三者間でも成立するものであることを客観的なデータに基づいて証明しなければなりません。このプロセスには、専門知識を持つ人材の確保や多大な資料作成が必要となり、経理部門や経営層に大きな負担を強いることになります。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
あなたの会社は大丈夫?移転価格調査のターゲットとなりやすい企業の特徴
税務当局は限られたリソースの中で効率的に調査を行うため、租税回避のリスクが高いと見られる企業に調査能力を集中させる傾向があります。具体的には、以下のような特徴を持つ企業がターゲットとなりやすいと考えられますので、自社の状況が当てはまるかどうか確認してみてください。
特徴1:海外子会社が黒字なのに、日本親会社が赤字または薄利
こちらは最も典型的な例です。グループ全体では利益が出ているにもかかわらず税率の高い日本にある親会社の利益が極端に少なく、税率の低い海外子会社に利益が偏っている場合、税務当局は「取引価格を操作して、意図的に利益を海外へ移転しているのではないか」という強い疑念を抱きます。特に、親会社が長年にわたり赤字を計上しているようなケースは調査対象として選定される可能性が非常に高いと言えます。
特徴2:海外子会社の利益率が、現地の同業他社と比較して著しく高い
海外子会社の業績が良いこと自体は素晴らしいことですが、その利益率が現地の同業他社の水準と比べて異常に高い場合も注意が必要です。これは、「親会社からの仕入れ価格が不当に安く設定されているのではないか」、あるいは「親会社が提供するサービスへの対価が低すぎる結果、子会社の利益が過剰になっているのではないか」と税務当局から推察される可能性が高い状況です。税務当局は公的なデータベースなどを活用して企業の利益率を分析しており、このような外れ値は容易に発見することができます。
特徴3:無形資産(ブランド、技術、ノウハウ等)の対価を十分に受け取っていない
日本親会社が長年かけて築き上げてきたブランド、特許技術、製造ノウハウといった「無形資産」を海外子会社が使用して事業を行い、利益を上げているケースは多いかと思います。この場合、子会社は無形資産の恩恵を受けているわけですから、その対価(ロイヤルティなど)を親会社に支払うのが当然です。
もし、この対価が支払われていない、あるいは著しく低い水準に設定されている場合、無形資産という価値ある資産を実質的に無償で海外に移転していると見なされ、税務当局から厳しい指摘を受ける可能性があります。
特徴4. 軽課税国・地域(タックスヘイブン)の子会社に利益が集中している
法人税率が著しく低い、いわゆる「タックスヘイブン」に設立した子会社にグループ全体の利益が集中しているようなケースも、税務当局が強い関心を示す典型例です。事業上の合理的な理由なく単に税負担を軽減する目的で利益が付け替えられていると判断されれば、移転価格課税の対象となるリスクは極めて高まります。
なお、これらの特徴に一つでも当てはまるからといって直ちに問題があるわけではありません。しかし、税務当局から見て「説明が必要な状態」であることは間違いなく、リスクを抱えている可能性を認識すべき状況といえます。
移転価格リスクマネジメントの具体的な進め方
自社にリスクの可能性があると認識した場合、具体的に何から手をつければよいのでしょうか。移転価格におけるリスクマネジメントの基本的な流れは、以下の2つのステップに集約されると考えます。
ステップ1:国外関連者との取引価格の妥当性を検証する
まず行うべきは、海外子会社との取引価格が「独立企業間価格」の考え方に照らして妥当な水準にあるかを確認することです。
独立企業間価格とは、「もしその取引が、全く資本関係のない独立した第三者との間で行われたとしたら、どのような価格が設定されるか」という基準で算定される価格を指します。
簡単にいえば、子会社に製品を100円で販売している場合、全く無関係の第三者にも同じ条件で100円で販売するのかという視点で検証します。もし第三者には150円で販売するのであれば、100円という価格設定の合理性を説明するのは困難といえます。なお、「独立企業間価格」を算定する方法は複数定められており、取引の内容に応じて最も適切な方法を選択する必要があります。
ステップ2:価格設定の根拠を文書として準備する(移転価格文書)
ステップ1で価格の妥当性を検証した後は、その結論に至ったプロセスと根拠を「移転価格文書(ローカルファイル)」としてきちんと文書化しておくことが極めて重要です。
移転価格文書は、税務調査で説明を求められた際に自社の価格設定の正当性を主張するための「防御」となります。具体的には、以下のような内容を記載します。
- 企業の事業概況(企業が属する業界や産業の分析を含む)
- 国外関連者との取引内容
- 独立企業間価格を算定するために行った機能分析・リスク分析
- 独立企業間価格の算定方法の選定理由
- 具体的な価格算定のプロセス
これらの文書をあらかじめ準備しておくことで、万が一の税務調査の際にも当局に対して論理的かつ客観的な説明を行うことが可能となり、不必要な指摘を避けることにつながります。
より確実性を求めるなら「事前確認(APA)」の活用も視野に
移転価格のリスクは、その性質上どうしても不確実性が残ります。この不確実性を抜本的に解消するための手段として「事前確認(APA: Advance Pricing Arrangement)」という制度があります。
これは、企業がこれから行おうとする国外関連者との取引価格の算定方法について、事前に税務当局に申請し、その妥当性の確認(いわば「事前の承認」)を受ける制度です。税務当局との間で合意が得られれば、その合意内容に従って申告を行っている限り、将来の移転価格調査で指摘を受けるリスクを原則として排除することができます。
特に、日本と取引相手国の両方の税務当局が参加する「二国間APA」を利用すれば、双方の国での移転価格リスクを同時に解消できるため非常に効果的です。申請には相応の準備と時間が必要ですが、取引規模が大きい、あるいは取引が長期間にわたって継続するような場合には、活用を検討する価値が十分にある制度と考えます。
まとめ
今回は、移転価格税制がもたらすリスクと税務調査のターゲットとなりやすい企業の特徴、そしてリスクマネジメントの進め方について解説しました。移転価格リスクにおける最大の問題は「リスクがあることにそもそも気づいていない」状態です。まずは本記事で挙げた特徴と自社の状況を照らし合わせ、客観的にリスクを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
移転価格税制の対応は専門性が高く、判断に迷う場面も少なくありません。具体的なリスク評価や文書化についてお悩みの場合は、国際税務の専門家に相談することをお勧めします。