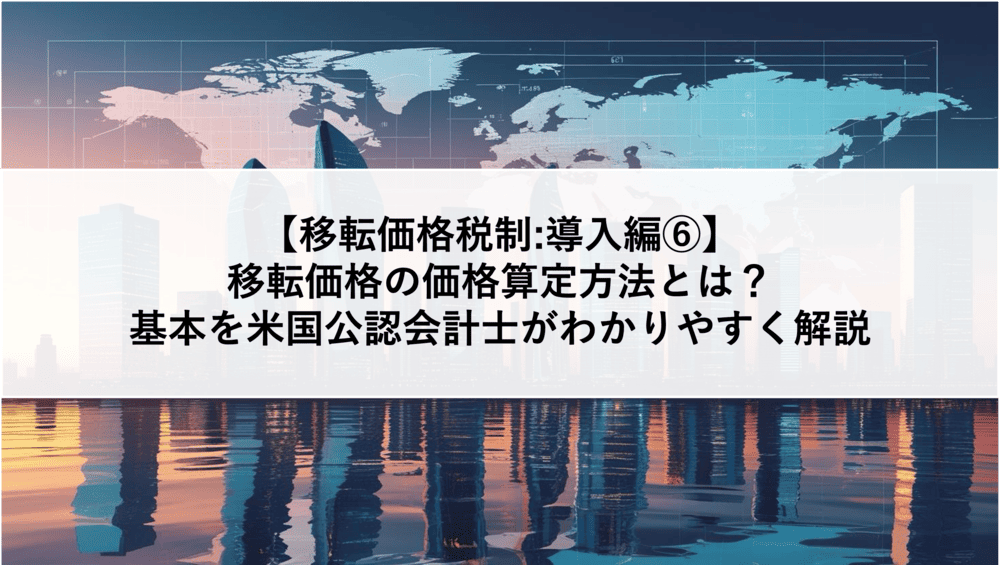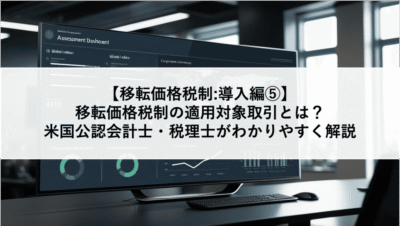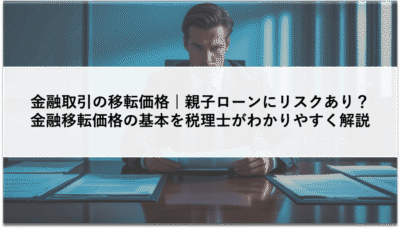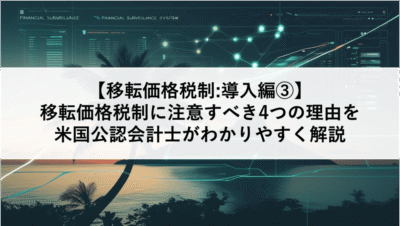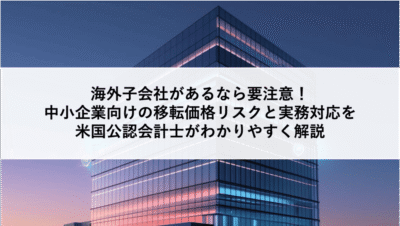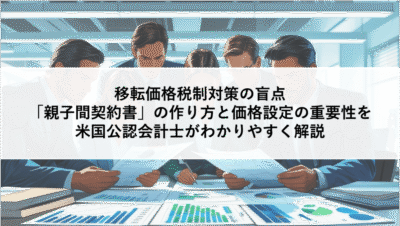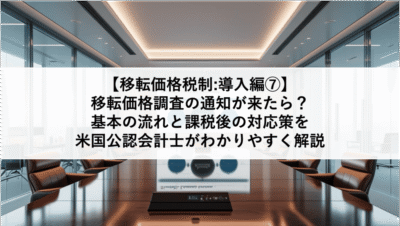海外子会社との取引価格を設定する際、「どの価格が税務上適切なのか」と悩まれている経理担当者の方や経営者の方は少なくないと思います。この価格設定の根拠となるのが「移転価格の算定方法」です。この記事では、国際税務の実務に長年携わってきた専門家が、日本の税法で定められている6つの移転価格算定方法について、その概要から具体的な考え方、そして実務上の選び方までを丁寧に解説していきます。初学者の方から実務で悩まれている方まで、移転価格算定の全体像を掴んでいただける内容です。
【移転価格税制:導入編①】移転価格とは?全体像が5分でわかる | 米国公認会計士・税理士がわかりやすく解説
移転価格算定の基本|なぜ独立企業間価格が重要なのか
まず、移転価格算定の目的と基本的な考え方について確認しておきましょう。
海外にある子会社や関連会社との取引を「国外関連取引」と呼びます。この取引価格(移転価格)を意図的に操作することで、利益を税率の低い国へ移転させ、グループ全体の税負担を軽減することができてしまいます。
こうした利益移転を防ぐために、税務当局は「国外関連取引は、全く資本関係のない第三者との間で取引した場合に成立するであろう価格で行うべき」というルールを設けています。この第三者間で成立する価格のことを「独立企業間価格(Arm’s Length Price)」と呼びます。
税務調査においては企業の国外関連取引がこの独立企業間価格で行われているかが厳しくチェックされます。もし独立企業間価格から乖離した価格設定であった場合、その差額分の所得が日本で追徴課税されることになります。これが移転価格税制の基本的な仕組みであり、適切な算定方法に基づいて独立企業間価格を決定することが極めて重要なのです。
最適な算定方法を選ぶ「ベストメソッドルール」とは
独立企業間価格を算定するため、日本の法人税法では6つの方法が規定されています。しかし、企業が自由に好きな方法を選べるわけではありません。
国外関連取引の内容や親子会社が果たしている機能、比較対象となる取引データの入手可能性などを総合的に考慮し、「最も適切な算定方法」を一つ選定する必要があります。この原則を「ベストメソッドルール」と呼びます。算定方法を選定する際に考慮すべき要素には、以下のようなものがあります。
- 移転価格税制の対象となる取引と選定した第三者間取引の類似性の程度
- 算定に用いるデータの信頼性や入手可能性
- 算定の基礎となる仮定の妥当性
- 国外関連者と第三者の機能やリスクの比較可能性
それでは、具体的に6つの算定方法を一つずつ見ていきましょう。これらの方法は、大きく「伝統的取引基準法(基本三法)」、「取引単位利益法」、そして「その他の方法」に分類できます。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
伝統的取引基準法(基本三法)
伝統的取引基準法は取引される製品やサービスの価格または売上総利益に直接着目する方法で、独立価格批准法(CUP法)、再販売価格基準法(RP法)、原価基準法(CP法)の3つが含まれます。理論上、最も直接的な算定方法とされています。
1. 独立価格批准法(CUP法:Comparable Uncontrolled Price Method)
独立価格批准法(CUP法)は国外関連取引と全く同じような状況下で、独立した第三者間で行われた取引の価格を独立企業間価格とみなす方法です。「似たような外部取引の価格をそのまま参考にする」と考えると分かりやすいでしょう。
CUP法は最も直接的で、理論上は優先度が高い方法とされています。比較対象となる取引には、自社が第三者と行っている取引(Internal CUP)と全くの第三者同士が行っている取引(External CUP)があります。しかし、CUP法を適用するには製品の種類、品質、取引数量、契約条件、市場の状況などが国外関連取引とほぼ同一である必要があります。従い、現実には対象取引と酷似した取引を見つけることは極めて困難であるため、実務で適用できるケースは限定的となっています。
ちなみに、CUP法と類似する算定方法としてCUT法(Comparable Uncontrolled Transaction)というものもあります。CUP法とCUT法はどちらも価格水準を比較しますが、価格設定の対象が異なります。CUP法は有形資産取引の移転価格(つまり、製商品の価格そのもの)の決定に重点を置いている一方で、CUT法は無形資産の移転価格(具体的には金利、手数料、ロイヤルティの割合など)の決定に重点を置いている点に違いがあります。
2. 再販売価格基準法(RP法:Resale Price Method)
再販売価格基準法(RP法)は、製品の買い手(例えば、海外の販売子会社)がその製品を独立した第三者に販売した価格(再販売価格)を起点に計算する方法です。
具体的には、その再販売価格から再販売者が得るべき「通常の利潤(売上総利益)」を差し引くことで、仕入価格である独立企業間価格を逆算します。超単純化すると、「売値から利益を引いて、仕入値を決める考え方」と考えると分かりやすいかと思います。
「通常の売上総利益率」は、その販売子会社や類似の機能を持つ独立した卸売業者などが第三者との取引で稼得している売上総利益率を参考にします。この方法は海外子会社が比較的単純な販売機能のみを担っている場合に適しています。
3. 原価基準法(CP法:Cost Plus Method)
原価基準法(CP法)は、製品の売り手(例えば、海外の製造子会社)が製品を製造するためにかかったコストを起点に計算する方法です。
具体的には、その製品の製造原価に売り手が稼得すべき「通常の利潤(売上総利益)」を上乗せ(プラス)することで、販売価格である独立企業間価格を算定します。超単純化すると、「コストに利益を足して売値を決める方法」と考えると分かりやすいかと思います。
「通常の原価基準利益率」は、その製造子会社や類似の機能を持つ独立した製造業者などが第三者との取引で稼得している原価に対する利益率を参考にします。この方法は海外子会社が製造活動を行っている場合に適しています。再販売価格基準法(RP法)とは価格算定の起点が逆になると理解するとよいでしょう。
取引単位利益法
基本三法の適用が困難な場合に検討されるのが「取引単位利益法」です。これは取引ごとの価格や総利益ではなく、取引から得られる営業利益に着目する方法です。
4. 取引単位営業利益法(TNMM:Transactional Net Margin Method)
取引単位営業利益法(TNMM)は、国外関連取引から得られる営業利益率が独立した第三者が同種の取引から得ている営業利益率と同水準になるように価格を算定する方法です。「似た会社の利益率に合わせて取引価格を決める考え方」と理解しておくと分かりやすいかと思います。
そして実務上、最も頻繁に利用されているのがこのTNMMです。なぜなら、CUP法のように完全に同一の取引を探したりRP法やCP法のように比較可能性を厳密に担保したりすることが難しい場合でも、公開されているデータベースなどから類似企業の財務データ(営業利益率など)を見つけやすいためです。
一般的に、親子会社のうち、より単純な機能(例えば、製造のみ、販売のみなど)を担っている側を「検証対象法人」とし、その法人の営業利益率が類似の機能を持つ独立企業群の営業利益率のレンジ(四分位レンジなど)に収まるように価格を調整します。
比較指標としては売上高営業利益率が一般的ですが、販売活動の効率性を測る指標として、売上総利益を営業費用で割った「ベリーレシオ(Berry Ratio)」等が用いられることもあります。この辺りの話は専門的な話になりますので、また別の記事で解説できればと思います。
5. 利益分割法(PS法:Profit Split Method)
利益分割法(PS法)は、親子会社間の国外関連取引によって生じた全体の利益(合算利益)をそれぞれの会社が果たした貢献度に応じて分割し、その結果得られる利益額が実現されるように取引価格を算定する方法です。「合計の利益を親子会社の貢献度で分け合う方法」と理解しておくと分かりやすいかと思います。
この方法は、親子会社双方が研究開発やブランド構築といった重要な無形資産の形成に関与しており、両者が不可分に結びついて利益を生み出しているような複雑な取引に適用されます。TNMMでは一方の機能が単純であることを前提としますが、利益分割法(PS法)は双方がユニークな貢献をしている場合に適します。
貢献度を測る指標としては、研究開発費、広告宣伝費、人件費、使用資産額などが用いられますが、その分割基準の客観性を合理的に説明する必要があります。比較対象企業を探す必要がないという利点がある一方、貢献度の算定が恣意的になりやすいという難しさも伴いますので、この分割基準の客観性や貢献度の比率は税務当局が非常に厳しくみるポイントでもあります。
その他の算定方法
上記の5つの方法に加え、特定の取引類型で用いられる方法があります。
6. DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)
DCF法は、2019年度の税制改正により独立企業間価格の算定方法の一つとして法令上明確化されました。これは主に、特許権や商標権、ノウハウといった「無形資産」の移転価格を算定する際に用いられます。
具体的には、その無形資産が将来生み出すと予測されるキャッシュ・フローを算出し、それをリスクなどを考慮した割引率で現在価値に割り引くことで無形資産の価値(取引価格)を評価する方法です。「将来稼ぐであろうお金を今の価値に直して価格を決める方法」と理解しておくと分かりやすいかと思います。こちらの方法は将来の事業計画や収益予測といった多くの仮定に基づくため、算定プロセスの客観性や予測の合理性を丁寧に立証することが求められる点に注意が必要です。
まとめ:最適な算定方法の選定は専門家との連携が鍵
今回は、移転価格税制における独立企業間価格の6つの算定方法について解説しました。移転価格の算定方法の選定と文書化は高度な専門知識を要する複雑なプロセスになります。どの方法が自社の取引に最適なのか、どのように価格の妥当性を立証すればよいのか、判断に迷う場面も多いかと存じます。ご自身のケースで具体的な検討が必要な場合や少しでも不安を感じる点がございましたら、国際税務の専門家に相談することをお勧めします。当研究所が運営する「みんなの国際税務 質問箱」では、匿名・無料で専門家からの一般的な見解を得ることも可能ですので、情報収集の一環としてご活用ください。