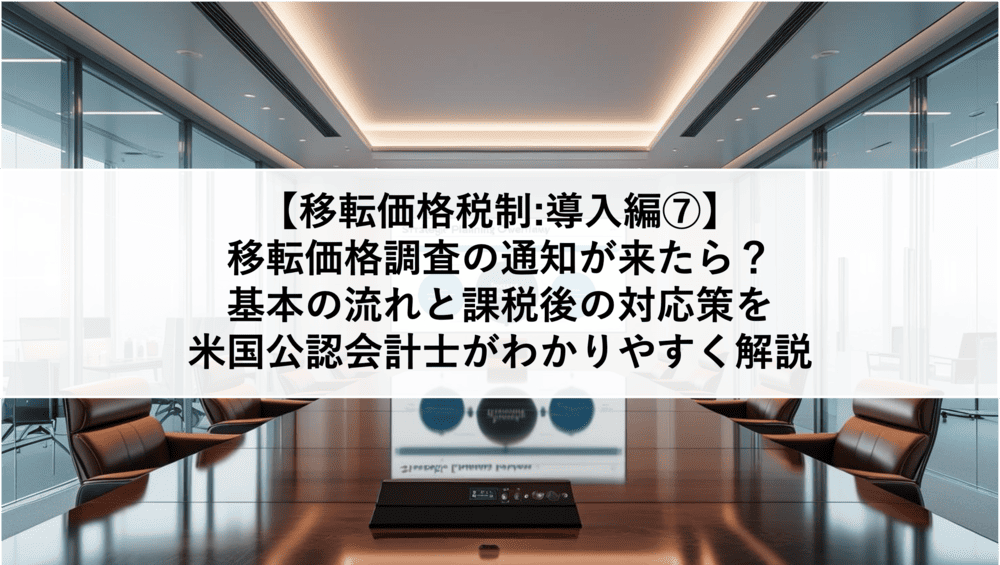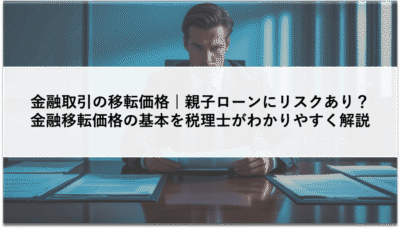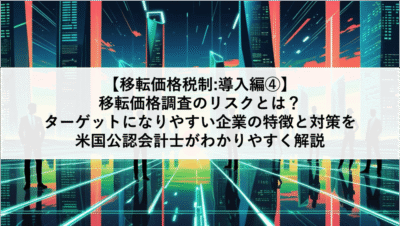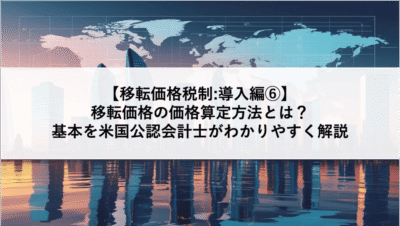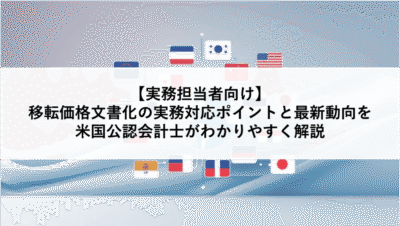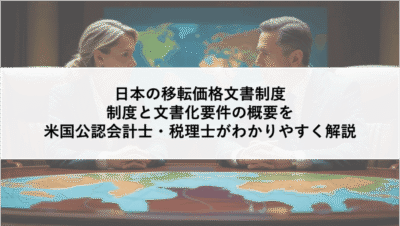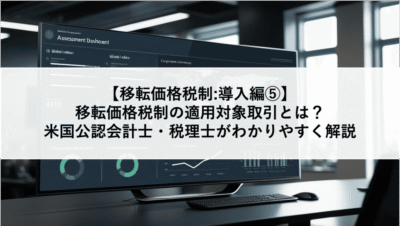海外に子会社や関連会社を持つ企業にとって、「移転価格税制」は避けては通れない重要な税務リスクの一つです。日々の取引において適正な価格設定を心がけていても、ある日、税務当局から「移転価格について調査を行います」という連絡が来る可能性はゼロではありません。
多くの場合、この一報は経理や財務の担当者にとって大きなプレッシャーとなるかと思います。通常の税務調査とは何が違うのか、どのような準備が必要でどれくらいの期間がかかるのか、そして万が一課税を指摘された場合はどうすればよいのか。様々な疑問や不安が頭をよぎるはずです。
この記事では、国際税務の実務に携わってきた専門家の視点から、移転価格調査の基本的な仕組みから万が一課税された場合の具体的な対応策まで、順を追って分かりやすく解説していきます。調査の全体像を事前に理解しておくことで、いざという時にも冷静かつ的確に対応できるよう、本記事をご活用いただければ幸いです。
移転価格調査とは?法人税調査との関係性を理解する
まず押さえておくべき最も重要な点は、移転価格調査が独立した調査として存在するわけではないということです。
原則は「法人税調査の一部」として実施される
法律上、移転価格調査は法人税の調査の一部として位置づけられています。したがって、通常は法人税の税務調査と同時に実施されます。
税務調査官が企業の事務所などを訪れて帳簿や資料を確認する「実地調査」の際に、法人税全般の確認とあわせて海外の関連会社との取引価格(移転価格)の妥当性についても検証が進められるのが一般的です。
そのため、法人税調査の連絡があったにもかかわらず、調査の終了時まで移転価格について特段の指摘や質問がなかった場合、「その事業年度については移転価格税制上の問題はなかった」と一旦は解釈することができます。
同意によって別々に調査が行われるケースも
ただし、ここには例外もあります。国税当局が「事前に納税者の同意」を得た場合には、法人税調査とは別に移転価格調査のみを単独で実施することが可能となっています。
実務上、税務当局から法人税調査とは切り離して移転価格調査を実施することへの同意を求められた場合、それは本格的な移転価格調査が開始される可能性が極めて高いことを意味します。この場合、調査はより専門的かつ深掘りされる傾向にあります。
調査期間が長期化しやすい理由
移転価格調査は通常の法人税調査と比較して、調査期間が1年から2年、あるいはそれ以上と長期化するケースが少なくありません。
その主な理由として、国外の関連者との取引実態の解明や比較対象となる他社のデータ分析、場合によっては相手国の税務当局への情報照会など、国内の調査だけでは完結しない複雑な手続きが必要になるためです。調査対応の担当者としては、長期的な対応が必要になることを念頭に置いておく必要があります。
移転価格課税を受けた場合の2つの選択肢
移転価格文書の整備など、どれだけ入念にリスク管理を行っていても、税務調査の結果として国外関連者との取引価格が不適切であると判断され、「移転価格課税(更正処分)」を受ける可能性は残ってしまいます。
移転価格課税が行われると、日本で算定された適正な利益に基づいて追加の法人税が課されます。しかし、取引の相手方である海外子会社の利益は現地の税法に基づき計算されているため、結果として、一つのグループ取引から生じた利益に対して日本と海外の両方で課税されてしまう「二重課税」の状態に陥ります。
この国際的な二重課税を解消するため、企業には大きく分けて2つの選択肢が用意されています。
- 相互協議による対応的調整
- 国内法に基づく不服申立て・税務訴訟
以下で、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
選択肢1:相互協議による国際的な二重課税の排除
移転価格課税によって生じた二重課税を解消するための、最も基本的な手続きが「相互協議」です。
相互協議とは?
相互協議(MAP:Mutual Agreement Procedure)とは、租税条約の規定に基づき、両国の税務当局間で二重課税の排除について協議を行う手続きのことです。日本で移転価格課税を受けた場合、納税者は日本の税務当局(国税庁)に対して相互協議の申立てを行うことができます。
この申立てが受理されると、日本の国税庁と取引相手国の税務当局の間でどちらの国の課税が正しかったのか、あるいは双方でどのように所得を調整すべきかを直接話し合うことになります。
「対応的調整」による二重課税の解消
相互協議の結果として両国の税務当局が合意に至った場合、「対応的調整」という形で二重課税が解消されることがあります。
例えば、日本の親会社が100の所得更正(追徴課税)を受けたとします。相互協議の結果、この課税が妥当であると両国で合意されれば、取引相手国の税務当局は、現地の海外子会社の所得を100減額し、それによって納め過ぎとなった税金を還付します。これにより、グループ全体として二重に課税されていた状態が是正されるイメージです。
ただし、相互協議はあくまで当局間の話し合いであるため、必ずしも合意に至るとは限らない点には留意が必要です。また、合意に至るまでには数年の期間を要することも珍しくありません。
選択肢2:国内法に基づく不服申立て・税務訴訟
もう一つの選択肢は、日本の国内法に則って課税処分の取り消しを求める方法です。これは、通常の税務調査の結果に不服がある場合と同様の手続きです。
具体的には、まず国税不服審判所に対して「審査請求」を行い、それでも納得のいく結果が得られなければ裁判所に「税務訴訟」を提起して司法の判断を仰ぐことになります。
移転価格課税への対応としては前述の相互協議が基本となりますが、以下のようなケースでは国内での不服申立てが重要な選択肢となります。
- 取引相手国と日本との間に租税条約が締結されていない場合
- 相互協議で両国当局が合意に至らなかった場合
- 日本の税務当局による課税処分そのものが、事実認定や法解釈の点で誤っていると強く確信している場合
特に、租税条約がない国との取引で課税された場合には相互協議という手段が使えないため、この国内での不服申立てが唯一の対抗手段となります。
まとめ
今回は、移転価格調査の基本的な仕組みと万が一課税された場合の対応策について解説しました。移転価格調査への対応は専門性が非常に高く、対応には高度な知識と経験が求められます。調査の連絡を受けた段階、あるいはその前の段階から、国際税務に精通した専門家と方針を協議しながら進めることが、自社の利益を守る上で極めて重要です。
もし移転価格に関して少しでもご不安な点や、具体的なご質問がございましたら、専門家への相談をご検討ください。当サイトが運営する「国際税務なんでも質問箱」では、匿名・無料で専門家への質問が可能です。個別の税理士に相談する前の第一歩としてご活用ください。