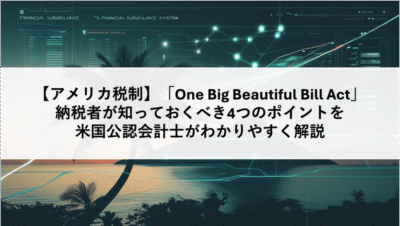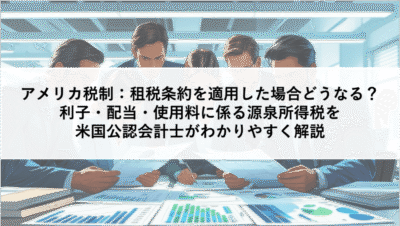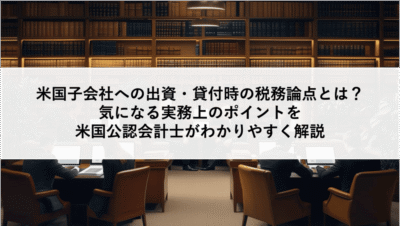2025年、米国の税務環境は歴史的な転換点を迎えました。2017年に第一次トランプ政権下で敷かれた「Tax Cuts and Jobs Act(以下、”TCJA”)」の多くの規定が失効する”タックスクリフ”が目前に迫る中、米国議会はこれに対応するための大規模な法案を可決しました。それが、2025年7月4日に成立した予算調整法案、通称「One Big Beautiful Bill Act」(以下、OBBBA)です。この法律は、単にTCJAの時限規定を延長するだけでなく、米国の経済成長と労働者支援を目的とした新たな税制を導入する、極めて広範な税制改革となっています。
米国に子会社を持つ、あるいはこれから事業展開を計画している日系企業にとって、このOBBBAの内容を正確に理解することは必須事項となるでしょう。法人税率の安定化、設備投資や研究開発への強力なインセンティブ、そして国際課税ルールの恒久化と再編(実務影響を踏まえ、本記事では割愛します)は、貴社の米国事業における投資計画、資金調達、サプライチェーン戦略、そして最終的な税負担に直接的な影響を及ぼします。これらの変更は、日本親会社の連結財務諸表にも波及する可能性があり、経営レベルでの深い理解が求められます。
本記事では、米国で国際税務の実務経験を積んだ米国公認会計士の視点から、このOBBBAが日系企業の米国事業に与える実務的なインパクトを、特に重要性の高い4つのポイントに絞って、基礎から分かりやすく解説します。なお、本法には個人所得税に関する改正(チップや残業代への優遇措置など)も含まれていますが、本稿では法人税および国際課税に焦点を当てて解説を進めます。
1. 法人税率21%の恒久化
OBBBAがもたらした最も大きな恩恵の一つは、税制の「安定性」と「予測可能性」を企業に提供した点にあります。これは単なる減税の継続以上の戦略的価値を持ちますので、以下で詳しく解説します。
2017年に成立したTCJAにおいて連邦法人税率は35%から21%へ引き下げられましたが、当初は期限付きの措置でした。今回のOBBBAはこの21%を恒久化し、税率変動の懸念を取り除いています。結果として昨年からの税率の変更は無いということになるため、税務実務への大きなインパクトはありませんが、裏を返せば、日系企業は今後10年、20 年といった長期スパンの設備投資や事業拡大を立案する際、安定した税率を前提にキャッシュフローと投資回収をより精緻にシミュレーションできるようになりました。
結果として、日系企業は米国子会社の将来キャッシュフロー予測の精度を格段に高めることが可能となります。この「税金キャッシュフローの安定性確保」は、日系企業が米国市場をより戦略的な投資先として位置づけ、大規模かつ長期的なコミットメントを行う上での心理的・財務的な障壁を取り除くという、大きな実務インパクトを持ち得ます。
2. 研究開発(R&D)費の即時損金算入の復活
2つ目の重要な変更点は、研究開発(R&D)費の取り扱いです。R&D費については、OBBBAにより、2025年1月1日以降から2029年12月31日以前に開始する課税年度に支払われた(もしくは発生した)米国内のR&D支出について、納税者は①全額を即時費用化、②60か月以上で均等償却、あるいは③10年間にわたり償却、の3つの選択肢からいずれかを選択することが可能になりました(従来は資本化義務がありました)。そして、これらの選択は「新たに発生したR&D支出」ごとに、その発生した年度の確定申告時に行うことができます。つまり、過去に発生し、すでに償却方法が確定した支出への遡及的な変更は不可能ですが、翌年以降に新たに発生した支出には別の償却方法を年度単位で再選択できるという柔軟性が認められています。そのため、たとえば黒字年度には即時費用化、赤字年度には償却の選択をすることで、年度ごとに税金のキャッシュフローを最適化が可能です。従い、米国内にR&D拠点を配置するインセンティブが一層高まると予想されています。
補足ですが、米国外で発生するR&D費用については従来どおり15年間で資本化・償却し続ける必要がありますので、ご注意ください。
国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!
以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。
ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。
3. 投資促進の追い風:設備投資を後押しする3つのインセンティブ
OBBBAは、米国内での投資を強力に後押しする3つの重要な優遇税制を含んでいます。以下で一つずつ解説していきます。
100%ボーナス減価償却(”Bonus Depreciation”)
TCJAで導入され、2023年から段階的に縮小が始まっていた100%ボーナス償却(即時償却)が、OBBBAによって復活しました 。これにより、企業は2025年1月20日以降から2029年12月31日以前に取得し使用を開始した資産であれば、取得初年度に全額を損金算入することが可能です。
これにより、投資初年度の課税所得が大幅に圧縮されることで納税額(税金キャッシュアウト)が減少し、その節税分をさらなる再投資や運転資金へ機動的に充当が可能になります。特に、工場の新設や生産ラインの大規模な刷新など、多額の設備投資を行う製造業の日系企業にとってこれは極めて強力なキャッシュフロー改善策となり得ます。実務上の注意点としては、ボーナス償却の適用条件である”期間条件”を満たすため、企業は当該資産を”いつ取得し、いつ使用開始したのか”を都度記録し、明示的に税務当局へ証明できるようにしておく必要があります。
適格生産資産(”Qualified Production Property”)
4. 財務戦略への影響:支払利子損金算入制限(163(j)条)の緩和
企業の資金調達戦略に直接影響を与える重要な改正が、支払利子の損金算入制限に関するルールの緩和です。
支払利子控除制限ルールの基礎知識
まず、内国歳入法典163(j)条の基本的な役割を理解することが重要です。この規定は、企業が過大な支払利子を計上して税負担を不当に軽減する、いわゆる「アーニングス・ストリッピング」を防止するためのものです。具体的には、各事業年度において損金算入できる支払利子の額に上限を設けています。
計算基準の変更(EBITからEBITDAへ)が意味すること
TCJAの下では、2022年以降、この損金算入の上限額を計算する際の基礎となる所得が「EBIT(利払前・税引前利益)」に設定されていました。これは多くの企業にとって非常に厳しい基準といえます。OBBBAでは、この計算基準を2025年1月1日以降から2029年12月31日以前に開始する課税年度については「EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)」の基準に戻すことを決定しました 。EBITDAは、EBITに減価償却費(Depreciation)と無形資産償却費(Amortization)を足し戻して算出される指標です。したがって、損金算入限度額を計算する際の基礎となる所得の額がEBITベースよりも大きくなり、結果として損金算入できる支払利子の上限額が引き上げられることになります。
設備投資やM&Aで多額の借入を行う企業への影響
この改正は、工場建設、M&A、あるいは大規模な事業再編などで多額の借入を行う、資本集約的な日系企業にとって大きな朗報です。特に、前章で解説した100%ボーナス償却を適用する企業は、初年度に巨額の減価償却費を計上するため、EBITベースでは利子控除が厳しく制限されていました。しかし、EBITDAベースに戻ったことでその制限が大幅に緩和され、デットファイナンス(借入による資金調達)の税務上のインセンティブが高まります。これにより、日系企業はより柔軟な財務戦略を米国で展開することが可能になります。
まとめ
今回のOBBBAは、TCJAの時限措置を単に延長するにとどまらず、設備投資・研究開発・資金調達といった企業の中核的な経済活動に対し、税務上のインセンティブを大幅に強化する改正となりました。法人税率の恒久化をはじめ、R&D費の即時損金算入の再導入や100%ボーナス減価償却の復活、さらには支払利子控除制限の緩和など、キャッシュフローに直接影響する変更が網羅的に盛り込まれており、米国市場における事業展開を検討する企業にとって追い風となる内容です。
もっとも、これらの優遇措置の活用には、各制度の適用時期や要件を正確に把握し、他国の税制との相互作用を含めた慎重な事前シミュレーションが不可欠です。特に、日本のCFC税制との整合性や、連結ベースでの税金キャッシュフローへの影響などを視野に入れ、米国子会社単体にとどまらないグループ全体での最適化を図る必要があります。こうした点を踏まえ、個別の投資・資金調達・税務戦略を検討する際には、顧問税理士や国際税務の専門家と連携しながら、適切なアクションプランを策定していくことが重要です。
OBBBAの影響は多岐にわたり、各規定が相互に複雑に影響し合います。特に、米国の新税制と日本の税制(タックスヘイブン対策税制など)との相互作用を考慮した総合的な分析は、高度な専門知識を要します。表面的な理解だけで重要な経営判断を下すと、予期せぬ追徴課税やペナルティといった大きなリスクを負いかねません。早い段階で、米国税務に精通した専門家に相談し、自社の状況に合わせた最適な対応策を検討することが、最終的に税務コストを最小化し、コンプライアンス・リスクを管理する上で最も賢明な選択となります。
当サイトでは、匿名・無料で質問できる相談窓口「みんなの国際税務Q&A」も設けておりますので、ご活用いただければ幸いです。本稿で解説した内容についてさらに具体的なご質問のある場合は、お気軽にお問い合わせください。
この記事で参照されている法律やガイダンスは、執筆時点のものです。最新の情報については、米国議会や内国歳入庁(IRS)の公式発表をご確認ください。